
山名氏
二つ引両/桐に笹
(清和源氏新田氏流) |


|
山名氏は武家の名門清和源氏の一支流で、新田義重の子義範が上野国多胡郡山名に住し、山名三郎を称したことに始まる。義範は『平家物語』にみえる山名次郎範義、『源平盛衰記』に山名太郎義範と記されている人物と同一人であろう。さらに『東鑑』にも山名冠者義範の名が見える。義範は源平の争乱期にあって源氏方として活躍、「平氏追討源氏受領六人」の一人として伊豆守に任じられた。
『東鑑』には義範をはじめ、山名中務俊行・山名小太郎重国・山名進二郎行直・山名進二郎行忠ら山名名字を名乗る人物が散見し、中務俊行は「謀反の風聞により捕らえられて誅された」とある。山名氏には源姓のほかに、武蔵七党の一である有道姓児玉党山名氏があり、『東鑑』にみえる「行」文字を通字とする武士は、有道姓山名氏と思われる。
山名氏の飛躍
源姓山名氏の場合、鎌倉幕府草創期に初代義範が活躍したものの、以後、歴史の表面にはほとんどあらわれてこない。おそらく、里見・大井田・大島氏らの新田一族諸氏とともに新田氏を惣領として仰ぎ、多胡郡の領地経営に汗を流していたのであろう。
鎌倉時代、源氏将軍家が三代で断絶してのちの幕府政治は、執権北条氏が次第に実権を掌握していった。鎌倉時代中期を過ぎるころになると、北条得宗家の専制政治が行われるようになり、幕府創業に活躍した御家人の多くが滅亡あるいは没落していた。源氏一門では足利氏が勢力を保つばかりで、山名氏の惣領新田氏は逼塞を余儀なくされていた。一門の山名氏らの状況も推して知るべしで、のちに山名氏の家名をあげた時氏が「元弘より以往は、ただ民百姓のごとくにて、上野の山名といふ所より出侍しかば、渡世のかなしさも身の程も知にき」と語ったことからもうかがわれる。しかし、政氏の妻が上杉重房の娘であることなどから、武家としてそれなりの地位は保っていたとみられる。
山名氏が大きく飛躍するきっかけとなったのは、元弘・建武の争乱であった。ときの当主政氏と嫡男時氏は惣領新田義貞に従って行動したようだ。元弘三年(1333)に鎌倉幕府が滅亡、翌建武元年に後醍醐天皇の親政による建武の新政が発足した。倒幕の功労者である新田義貞が勇躍して上洛すると、時氏ら山名一族もそれに従ったようだ。ところが、新政の施策は武士らの反発をかい、一方の倒幕の功労者である足利尊氏に武士の期待が寄せられた。
やがて、北条氏残党による中先代の乱が起ると、尊氏は天皇の許しを得ないまま東国に下向、乱を鎮圧すると鎌倉に居坐ってしまった。天皇は新田義貞を大将とする尊氏討伐軍を発向、尊氏は箱根竹の下において官軍を迎え撃った。この戦いにおいて、政氏・時氏父子は義貞を離れて尊氏に味方して奮戦、尊氏方の勝利に大きく貢献した。かくして、山名氏は新政に叛旗を翻した尊氏に従って上洛、尊氏が北畠顕家軍に敗れて九州に奔ると、それに従って尊氏の信頼をかちとった。九州で再起をはたした尊氏が上洛の軍を起こすと、時氏は一方の将として従軍、湊川の合戦、新田義貞軍との戦いに活躍した。
尊氏が京都を制圧すると後醍醐天皇は吉野に奔って南朝をひらかれ、尊氏は北朝を立てて足利幕府を開いた。時代は南北朝の対立へと推移したのである。建武四年(1337)、時氏の一連の軍功に対して、尊氏は伯耆守護に補任することで報いた。かくして、時氏は山名氏発展の端緒を掴んだのであった。
激動の時代を生きる
暦応四年(1341)、幕府の重臣で出雲・隠岐両国の守護職塩冶高貞が尊氏に謀反を起こし、領国に走るという事件が起った。時氏は嫡男の師義とともに高貞を追撃すると出雲において高貞を誅した。その功によって、時氏は出雲・隠岐、さらに丹後の守護職に補任された。高貞の謀反は、幕府執事高師直が高貞の妻に懸想したことが原因というが、真相は不明である。その後、出雲・隠岐守護職は高貞と同族である佐々木高氏(道誉)が任じられ、時氏は丹波守護に補任された。そして、貞和二年(1345)には侍所の頭人(所司)に任じられ、山名氏は赤松・一色・京極氏と並んで四職の一に数えられる幕府重臣へと成り上がった。
やがて尊氏の弟直義と執事師直の対立から、幕府は直義派と師直=尊氏派とに二分され、観応元年(1350)、観応の擾乱が勃発した。擾乱は師直の敗北、さらに直義の死によって終息したが、幕府内部の抗争により時代はさらに混乱の度を深めていった。はじめ時氏は尊氏に味方していたが、のちに直義派に転じ、直義が謀殺されたときは任国の伯耆に戻っていた。時氏は義詮方の重鎮である出雲守護職佐々木道誉をたのんで尊氏方への復帰を画策したが、道誉の態度はすげなく、腹をくくった時氏・師義らは出雲に侵攻すると出雲と隠岐を制圧した。
山陰地方に大勢力を築いた時氏らは、南朝方と呼応して文和二年(1353)には京に攻め入り、京を支配下においた。そして、直義の養子である直冬に通じて義詮方と対抗した。以後、直冬党として幕府と対立を続けたが、貞治二年(1363)、安芸・備後で直冬が敗れて勢力を失うと大内氏につづいて幕府に帰順した。帰順の条件は、因幡・伯耆・丹波・丹後・美作五ケ国の守護職を安堵するというもので、「多くの所領を持たんと思はば、只御敵にこそ成べかれけれ」と不満の声が高かったと伝えられる。いずれにしろ、幕府の内訌、南北朝の動乱という難しい時代を、山名時氏はよく泳ぎきったのである。
時氏には嫡男の師義を頭に多くの男子があり、子供らの代になると山名氏の守護領国はさらに拡大されることになった。
一族の内訌
応安三年(1370)、時氏は師義に家督を譲ると翌年に死去、山名氏の惣領となった師義は但馬と丹後の守護職を継承、あとは弟氏清らに分かった。永和二年(1376)、師義が死去したのち、家督は弟の時義が継承した。時義は若年より父時氏に従って兄師義らとともに行動、いちはやく上洛を果たして幕府の要職の地位にあった。師義死去のときは伯耆守護であったが、家督を継いだ時義は但馬守護職にも任じ、さらに、備後・隠岐の守護職も兼帯した。
この時義の時代に山名一族は大きく躍進、次兄義理は紀伊・美作守護職、四兄氏清は丹波・山城・和泉三ケ国の守護職、師義の実子で甥の満幸が丹後・出雲守護職、同じく甥の氏家が因幡守護職に任じられ、一族で守護領国は十二ヶ国*を数えた。それは、室町時代の日本全国六十八州のうち六分の一にあたり、山名氏は「六分一殿」とか「六分一家衆」と呼ばれる大勢力になった。
しかし、「満つれば欠くる」のたとえもある如く、一族が分立したことは内訌の要因になった。さらに、三代将軍足利義満は強大化した山名氏の存在を危惧するようになり、ついにはその勢力削減を考えるようになった。そのような状況下の康応元年(1389)、惣領の時義が四十四歳の壮年で死去した。時義のあとは嫡男の時熙が継いだが、将軍義満は時熙・氏之(幸)兄弟に我意の振るまいがありとして、一族の氏清と満幸に討伐を命じた。義満が山名氏の勢力削減を狙った策謀であることは明白だったが、氏清は「一家の者を退治することは当家滅亡の基であるが、上意故随わざるを得ぬ。しかしいずれ二人が嘆願しても許されることはないか」と確認したうえで出陣した。
追放された時熙・氏之に代わって、但馬守護職には氏清が、伯耆・隠岐守護職には満幸が任じられた。これで山名氏の内訌は一段落したものと思われたが、なおも山名氏の分裂を策する将軍義満は、許しを乞うた時熙・氏之らを赦免、氏清・満幸らを挑発した。義満の不義に怒った氏清は満幸・義理らを誘い、南朝方に通じて大義名分を得ると、明徳二年の暮に京へと進撃した。明徳の乱であり、この乱により氏清は戦死、満幸は敗走、義理は出家という結果になった。
乱後、幕軍として戦った、時熙に但馬国、氏幸に伯耆国、氏冬に因幡国の守護職がそれぞれ安堵された。こうして、さしもの隆盛を誇った山名氏も、将軍義満の巧みな謀略にのせられて大きく勢力を後退させたのである。とはいえ、但馬・伯耆・因幡は山名氏の勢力が浸透していた地域であったことは、山名氏にとっては不幸中の幸いであった。
* 山城国守護職を数えず、十一ヶ国とするものもある。
山名氏の再起
山名氏が大きく勢力を後退させたのち、にわかに勢力を伸張したのは大内義弘であった。義弘は明徳の乱に氏清勢を撃退する抜群の功を挙げ、和泉・紀伊両国の守護職に任じられ、一躍六ヶ国の守護職を兼帯した。さらに領内の博多と堺の両港による貿易で富を築くと、その勢力を背景として南北朝合一の根回しを行い、その実現によって得意絶頂を迎えた。
有力守護大名の弱体化を策する義満は、大内義弘の存在を目障りに思うようになり、両者の関には次第に緊張がみなぎるようになった。ついに義満打倒を決した義弘は、鎌倉公方足利満兼、美濃の土岐氏、近江の京極氏らと結び、これに旧南朝方諸将も加担した。さらに、山名氏清の子宮田時清が丹波で呼応した。かくして、応永六年(1399)、堺に拠った義弘は義満打倒の兵を挙げたのである。
乱は幕府軍の勝利に帰し、義満を頂点に戴く幕府体制が確立された。応永の乱に際して、但馬兵を率いた時熙は丹波に出兵して宮田時清を撃退。さらに堺の合戦において被官の大田垣式部入道が目覚ましい活躍をみせ、時熙は備後守護を与えられた。
ところで、さきの明徳の乱において、但馬国衆は山名氏清方と山名時熈方に相分かれて戦った。有力国衆の多くは氏清方に味方し、土屋氏、長氏、奈佐氏らが勢力を失った。なかでも土屋氏は一族五十三人が討死するという惨澹な有様で、山名氏は多大な人的損害を被った。時熈は山名氏を掌握したものの、家臣団の人材不足は深刻であった。そのようななかで、頭角をあらわしたのが垣屋氏と太田垣氏で、垣屋氏は土屋氏の庶流、太田垣氏は日下部一族の末流で、山名氏家臣団には大きな逆転現象が起こったのである。
垣屋氏は山名氏の上洛に従って西上した土屋一族で、時熙に味方した垣屋弾正は、乱戦のなかであやうく命を落としかけた時熙を助けて壮烈な討死を遂げた。弾正は明徳の乱を引き起こした張本は時熙であり、世間の目も時熙に辛辣である。ここは誰かが勇戦して討死、山名氏の名誉回復を図るべしとして、死装束をして合戦に臨んだと伝えられる。果たして、弾正の壮烈な討死によって、時熙はおおいに名誉を回復することができたのである。この弾正の功によって垣屋氏は、没落した土屋氏に代わって一躍山名氏家中に重きをなすようになった。
一方、応永の乱で活躍した太田垣氏は、乱後、但馬守護代に抜擢された。その後、時熙が備後守護に補任されると大田垣氏が守護代に任じられ、但馬守護代には垣屋氏が任じられた。こうして、垣屋氏・大田垣氏は山名氏の双璧に台頭、のちに八木氏、田結庄氏を加えて山名四天王と称されることになる。
その後、時熙は幕府内における地位を確立するとともに、但馬・因幡・伯耆に加えて、備前・石見・安芸守護職を山名氏一族で有するに至った。時熙は義満、義持に歴仕して、山名氏の勢力を回復していったのである。正長元年(1428)、義持が病死したとき、すでに嫡男の義量は夭逝していたため、つぎの将軍を籤引きで選ぶことになった。この件にもっとも深く関与したのは三宝院満済と管領畠山満家、そして山名時熙であった。

|

| | 山名氏の菩提寺-円通寺 | 円通寺にある時義(左)と時熙の墓
|
宗全の登場、応仁の乱の勃発
時熙のあとは二男の持豊が家督を継承して、但馬・安芸・備後・伊賀の守護職を与えられた。時熙には嫡男持熙があり、はじめ後継者に立てられいた。しかし、将軍義教の勘気にふれて、持豊が家督に立てられたのである。永享七年(1435)、時熙が死去すると、持豊が山名一族の惣領となったが、備後において兄持熙が反乱の兵をあげた。ただちに軍を起した持豊は備後に進攻すると、たちまち持熙を国府城に討ち取った。
一族の反乱を平定した持豊は領国支配を固め、幕府の侍所頭人に任じられ、時熙につづいて幕府内で重きなした。そして、持豊が侍所頭人在任中の嘉吉元年(1441)、播磨守護赤松満祐が自邸に招いた将軍足利義教を暗殺するという一大事件が起った。
将軍権力の強化と幕府政治の引き締めを狙う足利義教は、恐怖政治を行った。多くの守護、公家、武家が粛正の波にさらされ没落、つぎは自分の番と思いつめた満祐が義教を殺害するという暴挙を行ったのであった。この前代未聞の事変に際して幕府は動揺をきたしたが、赤松討伐軍を編成すると播磨に向けて進攻させた。その主力となったのは侍所頭人の地位にあり、赤松氏の本国播磨の隣国にあたる但馬守護職でもある山名持豊であった。
播磨に兵を進めた持豊は赤松勢が拠る城山城を猛攻、観念した満祐は自害、赤松氏宗家は没落した。乱後、山名氏の功に対して幕府は、播磨・美作・備前の守護職を与えた。持豊はただちに垣屋越前守熙続を守護代に任じて播磨に派遣すると、赤松氏残党を掃討するとともに、領国支配を推進した。しかし、播磨は赤松氏発祥の地であり、東三郡は幕府に味方した赤松満政が分郡守護に任じられるなど、領国支配の前途は多難であった。
播磨一国の守護職を望む持豊は幕府に働きかけ、ついに東三郡の守護職にも任じられた。この処置に怒った満政が挙兵すると、ただちにこれを降し、満政を播磨から追い払った。その後も赤松氏一族の挙兵が繰り返されたが、そのことごとくが持豊によって征圧された。山名持豊の傲慢と勢力拡大を嫌った幕府の謀略で、享禄三年(1454)、持豊は討伐を受けて隠居、家督を嫡男教豊に譲った。このとき、持豊は出家して宗全と号し、備後守護職には是豊が補任された。長禄元年(1458)、赦免された宗全はふたたび幕府内で権力を振るうようになる。
 将軍足利義政は政治に倦み、男子にも恵まれなかったことから僧籍にあった弟の義視を還俗させて後継者に立てていた。ところが、正妻の日野富子が懐妊、やがて男子が生まれたことでにわかに後嗣問題は波乱含みとなった。これに、管領斯波氏、畠山氏の家督問題が絡み、時代は動乱前夜の様相を呈した。一方、赤松氏で唯一残っていた次郎法師丸が、遺臣らの神璽奪還の功により再興が許されたのである。赤松氏再興の背後には管領細川勝元がおり、将軍継嗣問題、管領家の家督騒動、そして赤松氏の再興とが相俟って宗全と細川勝元の対立は決定的となった。
将軍足利義政は政治に倦み、男子にも恵まれなかったことから僧籍にあった弟の義視を還俗させて後継者に立てていた。ところが、正妻の日野富子が懐妊、やがて男子が生まれたことでにわかに後嗣問題は波乱含みとなった。これに、管領斯波氏、畠山氏の家督問題が絡み、時代は動乱前夜の様相を呈した。一方、赤松氏で唯一残っていた次郎法師丸が、遺臣らの神璽奪還の功により再興が許されたのである。赤松氏再興の背後には管領細川勝元がおり、将軍継嗣問題、管領家の家督騒動、そして赤松氏の再興とが相俟って宗全と細川勝元の対立は決定的となった。
かくして、応仁元年(1467)、京都御霊社に陣取った勝元方の畠山政長を宗全方の畠山義就が攻撃したことで、応仁の乱の火ぶたが切られたのである。
・写真: 京都御霊社、鳥居右側の石灯籠の傍らに応仁の乱勃発の碑がある。
戦国乱世へ
宗全は西軍の総帥として細川勝元の率いる西軍と合戦を繰り返した。乱において、山名一族の大方は宗全に属したが、二男で備後守護の是豊は勝元方について宗全と対した。宗全には嫡男の教豊があり、幕府の横槍があったとはいえ家督も譲っていた。ところが、寛正元年(1460)宗全は教豊を放逐した。是豊は自分が山名氏の家督を接げると期待したが、ほどなく教豊が嫡男に復したことで野望はあっけなく潰えた。この家督をめぐる不満と、勝元の娘婿であったことなどが相俟って、是豊は勝元方につき石見・山城の守護職に補任されたのである。東軍にあって気を吐いたのは、播磨奪還を目指す赤松政則と山名是豊であった。さしもの権勢を誇った宗全であったが、山名氏一族の統制は鉄壁とはいえないものがあったのである。



|
|
・西陣の宗全館跡 ・東西両軍が激戦を展開した百々橋跡 ・南禅寺塔頭真乗院境内墓地にある宗全の墓
|
応仁二年、細川勝元は京に軍勢を集結した山名方の留守を突いて、丹波守護代内藤孫四郎、長九郎左衛門らを但馬に侵攻させた。これを迎え撃ったのは、京に出陣中の父や兄の留守を守っていた大田垣新兵衛であった。竹田城から出撃した新兵衛は、丹波の夜久野高原に布陣する細川勢に突入、内藤孫四郎、長九郎左衛門らを打ち取る勝利をえた。
一方、播磨の回復を狙う赤松氏では、一族の赤松下野守が播磨に下り、旧臣を糾合すると播磨はもとより美作・備前の両国も回復してしまった。これに対して山名方は、大田垣宗朝が但馬に帰り、夜久野合戦勝利の余勢をかって丹波へ侵攻、氷上郡の全域と多紀郡の大山荘あたりまでを制圧する勢いを示した。
やがて、播磨・美作・備前の三国守護職は政則に与えられ、山名氏の分国は嘉吉の乱以前の状態に戻ってしまった。その後、泥沼化する戦いに倦んだ宗全と勝元の間に和議の気運が盛り上がった。しかし、文明五年(1473)、宗全は和議の成立をまたずして、京の陣中において波乱の生涯を閉じた。ほどなく、細川勝元も病死したため、東西両軍は領袖を失うことになった。翌年、勝元の後継者政元と宗全の後継者政豊の間に和議が成立し、応仁の乱も終わりを迎えるかと思われた。しかし、東郡の赤松政則・畠山政長、西軍の畠山義就・大内政弘ら主戦派は和議に応じず、その後も慢性的に戦いが繰り返された。
文明九年、西軍の中心的存在であった畠山義就、大内政弘らが相継いで領国に撤収したことで、さしもの応仁の乱も終熄を迎えた。しかし、乱はすでに全国に拡散しており、世の中は下剋上が横行する戦国乱世へと推移していた。
赤松氏との抗争
文明十一年、赤松政則は播磨に下向すると播磨・備前・美作三国の支配に乗り出した。政則は山名氏の分国因幡の有力国衆毛利次郎を援助して、山名氏の後方攪乱をはかった。毛利次郎は因幡一国を席巻し、山名氏にとって看過できない勢力となった。
山名氏の後方攪乱をはかる政則は、山名氏の分国である因幡・伯耆の有力国衆を抱き込んで山名氏への反乱を起させた。因幡では私部城に拠る毛利次郎が赤松氏に通じ、他の国衆も次郎に加わって反乱は内乱の状況を呈した。因幡の状況を重くみた政豊は但馬に帰国すると、ただちに因幡に出撃し、守護山名豊氏とともに次郎を因幡から追放した。ところが翌年、伯耆国で南条下総入道らが政則に通じて伯耆守護山名政之から離反、一族の山名元之とその子小太郎を擁して兵を挙げた。政豊は政之を応援して出兵、反乱は文明十三年におよんだが、元之らを追放して内乱を鎮圧した。
赤松政則の策謀による因幡・伯耆の反乱に手を焼いた政豊は、政則の介入を斥け、播磨の奪還を目指して出兵の準備を進めた。一方、政豊の嫡男で備後守護の俊豊は、父に呼応して備前から播磨への進攻を狙った。俊豊は備前の有力国衆松田氏元成を味方に引き入れると、文明十五年、赤松氏の守護所福岡城を攻撃した。松田一族は一敗地にまみれたものの、俊豊は太田垣氏らの兵を率いて備前に進撃した。かくして、但馬の政豊は俊豊の動きに合わせて、播磨へ向けて出陣すると、国境の生野に布陣した。
ときに京にいた赤松政則は、ただちに播磨に下向したが、生野方面と福岡城方面との両面作戦を迫られた。重臣の浦上則宗は備前福岡の救援を説いたが、政則は生野方面を重視し、主力を率いて生野へと出陣した。両軍は真弓峠で激突、結果は山名方の大勝利で、敗走する赤松軍を追って播磨に雪崩れ込んだ。政則の敗報に接した福岡城救援軍も播磨に引き返したため、福岡城の守備兵は四散した。戦後、赤松政則は播磨を出奔、浦上氏ら重臣は政則を見限って赤松一族の有馬氏から家督を迎えた。ここに、山名氏は播磨・備前を支配下に置き、垣屋氏、太田垣氏らを代官に任じて播磨の支配に乗り出した。
政則が出奔したあとの赤松軍は浦上則宗が中心となり、備前方面で山名軍と泥沼の戦いを展開した。山名氏が備前方面に注力している隙を狙って、文明十七年(1485)、細川氏の支援を得た政則は播磨に帰国すると旧臣を糾合、垣屋一族が守る蔭木城を急襲した。不意を討たれた垣屋勢は 越前守豊遠 左衛門尉宗続父子、平右衛門尉孝知ら主立った一族が討死する大敗北を喫し、辛うじて城を脱出した田公肥後守が書写坂本城の政豊に急を報じた。蔭木城の陥落は、赤松政則の動きにまったく気付いていなかった政豊の油断であった。
父子の相剋
蔭木合戦ののち、赤松政則と浦上則宗との間に妥協が成立、一枚岩となった赤松軍は勢力を増大、それまでの守勢から攻勢に転じるようになった。そして、文明十八年正月、山名勢は英賀の合戦に敗北、垣屋遠続らが戦死した。さらに同年四月、坂本の戦いにも敗北した山名政豊は、書写坂本城を保持するばかりに追い詰められた。長享二年(1488)、坂本城下で激戦が行われ、敗れた山名方は結束を失っていった。
窮地に陥った政豊は但馬への帰還を願ったが、垣屋氏をはじめ但馬の国衆らはあくまで播磨での戦い継続を求めた。さらに嫡男の俊豊も撤収に反対したため、追い詰められた政豊は、ついに坂本城を脱出して但馬に奔った。かくして山名勢は総退却となり、赤松勢の追尾によって散々な敗走となった。
但馬に逃げ帰った政豊に対して、但馬国衆まもとより俊豊を擁する備後国衆らは背を向けた。なかでも
一連の敗北で、多くの犠牲を払った山名氏の有力被官で播磨守護代の垣屋氏と政豊の間には深刻な対立が生じた。
備後守護代であった大田垣氏や備後衆は俊豊を擁する動きをみせ、俊豊が政豊に代わって家督として振舞ったようだ。
ところが、明応の政変によって将軍足利義材が失脚、義材に従って河内に出陣していた俊豊は窮地に陥った。ただちに但馬に帰った俊豊であったが、与党であったはずの垣屋・太田垣氏らが政豊方に転じたため、但馬は俊豊の意のままにはならない所となった。
明応二年(1493)、俊豊は政豊の拠る九日市城を攻撃、どうにか俊豊の攻勢をしのいだ政豊は、
逆に俊豊方の塩冶・村上氏を打ち取る勝利をえた。以後、政豊と俊豊父子の間で抗争が繰り返された。
情勢は次第に政豊方の優勢へと動き、ついに山内氏の進言をいれた俊豊は備後に落去していった。
明応四年、政豊は九日市城から此隅山城に移り、翌年には俊豊を廃すると次男致豊に家督を譲り、
備後守護も譲ったことで山名氏の内訌は一応の終熄をみせた。
しかし、この政豊と俊豊父子の内訌は、確実に山名氏の勢力失墜を招く結果となった。乱において
政豊・俊豊らは、垣屋氏・大田垣氏ら被官衆への反銭知行権の恩給を濫発、みずから守護権力を無実化し、
結果として垣屋氏・大田垣氏らの台頭が促したのである。とくに垣屋続成は俊豊と対立、政豊・致豊の重臣として
領国の経営を担うようになった。
衰退する山名氏
垣屋続成の台頭は致豊との対立を誘発、やがて両者は対立関係となった。永正元年(1505)、垣屋続成に此隅山を攻められたが、和議が成立して最悪の事態は回避されたものの山名氏の衰退は決定的であった。さきの政豊と俊豊父子の内訌、有力家臣の自立によって、山名氏は戦国大名への道を閉ざされたといえよう。永正九年、致豊は弟の誠豊に家督を譲ったが、これは垣屋・太田垣氏らの策謀によるもので、致豊にとっては不本意な引退であった。
家督となった誠豊は、権力基盤を強固にするため、因幡山名氏の内政に介入した。そして、守護山名豊重排除を策し、豊重の弟豊頼を援助して豊重を布施天神城に討ち取った。誠豊を後楯として因幡山名氏の家督となった豊頼であったが、豊重の子豊治の攻勢を受け、永正十二年(1515)には豊治が因幡守護となっている。豊治は妹を将軍義材の側室に送り込むなど、守護権力の強化を図り誠豊と対立した。両者の抗争は繰り返され、誠豊は豊頼の子誠通を応援して豊治と対抗させた。
大永二年(1522)、守護赤松氏と重臣浦上氏の擾乱で揺れる播磨に侵攻した。ところが、政村と村宗が和睦して山名勢に対したため、敗れた誠豊は翌年に播磨から撤退せざるをえなかった。この播磨出兵の失敗は、誠豊の権力後退につながり、垣屋氏をはじめ太田垣・八木・田結庄氏らの台頭が促された。一方で因幡において誠豊と対立していた豊治がにわかに急死したことで、誠通が因幡守護に収まった。なんとか因但を支配下においたかに見えた誠豊であったが、大永八年(享禄元年=1528)、死去した。誠豊のあとは、致豊の長男祐豊が継ぎ、但馬守護に任じた。
祐豊は此隅山城を本拠にすると因幡進出を企図した。祐豊にしてみれば誠豊が擁立した誠通は、父致豊を引退に追い込んだ誠豊派であり排除されるべき存在であった。後楯を失った誠通は、祐豊に対抗するため出雲の尼子晴久と結ぶと、名を久通と改めた。因幡国衆もまた誠豊の死によって但馬からの自立を願い、これを糾合した久通が天神山城で兵をあげたのであった。以後、但馬山名氏と因幡山名氏の間で戦いが繰り返され、天文十五年(1546)、久通は多治見峠において討死した。
久通を討ち取ったのち、祐豊は因幡の残敵勢力の掃討戦を行った。そして、弟豊定を因幡に派遣、豊定は天神山城に入ると因幡の支配にあたった。その後、豊定の子豊数は武田氏の攻撃を受けて敗北、天神山城から退転、中務太夫豊国が因幡守護となった。
乱世の終焉
祐豊の代になると垣屋氏をはじめ太田垣・八木氏らが自立し、領内の統制は十分に行われなかった。さらに、西方から尼子氏、ついで毛利氏の勢力が但馬に勢力をおよぼした。因幡では混乱のなかで勢力を拡大した鳥取城主武田高信が毛利氏と結び、山名氏に対抗する存在となった。永禄六年(1563)、兵を挙げあ高信は山名氏の拠る天神山城を攻略した。祐豊は毛利氏と対立する尼子氏を支援したが、永禄九年、出雲月山富田城を落とされた尼子氏は没落してしまった。毛利氏の勢力は、美作を本拠とする草刈氏にもおよび、草刈氏は因幡への領地拡大に動き出した。祐豊は尼子氏再興を目指す山中鹿之助ら尼子党を支援、毛利氏を後ろ盾とする武田氏ら国人衆と対立を続けた。
永禄十二年、毛利氏からの要請を入れた織田信長が羽柴秀吉を但馬に派遣 此隅山城は落ちて祐豊は討死したとの噂が流れた。しかし、実際は堺に没落していた。ほどなく信長に通じた祐豊は但馬に復帰、新たに有子山城を築いて本城とした。ところが、家臣団は毛利方と織田方に分裂、毛利氏の攻勢が激しくなると山名豊国の仲介で毛利氏と和睦をするなど、但馬山名氏は迷走した。かくして、天正八年、羽柴秀吉の攻撃を受けて有子山城は落ち、子の氏政は逃亡、城に残った祐豊は落城の五日後に病没して山名氏の本家は断絶した。
 但馬山名氏が没落したのち、羽柴秀吉が播磨から因幡に乱入、鳥取城をはじめ諸城がたちまち秀吉軍の前に陥落した。以後、毛利氏と織田氏の全面戦争となり、山名豊国は鳥取城に拠って羽柴軍を迎え撃った。しかし、降伏に傾いた豊国は中村春続・森下道誉らの抗戦派の家臣に追放され、秀吉に降り、信長からの助命を受けた。豊国が去ったのちの鳥取城は 、毛利氏から入った吉川経家を大将として羽柴軍に抗戦した。そして、天正九年、世に名高い「鳥取城の干殺し」で知られる攻防戦の結果、鳥取城は陥落した。ここに、山名氏が拠った城はことごとく潰え、山名氏の戦国時代は終わったといよう。
但馬山名氏が没落したのち、羽柴秀吉が播磨から因幡に乱入、鳥取城をはじめ諸城がたちまち秀吉軍の前に陥落した。以後、毛利氏と織田氏の全面戦争となり、山名豊国は鳥取城に拠って羽柴軍を迎え撃った。しかし、降伏に傾いた豊国は中村春続・森下道誉らの抗戦派の家臣に追放され、秀吉に降り、信長からの助命を受けた。豊国が去ったのちの鳥取城は 、毛利氏から入った吉川経家を大将として羽柴軍に抗戦した。そして、天正九年、世に名高い「鳥取城の干殺し」で知られる攻防戦の結果、鳥取城は陥落した。ここに、山名氏が拠った城はことごとく潰え、山名氏の戦国時代は終わったといよう。
生き長らえた豊国は、禅高と号して秀吉の御伽衆の一人になった。秀吉の没後は徳川家康に属し、慶長五年(1600)の関ヶ原の合戦に家康方として出陣、翌年に但馬国内に六千七百石の知行を与えられた。豊国が家康に遇されたのは、山名氏の先祖が、徳川氏が唱える先祖に近い存在であることを家康が利用したためだともいわれている。いずれにしろ、豊国の子孫は、江戸時代を通じて高家の一として続き、明治維新を迎えた。
・図:近世山名氏が用いた「糸輪に二つ引両」紋。

|

|
但馬守護山名氏の本拠として機能した此隅山城
| 山名氏が最期に拠った有子山城
|
→ 此隅山城址に登る
→ 有子山址に登る
●但馬山名氏
●伯耆山名氏
●因幡山名氏
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
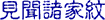

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
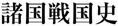
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
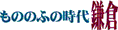

|
2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。
|
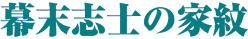
 これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
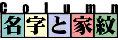

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

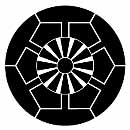
|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
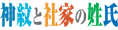

|
|

