

|
大崎氏★
●二つ引両
●清和源氏足利氏族
|
大崎氏の家紋としては、名生城址から発掘された軒丸瓦には、「立ち沢瀉」の紋が据えられている。また、軍旗には「木瓜」が据えられている。ここでは、清和源氏足利氏流の定紋を掲載した。
|
|
大崎氏は清和源氏足利氏の一門で、斯波氏の分かれである。斯波氏を名乗るようになったのは、足利泰氏の長子家氏が陸奥国斯波郡を領有したことに由来している。ちなみに、斯波郡は足利家兼が源頼朝の奥州征伐に従軍し、戦後に論功行賞として賜った土地である。斯波高経のときに鎌倉幕府が滅亡し、南北朝の内乱に際して高経は足利尊氏のもとで活躍した。
南北朝の争乱
建武年間のはじめ(1334頃)、陸奥守に補任された北畠顕家は義良親王(のちの後村上天皇)を擁して多賀城に拠り、鎌倉幕府の職制をそのまま取り入れた独立した政庁を創設した。これに際して、葛西・伊達・南部氏らの豪族が南朝方として忠誠を誓ったことで、奥州は南朝の勢力が強大化した。
建武二年(1335)「中先代の乱」をきっかけとして後醍醐天皇に叛旗を翻した尊氏は、高経の嫡男家長を奥州総大将(探題)に任じて奥州に下して勢力の確保に努めようとした。家長は斯波郡に下向して高水寺城に入り、北畠顕家と対峙した。
建武二年の暮れ、北畠顕家は足利尊氏追討のために多賀国府を進発し、鎌倉に向った。このとき、家長は顕家の西上を阻止せんとして相馬氏らとともに北畠軍と高野郡、行方郡で戦いとなったが阻止できず家長は顕家を追撃して鎌倉に入った。
上洛した顕家軍は尊氏軍と戦ってこれを破り、尊氏は九州に逃れ去った。顕家が奥州に帰って間もなく、九州で勢力を回復した尊氏は京都に攻め上るとたちまちのうちに制圧した。後醍醐天皇は顕家にふたたび上洛を命じ、これに応えて顕家は上洛の軍を起こした。家長は顕家軍を阻止せんと鎌倉で迎え撃ったが、敗れて戦死してしまった。家長を討ち取って西上した顕家も、和泉石津の戦いで敗れて戦死した。
顕家のあとは弟の顕信が継いで、奥州南朝勢の中心となった。一方、斯波家長が戦死したあと、奥州北朝方の中心として奥州入りしたのは石塔義房であった。興国三年(1342)義房は顕信軍と戦い、顕信を北奥に奔らせる勝利をえている。しかし、南朝方の力はいまだ隠然たるものがあり、貞和二年(1346)、幕府は吉良貞家、畠山高国の両管領を下向させた。以後、吉良・畠山の両氏は石塔氏を援け、三者協力して奥州における足利政権の基盤の確立につとめた。
奥州管領、斯波氏
ところが、中央では足利尊氏と直義の兄弟が不和になり「観応の擾乱」が勃発した。この乱は奥州にも波及し、吉良・畠山の両探題が対立、やがて合戦へと発展していった。観応二年(1351)に「岩切城の合戦」が起こり、両者は総力をあげてぶつかり、激戦の結果、岩切城を本拠とした畠山氏が敗れて吉良氏の大勝となった。この騒ぎのなかで北畠顕信が勢力を盛りかえし、多賀国府を奪回したが、吉良方の攻撃によって敗れた顕信は出羽に逃走した。
それから二年後の文和二年(1353)、一時奥州管領の代表格となっていた吉良貞家が死亡した。貞家が死ぬと、幕府は奥州の支配を強化するため斯波家兼を新たに奥州管領として赴任させた。ところが貞家の死後、先に吉良氏に敗れて会津に逃れていた畠山氏の遺児国詮が管領を主張して活動をはじめ、奥州総大将だった石塔義房の子義憲が鎌倉から奥州に入った。そして、吉良貞家のあとを継いだ吉良満家も管領を主張し、これに斯波氏を入れて四探題(管領)が並び立つという状況となった。そして、南北朝時代後半の奥州は、この四管領の勢力争いが展開され最終的勝利者となったのが斯波氏であった。
ところで、家兼が奥州へ下向したのは延元二年(1337)とするものがあるが、これは家長の下向を誤解したものであろう。また、『余目旧記』では貞和二年(1346)のこととなっている。家兼は暦応元年(1338)まで若狭守護に就任するとともに、兄高経の代官として越前や若狭で活躍した。「観応の擾乱」で兄高経を袂を分かって以降、一貫して尊氏党に属して幕府の引付頭人に抜擢されて幕政を担当した。その後ふたたび若狭守護に就任し、文和三年(1354)に陸奥に転任して、のちの大崎氏の祖となったのである。
家兼は斯波家長の叔父にあたり、若狭から陸奥に転じたとき、長子直持、次男兼頼も父とともに陸奥に移住した。家兼は二年足らずで死去したため、嫡子直持が家督をついで奥州管領となり、次男兼頼は羽州探題として出羽に入り、羽州南朝方の中心勢力であった寒河江大江氏を下すとそのまま羽州に土着して最上氏の祖となった。
大崎氏の勢力拡張
大崎氏が入部した地は「河内」と呼ばれていて、頼朝の奥州征伐に功のあった渋谷・大掾・泉田・四方田の四人の鎌倉武士が領していた。そして、かれらは「河内四頭」と呼ばれていた。そこへ大崎氏が入部して勢力を伸ばしたことで、「河内」地方は大崎と総称されるようになった。ちなみに、四頭のうちの渋谷氏は大崎四家老の一人として大崎氏滅亡まで続いた。
家兼のあとを継いだ直持は師山城に拠り、志田・加美方面に領主権を拡大し、その領内に奥州統治機構を設け、直持のあとは詮持が継承した。この直持、詮持の代に前奥州管領家であった石塔・吉良・畠山らの僭称を払拭し、管領職を世襲し奥羽の監督官として君臨した。しかし、明徳三年(1392)奥羽両国が鎌倉府の関東公方足利満兼の直轄支配下に置かれるようになると、大崎氏の奥州管領権は大きく制約を受けることになった。
応永六年(1399)春、満兼は弟の満貞と満直を奥州の固めとして、それぞれ稲村・篠川に下向させたことから、大崎氏の立場は微妙なものとなった。一方、稲村に下った満直は伊達氏と白河氏に対して援助を求め、所領の分与を要求した。伊達氏は「ながいはうぢゃうの三十三郷」白河氏は「宇多庄」をそれぞれ進上する旨を申し入れたが、満兼は「庄などは心得がたし、郡を進上」と過大な要求を強いた。そのため、伊達氏は大崎氏などを誘って鎌倉府に背いた。
当時、大崎詮持は鎌倉にあり、ただちに帰国の途についたが鎌倉軍の追撃を受けて仙道大越で自殺し、かろうじて孫の満持だけが大崎に帰ることができた。その後、満詮は満兼の弟満貞と満直を討とうとして失敗、自殺して果てた。残された満持は、伊達氏の援助を受けたことから、伊達氏に名取郡を割譲している。
応永六年、畿内では大内義弘が将軍足利義満に反抗して泉州堺で兵を挙げた。この義弘の行動に鎌倉公方満兼も応じようとしたため、幕府は奥州の諸氏に鎌倉府を牽制させた。大崎氏や伊達氏もまた鎌倉府と対抗するため、直接、京都の将軍に接近し、将軍や幕府も大崎氏、伊達氏を保護する立場を示した。そして、応永七年(1400)大崎氏は将軍から新たに奥州探題職を与えられ、東北地方における支配権を得たのである。
かくして、大崎氏は代々左京大夫に任ぜられ、探題職として行政・軍事にわたる強力な権限を行使して、大崎・名生・小野・新田・中新田などを根拠地として大崎五郡に勢力を拡大していった。斯波に代わって大崎を名乗るようになったのも、この頃からであった。
奥州探題、大崎氏
ここに大崎氏は半世紀をかけて、対立する四探題を制して最後の勝利者となり、大崎氏による一国一円単独の探題制度が確立したのである。大崎氏が領したのは、黒川郡三十三郷、志田郡四十四郷、加美郡十八郷、遠田郡六十六郷、栗原郡、羽州最上郡四十八郷で、あわせて三十五万石であったと「古文書」に記されている。堂々たる大大名であった。そして、大崎氏の居城は師山城、中新田城など諸説あるが、府城と定められた名生城以外は確証がない。おそらく名生城が探題府であったろう。
奥州探題という職は、管領職を行使して奥州武士たちに将軍御教書の施行、所領の安堵・宛行などを行った。その結果、近隣の国人領主や土豪層など在地領主を掌握することができ、大崎氏は代々探題職を受け継ぎながら、大崎・名生を本拠に強大化していったのである。
こうして室町時代における奥州の政治の中心は大崎地方におかれることになり、大崎氏は奥州諸武士の頂点に立ち「朔の上様」と尊称された。『余目氏旧記』によれば、大崎氏の名生館に参候する大名・国人は奥州全域に及び、伊達氏・葛西氏、あるいは葦名氏といったような、のちに大崎氏に対抗する戦国大名の家々は、みな大崎氏に参候していたのである。しかも、その席順も伊達・葛西・南部・留守・白河・葦名・岩城といったようにきちんと定められていたことが記されている。
そして、室町将軍の命令は大崎氏を通じて伝達され、幕府の賦課になる造内裏役の段銭なども大崎氏を通じて徴集された。また、国人らの申し分も大崎氏を通じて将軍に達せられ、官途の推挙も大崎氏が行った。以後、斯波大崎氏は奥州に公権を執行する最高機関である探題職を長く世襲し、幕府も大崎氏を奥州探題と呼んだ。そして、京都公方の分身として公方と称され、所領の大崎五郡を領国化し、奥州の雄として戦国時代に至るまでその勢力を維持していくことになる。
時代の変革
大崎氏は奥州探題として頂点にあったが、その一方で南北朝の動乱を生き抜いた国人たちは、さらに勢力を広げるために、違いに合従連衡し虚々実々の駆け引きを展開するようになった。そして、国人一揆とよばれる同盟関係が共通の事象として日本列島の各地において見られるようになった。
『余目氏旧記』には、留守家高のころ、澁谷・大掾.泉田・四方田の河内四頭に留守氏が加わった「五人一揆」のことが記されている。河内四頭の諸氏は鎌倉時代以来の家柄を誇り、南北朝の動乱期を生き抜いて大崎氏入部以後も、なお連合して反独立の地位を維持していのである。そして、葛西・山内・長江・登米氏ら北上川や迫川流域の諸家とも留守氏は一揆を結んでいた。さらに、余目持家は奥州の巨大勢力である伊達政宗と一揆関係にあったことが知られる。
このような地方国人らの一揆結合によって結ばれる婚姻関係、そこからもたらされる人的結合によって保障される国人らの独立性は容易に突き崩しがたものがあった。そして、それに対していかなる上級権力をもってしても、太刀打ちすることは難しく、かれらの自立性を認め、かららの存在と折り合う形でしか権力を維持することはできなかった。
幕府から奥州探題として認められた大崎氏にしても、その例外ではなかった。いかに、大崎氏が権勢を誇ってもそれは外交・儀礼的な表面だけに過ぎない存在となっていき、実力をともなう現実政治としては、大名・国人らの発言力を無視することはできず、かれらもまた大崎氏の口出しを許さないという力関係が背景にあったのである。
また、大崎氏の一門一家には、志田郡の古川氏をはじめ、遠田郡の百々・涌谷氏、栗原郡の高泉氏、黒川郡の黒川氏などがあって重きをなし、里見紀伊・仁木遠・中目兵庫・渋谷備前が四家老と呼ばれていた。さらに侍大将として氏家・柳目・伊場野・谷地森・宮崎・新田・小野田の諸氏が知られる。これらの一族・被官・豪族たちも大崎氏に服属しているものの、いずれも独立した領主であり、勢力関係が変化したり、利害が相反する場合は離反すること多かった。大崎氏は権威こそ保ったが、大名・国人からの圧迫、一族の自立、配下の豪族らの離反に悩まされるのである。
戦国時代への序奏
 六代持詮の代の永享四年(1432)、南部氏と下国安東氏との戦いがあり、両者の和睦を命じる室町将軍の命令が再三にわたって届けられたが、南部氏はそれを承引せず、ついには安東氏は没落の運命となっている。ついで、同七年には、和賀・煤孫の同族争いから、稗貫・江刺・薄衣・斯波・南部、さらに公方大崎氏の軍勢が出動する大乱となった。
六代持詮の代の永享四年(1432)、南部氏と下国安東氏との戦いがあり、両者の和睦を命じる室町将軍の命令が再三にわたって届けられたが、南部氏はそれを承引せず、ついには安東氏は没落の運命となっている。ついで、同七年には、和賀・煤孫の同族争いから、稗貫・江刺・薄衣・斯波・南部、さらに公方大崎氏の軍勢が出動する大乱となった。
七代教兼の時代の康正三年(1457)、「蠣崎蔵人の乱」が起り、蠣崎氏を討った八戸南部氏の一族・家臣に対して二十通に及ぶ官途推挙状を発行しているが、それらの推挙状には宛名がない。このことは、大崎公方が南部氏の家中に立ち入ることができず、推挙すべき人名を特定できなかったことを示している。その一方で、「享徳の乱」に際して、将軍足利義政より古河公方成氏の追討令と督戦の命を受け、寛正六年(1465)将軍の乗馬や漆の上納の命を諸氏に伝達するなどの活動が知られる。また、教兼の代の応仁元年(1467)京都において「応仁の乱」が勃発した。
このころになると南奥の伊達氏の勢力が伸び、大崎氏のもつ奥州探題の権威を実力でしのぐようになった。伊達氏は奥州諸氏の家督争いに後楯になるなどしたことから、探題の指揮権から脱して伊達氏に従う武士も現れてきた。さらに、「享徳の乱」「応仁の乱」などによって、時代は確実に戦国の様相を濃くし、社会には下剋上の風潮が激しくなってきた。奥州も例外ではなく、大崎氏の探題としての権威や機能も次第に失われつつあった。
応仁二年、北上川流域の登米・本吉・栗原・胆沢地方において、一大争乱が発生した。また、重臣氏家氏の反乱により教兼は居城を追われ、江刺・薄衣氏らに救援を依頼した。これに、葛西惣領・柏山・大原・本吉・寺崎氏らが介入して、大崎・葛西領内にまたがる争乱となった。文明元年(1469)には、大崎教兼みずから甲冑を着けて登米郡佐沼方面に出陣する事態となった。それに呼応して江刺・糠部・斯波・稗貫・遠野・和賀の諸勢が胆沢郡柏山に出動した。伊達氏も派兵を求められ、薄衣美濃入道が書状を送った。この書状が有名な「薄衣状」で、一説には義兼の代の明応七〜八年(1498〜99)のこととされるが、最近では文明元年のことに訂正されている。
・右:中世奥州勢力図
伊達氏の台頭
このように、北上川流域の争乱に対して、大崎氏は家中の反乱の鎮圧はもとより、葛西・柏山らの諸氏を従わせるだけの力を失い、江刺・薄衣氏に援助を求め、さらには伊達氏にまで派兵を求める依頼状を送らなければならない有様となっていた。
教兼の後を継いだ政兼は早世し、九代を嗣いだのが義兼である。この頃になると戦国の争乱は奥州にも波及し、長享二年(1488)、佐沼城主らの有力家臣が義兼に背き、大崎氏はふたたび「家中大乱」となった。この領内の反乱を義兼は鎮圧できず、伊達成宗に援助を求めた。成宗は大崎地方進出の好機として、金沢氏に三百騎をつけて大崎領に派遣し義兼を救った。葛西一族の薄衣氏も大崎に兵を出して佐沼城を攻めたことで、ようやく内訌は鎮圧された。
義兼の跡を継いだ高兼は早世。大崎氏は戦国乱世という困難な時代において、政兼─義兼─高兼の三代のうち二代が早世したことで、探題としての権勢を大いに傾かせざるをえなかった。一方、大崎氏の内訌に援助の手を差し伸べた伊達氏は着実に勢力を拡大し、伊達稙宗は大永五年(1525)陸奥国守護職に任じられ左京大夫に任官した。
奥州は鎌倉時代以来、守護職は置かれなかった。室町時代に奥州探題が置かれ、大崎氏がこれに任じられ左京大夫にも任官した。そして、大崎氏はその権威によって勢力を伸ばしたが、伊達氏が守護職に任ぜられたことで、探題職の権威は完全に失墜し、伊達氏と大崎氏の勢力関係は名実ともに逆転した。これによって、大崎氏は一地方大名と化してしまったのである。
相次ぐ家中の内乱
天文三年(1534)、志田郡泉沢領主の新田安芸頼遠が中新田・高木・黒沢らの諸氏を誘って反乱を起こした。これが、「大崎氏天文の内訌」の始まりとなった。このように大崎氏は一族・領内の豪族らを強力な領袖権をもって統制できなかったため、家中の離反が相次いだ。いいかえれば、一族・豪族の共同体という旧い体質のまま戦国時代を迎え、ついに大名領主制を確立できなかった。それが、大崎氏が近世大名に生き残ることができなかった最大の要因であった。
さて、義直は頼遠討伐に出陣したが、大崎氏一族である古川・高泉・一迫らの諸氏をはじめ、重臣の氏家氏も頼遠に味方したことで、大崎家中を二分する一大争乱となった。翌年、義直は泉沢城を攻撃したが、反義直方の氏家党が頼遠を支援した。この間、義直方の氏家太郎左衛門が岩出沢城を乗っ取り、義直方は優勢となったことで、頼遠は古川城に逃れ、古川城が反義直方の拠点となった。その後、岩出沢城が落され、高泉直堅が義直方の諸城に火を放って古川氏を援けた。
このように、大崎家中における反義直勢力は次第に勢力を増してきたため、義直の力だけでは反乱鎮圧が困難になってきた。ついに、義直は伊達稙宗に援助を求めた。稙宗は伊達氏の勢力を大崎に伸ばす好機としてこれを承諾し、みずから三千余騎の伊達勢を率いて志田郡に入った。義直が伊達氏のもとに支援を求めるために領地を留守にした間に、反義直勢は義直方の諸城を攻撃するなど活発な動きを示していた。
大崎領内に入った稙宗は師山城に入り、反義直勢力の拠点である古川城攻略を開始した。このとき、義直に従う勢は渋谷党、笠原一族ら五百騎に過ぎず、他はすべて義直に抵抗する古川氏に味方していた。稙宗は一千騎を率いて南門に陣し、伊達氏の宿老牧野宗興・浜田宗景らがそれぞれ一千騎を率いて西門・北門に向かった。これに、黒川景氏・留守景宗・懸田俊宗・長江宗武・国分宗綱らが従った。こうして、古川城をめぐる攻防戦が行われ、大勢は二日間で決した。敗れた古川氏は、燃え落ちる古川城とともに滅亡した。
ついで、稙宗は義直とともに反乱軍の最後の拠点である岩出山城を攻撃した。しかし、反乱軍も岩出山城を死守して長期戦となったが、ついに城方は降伏、首魁の新田安芸は出羽に落ちていった。ここに、数年におよぶ「大崎の乱」は収まった。
伊達氏天文の大乱
乱後、稙宗はその軍事力を背景として、大崎高兼の女に次男小僧丸(のちの義宣)を配して大崎氏に入れた。そして、小僧丸を義直の養子として大崎氏の家督を譲らせたのである。ここに至り伊達氏とのこれまでの力関係はまったく逆転し、伊達氏の武力が大崎領にも誇示されることとなったのである。そして、大崎家中は義宣を中心とする親伊達派と義直を中心とする反伊達派に分裂して対立するようになる。親伊達派としては氏家氏が、反伊達派としては笠原党がその中心であった。
かくして天文十一年(1542)、伊達稙宗と嫡子の晴宗との間に争いが起り、伊達家中を二分する大乱となった。乱は、晴宗が稙宗を桑折西山城に幽閉したことに始まった。この乱は「天文の大乱」とよばれ、伊達家中はもとより周辺の諸大名・国人らを巻き込んで奥州を揺るがす一大争乱となった。稙宗に属したのは、相馬・田村・二階堂・葦名・畠山・最上氏ら稙宗の子女を迎えた大名らで、晴宗には伊達家中の重臣らが与した。
大崎氏も二分し、義宣は稙宗に属し、義直は晴宗支持を表明して相争った。義宣は、天文十二年に、国分・名取・柴田方面の稙宗派の大将として、松森・秋保・支倉などに出陣して活躍した。乱は稙宗方の勝利になるかと思われたが、晴宗方の優勢となり、ついに天文十七年、稙宗が隠退して晴宗に家督を譲ったことで終結した。その結果、大崎氏においても稙宗派の義宣の勢力が失墜した。義宣は義直らの圧力によって追いつめられ、葛西氏を頼って出奔したがその途中の桃生郡二俣において殺害された。かくして、義直がふたたび大崎氏の家督に返り咲いたである。
最後の大崎家当主となったのは義直の子義隆で、父義直と同様に家臣団の反抗や、葛西氏との抗争に明け暮れている。天正年間初期における葛西氏との領界上の競り合いは、おおむね大崎氏側が頽勢であった。一方で、親族の山形城主最上氏の援助や、伊達氏の攻撃目標が佐竹・蘆名の連合軍に向けられていたということもあって、領内では反伊達の気運が高まっていた。
伊達氏との対立
そのような天正十四年(1586)、大崎義隆の寵童であった新井田刑部と伊庭野惣八郎の争いが家臣を二分する戦いに発展した。新井田刑部らは大崎氏執事の氏家弾正および伊庭野惣八郎ら反対派を追討したうえで主君義隆に詰め腹を切らせようとし、伊達政宗に奉公を誓い援助を願った。政宗はこれを大崎氏攻略の好機として新井田らに援助を約した。ところが、新井田一党は政宗との約束に違反して、逆に義隆を擁して氏家弾正を盟主とする反対派を討つ行動に出た。事態の急転に進退が窮した氏家弾正は、片倉景綱を頼って政宗に援助を願い出た。これにより、伊達政宗は氏家党救援を名目として大崎領内への侵攻を決した。
伊達家が動員した兵数は、一万数千人というものであった。しかし、そのほとんどが刈田・柴田・名取・宮城郡などの豪族たちで、伊達家譜代の家臣団はあまり参加していなかった。伊達家にとって大崎出兵は本来の作戦行動ではなく、反伊達連合軍が活動する福島仙道方面や、葦名氏に対する会津作戦の陽動的な意味合いも含まれていた。そして、政宗は陣代として浜田伊豆、総大将は一族の留守政景と重臣の泉田安芸、軍奉行には小山田筑前を任じてそれぞれ兵を率いさせた。
当時、伊達氏と対立して大崎氏を応援する最上義光は反伊達連合軍と結んでおり、政宗が大崎に出陣すれば、義光が反伊達連合軍と共謀して留守の米沢城に対して兵を向けることは必至であった。それゆえに政宗は米沢城を動けなかったのである。さらにいえば、政宗自らが出陣しなくとも簡単にけりが付くものと考えていたようである。たしかに、伊達軍の装備はいずれも最新式のもので、兵の訓練もよく行き届き、大崎氏のそれとは比較にならなかった。大方の見方も伊達氏の一方的勝利に終わるものとみられていた。
伊達の大崎侵攻軍は志田郡千石城に集結して、全軍を先陣と後陣の二手に分け、先陣の大将は泉田安芸が当り、大崎方の拠点である中新田城攻撃に兵を進めた。後陣の大将は留守政景で、師山城の南に陣を布いて大崎方の出撃を待った。一方の大崎方は、中新田城を主城として、桑折城、師山城、そして下新田城に兵を入れて伊達軍の進撃を待ち受けていた。加えて大崎方では、桑折城と師山城に早くより武器弾薬・兵糧などを送り込み、備えを固めて一大要塞化していた。
桑折城主は、大崎四家老の一人渋谷氏であった。それに、黒川月舟斎(晴氏)が助勢として入っていた。黒川氏は大崎氏の一族であったが、早い時期から伊達氏の傘下にあった。加えて、月舟斎の娘は敵の総大将の一人である留守政景に嫁いでおり、政景とは婿舅の間柄であった。しかし、月舟斎は伊達氏と袂を分かって大崎方に転じてその一翼を担っていた。桑折城主渋谷氏は月舟の叔父であり、嗣子には大崎義隆の弟にあたる義康を迎えていたことなどの理由から大崎氏に転じたものと考えられる。
大崎合戦
伊達軍は、中新田城を目指して桑折城・師山城の線を越えたが、大崎方からの攻撃はなく、雪の残る大崎原野を怒濤のように進撃した。桑折城・師山城の大崎勢は伊達軍の先陣と後陣を分断する作戦をとっていたのであるが、伊達軍は「大崎勢は臆した」とみて中新田城への攻撃を開始した。さすがに、歴戦の伊達軍の攻撃はすさまじく、中新田城は三の丸・二の丸が落され本丸を残すのみとなった。
城将の南条下総守は、兵を叱咤してよく伊達軍の攻撃を防いだ。伊達軍の猛攻にさらされながらも、下総守にはひとつの確信があった。それは、間もなく大雪が来るということであった。大崎平野は雪の多い土地柄であり、雪が降れば籠城軍は俄然有利となる。伊達氏の侵攻に対して大崎方は、雪が降ることを計算して作戦を立てていたようでもある。そして、大雪はきた。突然の天候の変化と急激な気温の低下は籠城軍にとって俄然有利となり、大雪を遮るものもない伊達軍は攻城を断念し兵を引き上げようとした。
これがきっかけとなって、伊達軍と大崎軍との攻防は
逆転した。伊達軍の撤退が始まると、桑折城で満を持していた大崎勢に月舟斎の出撃命令が下され、伊達の先陣は散々にたたかれて軍奉行の小山田筑前をはじめ多くの兵が大崎原野を血に染めて戦死した。残った兵は命からがら新沼城に逃げ込むのが精一杯であった。一方、留守政景率いる後陣は大崎原野に取り残され、大崎方の攻撃にさらされるばかりとなっていた。政景は婿舅の関係を頼んで、月舟斎に千石城へ帰ることの許しを乞うた。その願いを月舟斎が入れたことで辛うじて留守勢は虎口を脱することができた。
まさに、合戦は大崎方の会心の勝利に終わった。この「大崎合戦」は伊達政宗の輝かしい戦歴における唯一の汚点とも言われる戦いで、大崎氏側は永年圧迫を受けていた伊達氏に一矢を報いた。しかし、この合戦における勝利も、大崎戦史の掉尾を飾るものに過ぎなかった。
伊達氏に服属する
大崎表の敗戦と伊達軍の新沼籠城を知った政宗は、ただちに援軍を送り、その一部は松山城に入った。しかし、強気に軍を進めて大崎方を刺激すれば、敵中で籠城している新沼城が危うくなり、また、新沼籠城勢が大崎勢の包囲を突破して松山城に逃れるには、大きな犠牲がでることは必定であった。また、大崎方面で伊達軍が敗れたことが、南奥の反伊達連合勢に伝われば、安達郡方面の情勢が険悪となり、最上方面も防備の手を抜けない状態にあった。大崎方面に、大規模な軍を派遣することも、政宗みずからが出陣することもできなかった。政宗にしてみれば、いかにして大崎における敗戦の傷を最小限に止めるかが急務となった。
このようなとき、大崎方から和議が申込まれたのである。大崎氏にしても伊達氏に勝利したとはいえ、それは伊達氏の正規軍ではなく、伊達氏のつぎの攻撃を退けるだけの力もなかった。大崎氏は新沼城の泉田安芸と長江月監斎を人質に出せば、伊達勢の引き揚げを認めると連絡した。この申し入れに泉田安芸と長江月監斎が人質となり、全員無事新沼城から出ることができた。その後、長江月監斎は許され、泉田安芸は最上に移された。そして、最上義光の妹で、政宗の母にあたる保春院の仲介によって伊達氏と大崎・黒川・最上三氏との間に和議が成立したのである。
しかし、和議が成立したとはいえ伊達氏と大崎・黒川両氏との間はしっくりといかなかった。義隆は氏家吉継を反逆者として切腹させようとし、身の危険を感じる吉継は政宗に援助を求めた。政宗は葦名氏との決戦を企図しており、大崎・黒川氏を完全に自己の勢力下に置くことで北方の憂いを断とうとした。
翌年、原田休拙斎を派遣して大崎地方の動静を探らせ、泉田安芸に大崎方面への出動を準備するように命じている。このような政宗の動きを知った最上義光は、伊達氏が大崎領を併呑すれば、最上領は東と南の両面から圧迫されることになり、保春院に依頼して大崎・伊達両氏の調停に努めこれに成功した。政宗の無言の圧力が大崎氏をして屈服させたともいえよう。
こうして大崎氏は伊達氏の軍門に降り、氏家吉継の件も落着した。こうして、北方の憂いを解消した政宗は天正十七年(1589)、摺上原で会津の葦名氏と戦い大勝して葦名氏を倒すと会津黒川城に入城し、ついで二階堂氏を攻略し南奥州を支配下におさめた。そして、いまだ勢力を保持している大崎氏を徹底的に武力討伐して、大崎地方を領有しようと決心した。
大崎氏の没落
政宗は大崎地方周辺の家臣に準備を命じ、大崎家中に調略の手を伸ばした。しかし、この計画は中央情勢の急迫により実行されるまでには至らなかった。
すなわち、同年、豊臣秀吉が小田原征伐の出陣命令を下したのである。秀吉は一挙に関東から東北地方を支配下におさめ、天下統一を完成させようと決意した。政宗が摺上原で葦名氏を討ち滅ぼしたことも、惣無事令違反として処罰の対象となっていた。政宗にしてみれば、大崎氏にかかずらっている場合ではなくなったのである。
翌天正十八年(1590)、豊臣秀吉による小田原征伐が開始されたが、大崎義直は領内不穏で参陣が叶わず、小田原城開城後の「奥州仕置」によって領地は没収、城地追放の憂き目となった。このとき、大崎氏同様に小田原参陣を果たせなかった葛西・和賀・稗貫らの諸氏も領地没収の処分を受けた。
大崎氏は中世以来栄えた名門であったが、戦国時代という乱世にあたって優れた当主を得られず、家中の反乱をついに克服することができなかった。さらに、伊達政宗に降ったことで、中央との直接外交の途も閉ざしてしまった。一方、伊達政宗は傘下となった周辺の大名・国人らの頭領的立場で行動したため、大崎氏らとしても政宗に遠慮して独自に小田原に参陣することをはばかったと想像される。いいかえれば、みずからの運命を政宗に委ねたところに没落の要因があったといえよう。
かくして、大崎・葛西・和賀・稗貫氏ら小田原に参陣しなかった大名らは没落の運命となった。そして、大崎・葛西領は木村吉清・清久父子に与えられた。木村吉清は明智光秀の旧臣で、それまでは五千石で秀吉の旗本だった。そのような人物が、にわかに三十万石という大封の大名になったため、浪人を雇用し身分の低い者を武士に取り立てたにわか仕立ての家臣団を従えて入部してきた。
大崎・葛西一揆
大崎・葛西領に入部した木村父子は、厳しい太閤検地を実施し、にわか仕立ての家臣も粗暴な振舞いが多かったため、反発した大崎・葛西氏の旧臣らが一揆を起こした。その背景には、秀吉に含むところのある伊達政宗の扇動があったともされている。戦記物語などによれば、大崎左衛門尉義隆以下の大崎一族が出陣したというが、前後のことから信憑性に欠けるようだ。所領を没収されたあとの義隆は、石田三成を頼って京都に上り大崎氏再興をはかっていたことが知られる。
大崎・葛西一揆は、蒲生氏郷と伊達政宗によって取りあえず鎮圧された。しかし、一揆扇動の嫌疑を受けた政宗は上洛を命じられ、裁判に臨んだ政宗は秀吉の嫌疑を解き、かえって大崎・葛西氏旧領へ移封の内示を受けた。翌年の春になると伊達政宗は一揆軍に対して徹底討伐の軍を起し、大崎領の宮崎城、葛西領の登米郡佐沼城が次々と攻略された。葛西・大崎一揆軍は最後の拠点である佐沼城に籠城したが、伊達軍の猛攻にさすがの堅城も落ち、城内の武士五百人、百姓ら二千余人が斬殺され、のちに「佐沼城のなで斬り」と呼ばれている。これは、伊達政宗が一揆扇動の証拠を消す意味もあって、かくのような皆殺しとなったとする説もある。こうして、葛西・大崎氏旧領は伊達氏に帰属するところとなったのである。
この大崎・葛西一揆によって大崎氏再興の芽はまったくなくなり、その後の義隆は豊臣秀吉から上杉景勝付を命ぜられ、慶長八年(1603)、会津で没したと伝わっている。義隆の子息たちは南部氏、最上氏などに仕えたことが系図からうかがわれるが、いずれも、大崎三十余万石を領したといわれる戦国大名大崎氏の裔としては、まことに寂しい姿であった。・2004年11月05日
【参考資料:古川市史/岩出山町史/宮城県史/戦国大名系譜人名事典 など】
●氏家氏
●笠原氏
●黒川氏
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
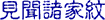

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
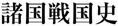
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
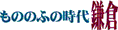

|
2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。
|
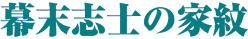
 これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
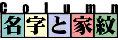

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

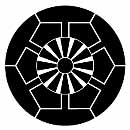
|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
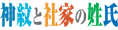

|
|

