
岩城氏
れんじに月
(桓武平氏繁盛流/維茂流?) |

|
岩城氏は桓武平氏繁盛流(維茂流ともいう)と伝えられている。『寛政重修諸家譜』所収の岩城氏系図によれば、常陸大掾平国香の子孫安忠を祖とし、その六代目にあたる隆行(成衡)が陸奥に下り、藤原清衡の女婿となり、妻との間に五人の子供をもうけた。長男が隆祐で楢葉郡に、次男隆衡(隆平)は岩城郡、三男隆久は岩崎郡、四男隆義は標葉郡、五男隆行は行方郡をそれぞれ与えられたと記されている。すなわち、隆行(成衡)の次男隆衡(隆平)が岩城氏の祖となり、平安後期には岩城郡に本拠を構えて、一族を分立させながら村落の開発を進め勢力を拡大してきたと伝えている。
文治五年(1189)の源頼朝の奥州征伐(奥州合戦)に、多くの武士が参加して戦後の論功行賞で奥州に新しい所領を得た。かつて平泉の藤原氏との関係を深めていた岩城氏、一族の岩崎氏らも鎌倉方として奥州合戦に参陣し、岩城郡・好島郡・岩崎郡などに地頭職を安堵された。
岩城氏の系譜を探る
岩城氏系図は諸本が伝わっているが、それぞれ異同が少なくない。そして、海道小太郎成衡なる人物を祖とする系図がいくつか伝わっている。たとえば『藩翰譜』の岩城氏系図、『姓氏家系大辞典』所載の仁科岩城氏系図などで、それらの系図にみえる成衡は忠衡の子と記されている。
各種岩城氏系図の初期に記された人物のなかで史料などから実在が確認できるのは忠清・清隆・師隆で、十二世紀末から十三世紀初頭を生きた人たちである。そして、前記系図における成衡はかれらと同時代の人物と位置付けられている。他方、海道小太郎成衡は『奥州後三年記』に乱の発端を作った人物として登場している。後三年の役は、十一世紀の争乱であり、『奥州後三年記』にみえる成衡は、岩城氏系図にみえる成衡とは時代が適わないようだ。
岩城氏の系図でもっとも信憑性の高いのは『国魂文書』の中の「岩城国魂系図」である。国魂系図は鎌倉時代に岩城氏一族の国魂氏が、一族富田氏との所領争論関係の文書として作成したものである。この国魂系図は、高久三郎忠衡を祖として、次に岩城二郎忠清─好島太郎清隆─新田太郎師隆─岩城太郎隆義として隆義の後家で終わっている。そして、岩城氏の祖とされる海道小太郎成衡なる人物はこの系図にはあらわれてこない。
とはいえ、高久三郎忠衡と海道小太郎成衡はともに「衡」の字を共有しており、真衡・清衡・家衡など清原一族およびそのあとを受けた奥州藤原氏の名乗りに見られる通字である。このことから、忠衡と成衡とは近い関係にあったか、あるいは同一人物であったのかも知れない。これらのことから、海道小太郎成衡を岩城氏の祖とするのは、そのままに受け取ることはできないが、まったく否定するわけにもいかないようだ。
岩城一族の勢力伸張
国魂系図は古文書に出てくる人名とも一致するところが多く、矛盾するところが少ないものである。この国魂系図から岩城氏の発展を追ってみると、二代、三代、四代と代を重ねるごとに一族が枝分かれし発展していった。そして、岩城郡内の中世の村の名を名字とする一族が多くあらわれてくる。
ちなみにいわき地方だけを挙げれば、好島・新田・富田・国魂・岩間などがあり、その他「飯野文書」のなかの元久元年(1204)の史料には、新田太郎、好島三郎、深沢三郎、千倉三郎、片寄三郎、大森三郎、戸(富)田三郎、田戸(富)次郎、大高三郎などの岩城一族と目される人々の名前が記されている。これらの名乗りはそれぞれが領した土地の名を名字としたものであり、岩城氏一族が開発領主として、惣領を中心として新しい村づくりを行っていたことを示している。
初代高久三郎の高久は滑津川河口部の地名であるが郡名でも郷名でもない、二代目にあたる岩城二郎、岩崎三郎、荒河四郎らは、岩崎が郡名、岩城と荒河は郷名であろうと推定されている。岩城と荒河の地名の特定は難しいが、高久はそのいずれかに含まれていた小さな地名であったようだ。
初代の名字がもっとも小さい地名なのは、おそらく支配領域を示すものではなく、その居館の所在地を示したものと思われる。すなわち、中世の岩城氏一族の人々は初代の高久三郎忠衡を特別な気持ちで尊敬し、それがかれらをして高久と呼ばせたのであろう。いいかえれば、高久三郎忠衡は、十二世紀の初めに常陸の本拠地から高久の地に移住し、そこに居館を構え、岩城郡衙と密接な関係を持ちながら土着し勢力を拡大していった人物であったと想像される。
南北朝期における動向
鎌倉時代の岩城氏の惣領は忠清の系であり、鎌倉時代後期には岩城二郎を名乗っていた。鎌倉幕府が滅亡し南北朝の内乱期を迎えるとはじめ南朝方についたが、のち北朝に転向した。岩城一族は次第に好島荘領所職の伊賀氏の支配を排除し、岩城惣領の隆泰は文和三年(1354)ころに伊賀盛光に代わって岩城郡の守護を努めていたとみられる。
十四世紀後半の岩城氏の惣領は周防守を称し、十五世紀の初めの応永十七年(1410)以後は、白土氏が岩城氏の惣領になっていく。すなわち、鎌倉時代には忠清─清隆─師隆─隆義と続き、隆義のあとはその後家が継ぎ、そのあとは師隆の次男の系統である岩城小次郎繁隆─乗祐─隆衡─(願真)─隆兼が継ぐことになる。
岩城小次郎隆衡は、鎌倉末期の確かな文書にその名が見え、岩城次郎願真は幕府の使節として活躍し、元弘の乱(1331)には、幕府軍の有力者として笠置山攻めに向ったことが知られている。そして、建武元年(1334)には、好島荘八幡宮造営注文に岩城次郎入道願真として現れるなど当時の文書からその存在が認められる岩城一族における有力人物であった。また、貞和二年(1346)の奥州管領奉行人連署奉書に「好島・白土・絹谷・大森・岩城・田富・比佐・富田」と書かれた地頭「岩城」氏は書かれた位置からいっても、東目村の地頭ではなく、八立村の地頭である次郎入道願真であると考えられる。
また同五年の奥州管領奉行人の奉書は、岩城弥次郎隆兼に宛てられており、弥次郎隆兼は、建武元年の八幡宮造営注文に東目村の地頭として書かれている人物であり、岩城氏の惣領は隆衡のあと願真を経て隆兼に伝わったとするのが妥当と考えれれる。その傍証として、貞和五年(1349)八月、岩城隆兼は、好島荘内河中子に対する糟屋宗久の競望を停止させる奥州管領府の命を受けている。このような命令を受けたのは、隆兼が惣領であったからに外ならない。
乱世への序奏
明徳三年(1392)南北朝が合一されたのち、将軍足利義満は陸奥・出羽の二国を関東公方の管轄下においた。足利氏は京都に幕府を開いたのちも、武家政権発足の地であり、足利氏の出身地でもある関東の経営を重視していた。一方、建武政権の発足時、奥州の掌握を目ざした後醍醐天皇に対抗する上からも鎌倉を中心とした関東を掌握することは、足利氏にとって存亡にかかわる問題だったのである。そのため、元弘三年(1333)には弟の直義を鎌倉に下してその任にあたらせ、建武四年(1337)には嫡子義詮を鎌倉においたのである。義詮が二代将軍となったのちは、その弟の基氏が鎌倉に下され関東の統治にあたった。以後、基氏の子孫が鎌倉公方を世襲し、それを上杉氏が関東管領として補佐する鎌倉府体制が確立された。
こうして成立した鎌倉府は、関東の政治の中心として小幕府の体制を整え、国家権力たりうる権限を有していた。そのため、幕府から独立しようとする、あるいは幕府にとって代わろうとする動きを内在し、代を重ねるごとに幕府との対立的構図が顕在化していったのである。そこへ、奥羽の支配を幕府から認められたことで、関東公方は奥州武士との間に支配服従の法的根拠を持つことになった。
応永三年(1396)の「田村庄司の乱」に際して、関東公方氏満は岩城氏らに出陣を命じている。翌年、岩城郡の守護であった岩城氏の惣領が鎌倉に参上したが、そのとき、岩城惣領は飯野(伊賀)氏に銭一貫文を賦課している。おそらく、岩城惣領は郡守護として、伊賀氏や岩城一族、郡内諸領主に対して鎌倉当参合力銭を賦課したものと思われる。公方氏満は奥羽が支配下に入ったのち多数の代官目代を下していた。そして、田村庄司の乱を鎮圧したことで、応永六年(1399)さらに強力な鎮将として満直・満貞をそれぞれ篠川・稲村の御所として下向させ、奥州武士に対する鎌倉府の支配強化を進めたのである。
満直・満貞が下向したころ、岩城惣領は郡守護=検断職を掌握していた。そして、白土・好島らの岩城一族に惣領としての立場で望み、伊賀氏の所領を蚕食していた。しかし、やがて岩城氏内部では、白土を領した白土氏や好島を領した好島氏が台頭しつつあり、岩崎郡には岩城氏と同族にあたる岩崎氏が勢力を拡大していた。一方、南部には佐竹氏、北方の楢葉郡には楢葉氏、それに隣接する標葉郡には標葉氏、さらに行方郡には東海道守護=検断職を有する相馬氏が強力な勢力を形成していた。
岩城氏惣領制の崩壊
室町時代の応永年間以後、岩城氏の中心は白土氏となっていくが、白土氏は国魂系図の新田師隆の子隆行に始まるとされている。ところで系図によれば、隆行の子隆祐から照衡の代に至るまで、「岩崎を称す」「絹谷を称す」「鎌田を称す」などの記述がみられ、白土氏から一族が分出していたことが知られ、白土氏は中山・絹谷・岩間・頴谷・鎌田などに一族を展開していたようだ。
のちに岩城惣領となる隆忠に関して、もともと長友を根拠地とし、白土氏を攻撃して白土に進出したという言い伝えがあり、岩城朝義と関係が深かった薬王寺が荒廃していたのを、隆忠が再興したともされている。またこの隆忠は、朝義によって薬王寺を追われた僧正隆忠の生まれ変わりとされる。これらのことは朝義系と隆忠系(白土)の対立を伝えたものと思われ、白土系が朝義系に取って替わったことの大義名分を物語ったものともいえよう。さらに、隆忠を僧正隆忠の生まれ変わりとし、長友から白土に進出したとしているのは、長友に根拠地をおいた朝義系と白土に本拠を置いた白土隆忠との系譜を続けようとする意図が働いたものと考えられる。
そのことを物語るように、諸系図に記される隆衡の跡は隆守−義衡−照衡−照義−朝義と続くが、これらの名前は根本史料には一切登場しないのである。南北朝期に岩城氏の惣領であった隆兼のあと、岩城氏惣領として根本史料に登場するのは、「隆教」と「隆泰」らである。しかし、諸岩城系図には隆兼も、隆教・隆泰ともに記されていないのである。これは、のちに岩城惣領となる白土系岩城氏とは別系岩城氏であったため、白土岩城氏が惣領になったとき、古文書・系図類が没収され、作為が施された結果と考えられる。かくして、のちに岩城惣領となった白土氏は常陸守隆弘のころから頭角を現わし、清胤を経て隆忠の代に本来の惣領家であった岩城氏に替わって新惣領となったものとみて間違いないだろう。
このことは、岩城氏に限ったことではなく、南北朝時代は惣領制の崩壊という側面を有しており、有力庶子家による惣領家の乗っ取りという事例は全国的に見られるものである。いわゆる、戦国時代における下剋上の先がけをなす社会事象の一つであった。
争乱の時代を生きる
応永十七年(1410)、海道に五郡一揆が結ばれた。この一揆は両御所に対抗するために結ばれたもので、岩城・白土・好島・諸根・相馬・楢葉・標葉ら海道五郡に居住する十名の国人たちが名前を連ねている。ここでは海道五郡が一つの地域として意識され、そこに帰属する人たちは強い一体感をもって行動したものと思われる。このように海道五郡が一体のものとして意識されたのは、中世においてこのときが最初で最後であった。『寛政重修諸家譜』や東奥標葉記』などにみえる海道小太郎成衡の五子の五郡分封のことは、この「五郡一揆」が解体し、そのなかから岩城氏や相馬氏が抜け出して大名化していった時期に、岩城氏がその覇権を主張するために構想したものではないだろうか。
応永二十三年になると鎌倉府内部に分裂が生じた。すなわち「上杉禅秀の乱」であり、幕府ははじめ静観の立場をとったが、のちに持氏を援けて氏憲の征伐に踏み切り、駿河今川氏・越後上杉氏らを出陣させた。この乱において、いわき地方の国人をはじめ南奥の国人の多くは禅秀に味方した。篠川御所満直も禅秀方に加担したため、五郡一揆は次第に満直と結ぶようになった。その後、持氏方が優勢になると満直や五郡一揆は禅秀支援をやめて幕府方に転じている。このように、国人たちは絶えず変化する情勢に対応して、自己に有利な行動をとっていたのである。
乱が鎮圧されたのち、関東公方持氏は禅秀に加担した関東の諸氏征伐を開始した。それは、幕府が支援する京都扶持衆にも及ぶようになり、ついには幕府と鎌倉府との間に不穏な気配が流れるようになっていった。応永三十一年(1424)、京都と鎌倉は一応の和睦をしたが、事態はそれですべて解決とはいかなかった。篠川御所満直は、関東・奥州の京都扶持衆を保護するように幕府の命を受けていた。また正長元年(1428)、京都と鎌倉の関係が悪化すると、幕府は南奥州の国人らに御内書を送り、鎌倉を背後から牽制するように命じていたことが『満済准后日記』にみえている。そして、御内書を送られたのは伊達・葦名・白河・石橋・懸田らの南奥諸氏とともに岩城・岩崎・標葉・相馬らの海道諸氏らであった。
その後、永享三年(1431)ふたたび幕府と鎌倉府の関係は和解するが、七年にいたってふたたび対立し、永享十年(1438)関東公方足利持氏は「永享の乱」を起こした。この乱に際して幕府は、持氏と対立した関東管領上杉憲実を援助するよう南奥の諸将に命じた。おそらくいわき地方の国人たちも幕府方に参戦したものと思われる。乱そのもは持氏の敗北に終わり、捉えられた持氏は幕府の命で自刃し、鎌倉府はいったん滅亡した。永享十二年三月、下総の結城氏朝が持氏の遺児安王丸・春王丸を奉じて兵を挙げた。「結城合戦」と呼ばれるもので、幕府は上杉清方を大将として討伐軍を派遣した。岩城一族もこの合戦に参加し、岩城隆忠は親類被官らが討死あるいは傷を蒙った軍忠に対し、将軍義教から感状を受けている。結城合戦の最中に、篠川公方満直は周辺の国人らによって攻め殺されている。鎌倉府の滅亡によって、その存在意義が失われた結果であった。
このように関東が争乱に明け暮れた、応永年間から明応年間(1394〜1500)にかけてのいわき地方をみると、その初期は、岩城、岩崎両氏を中心とした国人領主相互の対立が激しくなる時期であり、中期はいわき地方の国人領主が白河・石川等の周辺国人をも巻き込んだ嘉吉の内訌が起こり、いわき地方を統一して岩城新惣領となった白土隆忠の活躍した時期であった。そして末期にあたる応仁三年(1469)から明応八年(1499)までの二十余年間は、領内支配を固めた岩城氏が、いわき地方の外に発展しようとする時期である。
この間のいわき地方に関する多くの古文書が残されているが、なかでも嘉吉の内訌と称される時期に多くの文書が残されている。このことから、このころいわき地方は大きな変動期に見舞われていたことが知られる。そして、その中心となったのが岩城清胤と岩城隆忠であったことは、二人の文書が圧倒的に多いことで知られる。そして、隆忠は伊賀氏を完全に岩城氏の支配下に組み入れ、さらに有力一族である岩崎氏を滅ぼし、併せて各地に散在する一族を従えていった。こうして岩城隆忠はいわき地方を統一し、岩城氏が戦国大名へ発展する道を拓いたのである。
岩城氏の勢力拡大
隆忠の跡は親隆が継いだ。親隆は文明六年(1474)白河政朝と兄弟の契約をし、これを後楯に楢葉を攻略した。その後、家督を常隆に譲ったが、親隆は常隆とともに政事にあたっており、このころ白土から大舘に拠点を移したことが知られる。それは、文明十五年(1483)のこととされ、以後、大舘城が戦国時代末期まで岩城氏の拠点となるのである。このように、親隆・常隆父子は協力して領内の掌握につとめ、本拠を大舘に移して一応それに成功した。以後、掌握した領内を基盤に、領外への発展を企てていくことになる。
一方で、いわき地方の南隣にあたる常陸では、佐竹氏とその有力一族である山入氏とが対立する「佐竹の乱」が一世紀近くにわたって続いていた。領内を固めた親隆・常隆父子は、文明十七年、「佐竹の乱」に介入、常陸に入り多珂郡の車城を攻略した。そして、この車城に常隆の弟隆景を入れて車氏を名乗らせ防備を固めた。こうして岩城氏は佐竹氏の太田城を直接脅かすようになった。
佐竹氏の内訌は、小野崎・江戸両氏と結ぶ山入氏が優勢となり、佐竹宗家は太田城を追われるという危機を迎えた。ところが、太田城に入った山入義藤が死去したことから、佐竹氏と山入氏との間で和議の気運が高まった。そこに岩城氏が調停の労をとったことで、明応二年(1493)ついに両者の和議が成立した。しかし、和議が成立したにもかかわらず、山入氏義は太田城を明け渡そうとせず、かえって佐竹義舜を金砂に追放したため、「佐竹の乱」が再発した。そして、岩城氏はじめ小野崎・江戸氏らの支援を受けた義舜が氏義を太田城に攻め、ついに山入氏を討ち太田城を奪い返すことに成功した。山入氏は滅亡し、佐竹氏の領内統一がここに実現され、以後、佐竹氏は戦国大名への道をひた走ることになる。
常隆は明応六年(1497)矢河瀬禰宜職を飯野氏に安堵し、二年後には飯野出羽守に対して、他国への陣役と田銭とを免除し、飯野八幡における飯野氏の支配権を安堵した。また、小川長福寺住持職を安堵するなど、領内の社寺の禰宜・住持職にまでその権限を及ぼすにいたった。
南奥州の最大勢力となる
永正七年(1510)、常隆は佐竹義舜と江戸通雅・通泰父子との新しい盟約を仲介した。そして、この年佐竹氏はかつての「佐竹の乱」に白河氏に奪われた依上保の地を白河氏の内紛に乗じて奪回したが、この奪回には岩城氏の支援があったようだ。常隆は系図によれば「御子数五十人」とあり、そのうち隆輔は舟尾殿、隆通は上田殿、隆時は富岡殿と注記されている。船尾は旧岩崎氏の本拠地であり、上田はいわきの南部にあたり佐竹氏に対する抑えを担い、富岡は相馬氏に対する抑えを担った。こうして、文明末年(1486)から永正ころにかけて、岩城親隆・常隆父子の佐竹一族に対する優位は歴然としていた。常隆の子由隆は永正八年ころ家督を相続したようだが、常隆も健在で一定の領主権を行使していたようだ。
他方、永正三、四年(1506・07)ころ、古河公方足利政氏と高基父子の間が不和となり、十一年ころ、その対立は頂点に達した。関東諸氏の多くが高基に与したため、政氏は奥州諸氏に加担を求め、なかでも岩城常隆・由隆父子に大きな期待を寄せた。しかし、当初常隆はいずれにも加担せず、両者の和解を進めたことが知られる。しかし、永正十一年(1514)常隆・由隆父子は、政氏の依頼を受けて佐竹義舜とともに出陣し、高基方の宇都宮忠綱らと宇都宮付近で合戦した。このとき、白河顕頼が岩城氏に応じて参戦しており、岩城氏の勢力は白河氏を圧倒するようになっていた。永正十七年には、岩城勢は那須山田城を攻撃し、翌大永元年(1521)にも那須口を攻めた。
大永元年の出陣は、白河氏から那須氏に入った資永が内訌で自殺したことに対する白河顕頼、あるいは政氏の要請によるものとされる。この戦いには、岩城氏の要請で小田・宇都宮両氏が出陣したという。さらに那須山田城を攻めた岩城勢のなかに、須釜・小野・栗出・大越ら石川一族、田村一族の名が見え、岩城氏の勢力が石川領の一部や田村領にも拡大していたことをうかがわせている。こうして、岩城氏は南奥の大勢力として政氏・高基父子から最も期待を寄せられる存在となり、常隆・由隆の二代において、南奥随一の勢力を有するにいたったのである。
ところで、常隆は由隆に家督を譲ったとするのが通説だが、由隆の前に盛隆に家督を譲ったようだ。しかし、諸系図に盛隆の名はみえない。とはいえ、盛隆は大永三年(1523)に修理大夫に任官していることから、実在していたことは紛れもない。ただ、嗣子がなかったようで、弟の由隆が養子にはいって岩城氏の家督を継いだものと思われる。一方、由隆は大永三年のころ政隆に家督を譲ったというが、岩城系図に政隆の名はみえない。そして、政隆の跡を継いだ重隆について、由隆の二男で始め白土を称したが、政隆の死去によって跡を受けて岩城氏の家督を継いだとされる。おそらく、政隆は家督を相続せず、天文三年のころに由隆から重隆に譲られたものと思われる。このように、南奥州に勢力を確立した時期における、岩城氏の家督継承については、不明な点が多く見受けられるのである。
南奥州の戦乱
天文三年(1534)岩城氏は白河氏とともに、伊達・葦名・二階堂・石川諸氏の連合軍に攻められ、敗れた岩城氏は木戸川・金剛川に敗走した。戦いの原因は岩城重隆が娘と伊達稙宗の嫡男晴宗との縁組を拒否して、白河氏に嫁がせようとしたためであったという。『奥羽茶話記』などは、大永三年(1523)のこととして、岩城と伊達の縁組を媒介した相馬重胤が重隆の違約を怒って岩城領の楢葉郡を攻め取ったのだという。いずれにしろ、合戦後に重隆の娘は晴宗に嫁いで、二人の間に生まれた第一子親隆が岩城家を継いだ。
親隆の生年は天文五・六年ごろと推定されており、晴宗と重隆の娘の縁組みをめぐる岩城氏の敗戦は、天文三年とする方が自然なようだ。そして、相馬氏の岩城領の楢葉郡への侵攻は、岩城氏が違約を攻められたのを好機として、稙宗の女婿である相馬顕胤が行ったものと考えられる。
ところで、晴宗の父にあたる伊達稙宗は子沢山で知られ、娘を田村・二階堂・葦名・相馬氏などに入室させ、男子を周辺諸氏に入嗣させている。晴宗と重隆の娘との縁組も岩城家中を掌握せんとする稙宗の遠謀であったとみて間違いないだろう。
天文十年ころになると、白河氏が佐竹・葦名両氏の圧迫を受けるようになった。岩城重隆は佐竹氏と親類関係にあり、白河氏とは友好関係を築いていた。天文十年、佐竹義舜の子義篤が白河領に侵入したとき、重隆は白河・佐竹両氏の和解につとめ、東館の破却を条件に和解が成立し戦いは佐竹氏の勝利となった。このとき、調停の代償として岩城氏は依上保を得た。こうして、岩城氏の勢力は、常陸多珂郡と依上保、石川庄の一部、さらには高野郡まで及ぼうとし、岩城氏は最盛期を現出したのである。
伊達氏天文の乱
天文十一年(1542)、南奥州に大勢力を築きあげ陸奥守護職に任じられていた伊達稙宗が嫡子の晴宗によって突如幽閉されるという事件が起った。いわゆる「伊達氏天文の乱」で、伊達氏の家中を二分する抗争に発展した。さらに奥州の諸大名をも巻き込んで一大戦乱となった。この乱に際して重隆は、一貫して女婿であり嗣子として迎える約束の孫重隆の父でもある晴宗に加担して行動した。一方、稙宗方には相馬・田村氏らが加担したことで、岩城氏は両氏と緊張関係におかれた。
乱は相馬顕胤らの活躍によって稙宗方の有利に展開し、苦戦に追い込まれた晴宗は岳父岩城重隆の支援に期待を寄せた。しかし、残された史料などからみて、当初重隆の行動は活発ではなかった。やがて、天文十四年ごろから活発な動きを見せるようになり、十五年には稙宗方の畠山氏に攻められた本宮宗頼を保護し、稙宗方に圧迫されている安積伊東氏に援軍を送って晴宗方の巻き返しを図ろうとした。
翌十六年になると葦名盛氏とともに安積口に出陣して稙宗党を牽制した。また、晴宗の要請をいれて海路相馬領を攻め、ついで田村領の小野新町を攻めた。こうした重隆の活躍と葦名盛氏の参戦によって晴宗党は次第に優勢に転じ、さらに田村家中が二分するなどして晴宗党の優勢は確固たるものとなった。
ここにいたって、田村隆顕が伊達父子の間を調停し、室町将軍からも停戦命令が下され、さらに将軍は葦名盛氏にも調停を命じた。ついに九月、伊達父子の和解がなり、天文の乱は終結して晴宗が伊達氏の家督となった。この乱における晴宗の勝利に果たした重隆の役割は、まことに大きなものがあったといえよう。以後、岩城氏は南奥に重きをなし、永禄十二年(1569)六月、重隆は死去した。重隆の跡は、先述のように伊達晴宗の長子で重隆には外孫にあたる親隆(宣隆)が継いだ。
佐竹氏勢力の浸透
先述のように天文十年佐竹氏は白河領に侵攻し、岩城氏の仲裁により高野郡南部を手中におさめた。その後も佐竹氏は白河領への侵攻を繰り返し、永禄初年の段階では、佐竹氏は菊田庄から御斎所を経由して石川庄の蒲田・赤坂をのぞみ、高野郡全域の経略を進めようとしていた。佐竹・白河両氏と好みを通じる岩城氏は、両者間の調停に尽力したことが残された親隆の書状から知られる。親隆は佐竹義昭の娘を室に迎え、二人の間には常隆が生まれていた。岩城氏は親隆の代になると衰退の色を見せるようになり、次第に佐竹氏からの介入を許すようになるが、永禄年間の親隆の書状などからは親隆が一定した自立性を保持しようとつとめていたことがうかがわれる。
元亀二年(1571)、佐竹氏は葦名盛氏・白河晴綱の連合軍と戦ったが、この合戦に岩城氏は佐竹氏を支援して出陣した。そのような同年、佐竹義重が岩城家中の船尾・窪田両氏の訴訟を裁決する書状、建徳寺と善門寺の権益を先例によって認許する書状を発給している。これらの義重の書状は、岩城氏の当主が持っている権限を行使したものである。このことは、岩城氏の家中に重大な事変が起き、それによって佐竹氏が岩城氏に介入してきたことを示したものといえよう。
親隆は祖父であり養父でもある重隆の在世時から、軍事・政治活動をしていたことは残された文書から知られる。永禄五から六年ごろには、二階堂盛義の懇望を入れて田村領に侵攻し、さらに、田村領小野・石川領蓬田に出陣して数百人を討ち取り、二階堂盛義父子を援けて岩瀬郡長沼に出陣している。また、重臣に宛てた書状から、葦名盛氏・盛興父子と敵対していたこともうかがえる。その一方で、叔父にあたる伊達実元に宛てた書状には、晴宗・輝宗父子の不和を憂慮し、輝宗の角田攻撃を止めさせるよう申し送っている。また、二階堂盛義と結んで会津を攻撃しようとしている輝宗の血気をいましめるようにも伝えている。輝宗は親隆の実弟であり、盛義の室は親隆の妹であった。親隆は輝宗・盛義と、これに対抗する葦名盛氏との間に立ってその講和の斡旋に当たろうとした。そして、永禄九年、伊達・葦名氏の和解は成立した。他方『磐城史料』には、永禄末年、常陸多賀郡の大塚掃部介が親隆に属して佐竹方の龍子山城を攻略した。その後、佐竹義重がこれを攻めたが落とすことはできなかったと記している。また『奥相秘鑑』には、元亀元年(1570)、岩城氏の軍勢が相馬領を攻め富岡・木戸を奪回したとある。
このように、親隆は南奥における戦国大名の一人として、近隣諸豪に伍して勢力を維持・拡大し、岩城氏の全盛期を保っていた。そのような親隆がいまだ当主であった元亀二年に、佐竹氏が岩城氏の家中に介入してきたのにはいかなる背景があったのだろうか。
岩城氏衰退の兆候
『奥相茶話記』に、「岩城親隆は仙道に出陣して勝利をえて首実検をしているところを、敵軍の不意打ちをうけて敗北、親隆はこれを無念に思い、ついに狂乱の病となる」と記している。この説を信用するならば、親隆は「狂乱の病」となった。そして、永禄十二年ごろの親隆文書を見ると、すでに花押がすえかねるほどに病状が悪化していたようだ。親隆の病が重くなると、夫人の佐竹氏が政務をみるようになった。そして、永禄十二年に重隆が死去したことで、佐竹氏は岩城氏の家中に介入するようになり岩城領の仕置きを行うようになった。それは、親隆の病をさらに重くすることとなり、いよいよ佐竹氏の勢力が岩城氏に浸透していったものと考えられる。
『磐城史料』に天正二年(1574)伊達輝宗が岩城領竹貫を攻めたのに対し、親隆は大塚・車・白土・大高の四将を派遣して竹貫城を援け伊達勢を破ったという。さらに元亀・天正の間、親隆の勢力は日々に強くなり、佐竹領を侵略し、ついには佐竹氏の居城太田城にほとんど迫るばかりとなった。まさに向かうところ敵なしといった状況であったという。しかし、この記事は親隆の病状のことなどから、そのままには受け取れないものといえよう。また、『福島県史』によれば、永禄三年(1560)佐竹義昭によって南郷が落ちたとある。さらに、佐竹氏の手が岩城氏に伸びていたようで、船尾式部大輔が佐竹義昭に従属していた様子もうかがえる。船尾氏は岩城一族であり、重要な一族が佐竹氏によって切り崩されつつあったことを示している。
永禄十年には、菊田庄の上遠野氏が岩城氏からの自立をみせている。こうして、岩城氏は佐竹氏への傾斜を強めるようになり、親隆の病気によってその介入を許し、衰退の兆候をあらわしながらも戦国大名としての立場を維持することにつとめていたようだ。やがて、親隆が病死(「寛政重修諸家譜」によれば、文禄三年(1594)まで生存していたとある)すると、常隆が母である親隆夫人の後見を受けて家督を継いだ。天正八年(1580)、佐竹氏が岩城領へ侵入したが竹貫三河守らの活躍で撃退に成功している。このころ、岩城領の北に位置する相馬氏は伊達氏と戦いを続けていて、常隆は伊達氏からの依頼を容れて両者の調停にあたり、佐竹氏などの協力も得て和議を成立させた。
岩城氏にとって伊達氏と連携することは、相馬氏を索制するためにも得策であった。しかし、伊達氏に近い田村氏と岩城氏は敵対していたため、次第に佐竹氏との連合関係が強くなり天正九年ころにはその関係は不動のものとなっていた。
伊達政宗の台頭
天正十三年(1585)十一月、佐竹以下の連合勢と伊達軍とは安達郡本宮観音堂・人取橋で激突した。この戦は、田村清顕の要請で大内定綱を塩松から敗走させた伊達政宗は、この年十月、二本松畠山義継のために不覚にして二本松へ連れ去られようとした父輝宗を義継もろともに銃撃するという痛恨事を招いた。政宗は父の復讐として二本松に兵を向けた。これに対し、佐竹以下の連合軍が二本松を救援しようとして起きたものであった。この合戦に、常隆は自ら三千騎の兵を率いて連合軍に参陣した。合戦そのものは、佐竹氏の留守をうかがった里見氏の軍のために、佐竹氏が軍を常陸に帰したため勝負は決しないままに一日で終わった。
ついで天正十六年六月から七月にかけて、安積郡の郡山・窪田をめぐり佐竹・葦名の兵と伊達政宗の兵が対峙した。いわゆる「郡山合戦」である。岩城氏はこの合戦には参加せず、両者の仲介調停の役をつとめた。常隆の骨折りによって佐竹・伊達両氏の間に和睦が成立し、八方に敵を抱える伊達政宗の常隆に対する感謝の念は深く、小川隆勝・白土隆通ら米沢に参上した岩城氏の家臣に対して政宗はそれぞれ引出物を与え、帰還する志賀右衛門に常隆への書状を託し、常隆に感謝の意をを現わしている。
その後、岩城氏は伊達氏と離れて相馬氏と結ぶ姿勢を示し、天正十七年(1589)下旬、常隆は大挙して田村領に侵入し、田村南部を岩城氏の勢力下に入れた。これに対して政宗は相馬に兵を出し、相馬領北方を攻めて新地・駒ケ嶺の二城を奪い、本宮から猪苗代に出馬した。そして、同年六月の「摺上原の合戦」で葦名氏を撃ち破り、敗れた葦名義広は実家である常陸佐竹氏のもとに走り葦名氏は滅亡した。ここに、政宗は一躍奥州の覇者となったのである。この情勢に、白河結城氏、石川氏らは伊達氏に帰属し、常隆も伊達政宗と講和した。
天正十八年二月の政宗書状によれば、常隆は政宗出馬の節は即刻応援の兵を多数出す由であるとのことが記されている。当時、政宗は相馬・佐竹氏と敵対しており、岩城常隆は因縁深い佐竹氏と敵対してでも政宗に従うという意志表明をしているのである。三月には、志賀式部が常隆の使者として黒川城に参上し、講和以後の岩城氏は伊達氏との友好関係の維持に努めていた。
その後の岩城氏
天正十八年(1590)、豊臣秀吉が小田原北条氏征伐の軍を起こした。この小田原の陣に参陣するしないは関東・奥羽の諸将にとってその後の運命を決定する重大な意味をもつものであった。すでに天正十五年の暮に、岩城氏家中の白土右馬助宛に秀吉判物が届けられていた。白土右馬助はかつて上洛し、羽柴時代の秀吉と相識る仲となっていたのである。
天正十五年当時は、伊達・佐竹をはじめ関東・奥羽の諸将は、秀吉の発した「惣無事令」の指令を無視して合戦を続け、岩城常隆は佐竹陣営の一角を構成しつつ、やがて伊達氏と講和するという政治的・軍事的行動をとっていた。しかし、秀吉の小田原征伐が開始されると、情況は大きく変化した。そして、五月、常隆は小田原参陣のために岩城を出発した。このころ、常隆は病に冒されていたが、それを押して出陣し無事秀吉に拝謁することができた。七月、後北条氏は降服して小田原城は開城された。その半月後に病の篤くなった常隆は相模国星谷において客死した。享年二十四歳の若さであった。『那須記』などには、那須氏を攻めて討死したとあるが、とるに足らない説といえよう。
常隆には男子政隆があったが、豊臣秀吉の取りなしで政隆は退けられ、佐竹義重の三男貞隆が継いで所領十二万石を認められた。『水戸市史』は小田原落城後、「江戸を発して陸奥に向かった秀吉は、途中で岩城常隆の死没を聞くと、自分に忠実な佐竹氏に命じて、義宣の弟をもって岩城氏を嗣がせた」と記している。また『武徳編年集成』は、秀吉が旧知の白土摂津守を岩城家督に立てるとの内意があったことを記しているが、どうであろうか。
関ヶ原の戦いにおいて岩城氏は東軍方になったが、上杉景勝征伐の不参加を口実に所領を没収された。その後の元和二年、大坂の陣参加の功により信濃国川中島で一万石を与えられ、さらに貞隆の子吉隆は出羽国由利郡に移封され、同郡内において二万石を領有し子孫は明治維新に至った。一方、常隆の実子政隆は伊達氏に仕えて五千余石を領し、のち伊達姓を許され一門となった。
【参考資料:東北中世史 : 岩城氏とその一族の研究/いわき市史/概説平市史/福島県史 ほか】
→ダイジェスト版へ
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
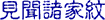

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|

日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
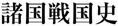
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
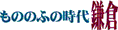

|
2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。
|
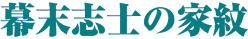
 これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
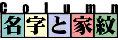

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

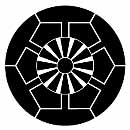
|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
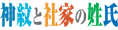

|
|

