

|
八戸氏波木井氏
●南部鶴/割菱
●清和源氏義光流
|
近世南部氏の所伝では、南部氏の初代光行は源頼朝の側近として仕え、文治五年の奥州征伐に従軍し、その功績によって、糠部五郡を賜わったという。光行は建久三年(1192)の春、三戸に平ケ崎城を築いて地頭代を据え、自身は鎌倉に帰り同地で没した。しかし、糠部五郡のことは信憑性の高い史料として有名な『吾妻鏡』などでは確認できず、現存する後世の文献にのみ見らればかりであり、鎌倉期の糠部郡の地頭・地頭代は北条家の御内人の工藤氏らに限られていたのである。光行が糠部五郡を賜ったという話は、そのままには受け取れないところがある。
系図によれば、初代光行には六人の男子があり、三男の六郎実長は波木井を称し、のちの根城(八戸)南部氏の祖となった。根城南部氏は南北朝において活躍、中世における南部氏を代表とするなった。
波木井南部氏と日蓮
ところで、波木井南部氏は日蓮宗と関係が深かったことはよく知られている。
日蓮は日蓮宗の開祖で、十二歳のときに出家し、鎌倉や比叡山で修行を積み、建長五年(1253)に立宗した。そうして、鎌倉に出て布教活動を開始した日蓮は、文応元年(1260)に有名な『立正安国論』を書き執権北条時頼に建白した。その内容は天変の予言とその要因としての激しい他宗攻撃で、幕府や宗教界の反発をかった。そのため、さまざまな法難にあうが屈することなく、蒙古襲来をにおわす国書の到来を機に、改めて幕府の対応を強く非難した。そのため、日蓮は幕府に捕えられて佐渡へ流された。そして、文永十一年まで流人生活を送り、許されて鎌倉に帰着すると、幕府の下問に対して蒙古襲来の危険性を示唆したが、結局入れられることはなかった。
そのような日蓮に手を差しのべたのが波木井太郎実長で、日蓮も実長の求めに応じて、文永十一年(1274)五月十二日、身延へ出立したのである。身延に到着した当初は実長の館に滞在していたが、身延山中に草庵ができると、そこに移り住んだ。こうして、日蓮の晩年八年間の修行の場となった身延山は日蓮の心を捉えたようで、墓所にせよとの遺言が残され、のちの身延山久遠寺の発展をみることになるのである。
日蓮の身延での宗教生活を支えたのは波木井実長であり、実長が日蓮の信徒になったのは、御家人として鎌倉に出仕した正嘉元年(1257)のことであったという。しかし、実長の日蓮宗への入信時期は、文永六年(1265)に日蓮の弟子日興を介してのことであったとする説が有力である。いずれにしろ、実長は熱心な日蓮宗の信者となり、嫡男の実継をはじめ二男の実氏、三男の祐光などの一族も日蓮宗の信者となっている。
実長のあとは四男の長義が継いで波木井南部氏の二代となったが、長義も日蓮宗の信徒で、正和二年(1313)の死去の前年に、父が寄進した身延山の地を安堵する置文を残したといわれる。一方、嫡男実継の流れは本家から養子として迎えた師行の代に奥州糠部に下って奥州南朝方として活躍、その子孫は根城を本拠として戦国末期にいたって八戸氏を称した。一方、長義の系は甲斐にとどまり、戦国時代まで勢力を維持したことが知られる。
根城(八戸)南部氏の台頭
根城(八戸)南部氏が奥州と関わりを持つはじめとなったのは、鎌倉時代末期の「安藤の乱」に際して、波木井南部長継が糠部に出陣したときと見られる。長継のあとは甥にあたる養子の師行が継ぎ、師行は新田義貞の鎌倉攻めに応じて挙兵し、師行の弟政長は奥州より兵を率いて義貞軍に加わり鎌倉に攻め上ったとある。このことからも、鎌倉末期に南部氏の所領が奥州にあったことがうかがい知られる。
鎌倉幕府が崩壊したのち、陸奥は後醍醐天皇の皇子義良親王をいただいた陸奥守北畠顕家が多賀国府に下って、諸政をとるようになった。甲斐にあった波木井(根城・八戸)南部氏の当主である師行も、このとき顕家に従って陸奥に下向したものと思われる。
陸奥の国司となった顕家は、陸奥の領主や諸将士に向って所領は国司の国宣をともなう安堵状によらなければ領知権を認めないと布告した。そして、こうした国司の代行者として南部師行は糠部に派遣され、領知権の認証や、領地を没収された北条方の武士たちの処理にあたった。さらに、師行の活躍範囲は久慈郡・津軽郡・閉伊郡、出羽の比内・鹿角郡に及んでいた。
師行は当時の武士としては珍しい無欲な質であったようで、ことさらに恩賞を望まなかったようだ。そのような師行に対して北畠顕家は、師行の活躍に対する恩賞と旧勢力の反乱発生を押さえる意味もあってか、糠部に望みの地があったら申し出よといっている。こうして、根城(八戸)南部氏は宗家にあたる三戸南部氏に代わって大きく台頭したのである。その一方で、本来南部氏の嫡流たる三戸南部氏の南北朝時代における動向は不明な点が多い。断片的に残された記録から、三戸南部氏も南朝軍に属して活躍していたことが知られるが、根城(八戸)南部氏が最後まで南朝方に尽したのに対して、いち早く北朝方に転じたようだ。
奥州南朝方の中心として活躍
糠部の大平洋岸地域を平定した師行は、建武二年(1335)、顕家から津軽平定を任された。津軽はもともと北条方の有力な地盤で、安達高景や名越時如ら鎌倉北条方の残党が集まって再起を図ろうとし、その勢いはあなどりがたいものとなっていた。津軽の平定には、在地最大の豪族である安藤一族を味方にする必要があり、師行は安藤氏に対する工作を行い国司方につけることに成功、その年の暮れには津軽を平定することができた。
翌建武二年、「中先代の乱」が起こり、乱を鎮圧した足利尊氏が後醍醐天皇に叛旗を翻した。尊氏は奥州の南朝方に対抗するため一族の斯波家長を奥州に下向させ、反南朝勢力の結集につとめさせた。このような尊氏に対して天皇は新田義貞を大将とする討伐軍を送ったが、討伐軍は尊氏軍に敗れ、敗走する新田軍を追ってきた尊氏軍によって京都は制圧された。この事態に天皇は北畠顕家に上洛を命じ、顕家は奥州の兵を率いて上洛、尊氏軍を一戦に打ち破り尊氏は九州に逃れ去った。この顕家軍には、白河結城・伊達・葛西氏などが従い、南部政長の子信政が糠部の兵を率いて加わっていた。
翌延元元年(1336)、勢力を盛りかえした尊氏は西上の軍を起すと、摂津湊川で楠木正成を破り京都を回復した。以後、日本全国は南北に分かれて戦う南北朝内乱の時代となった。このころ、師行・政長兄弟は津軽にいて、足利方の曾我勢と戦いを繰り返していた。一方、顕家に対して親房から西上するようにとの指示が届いた。翌年、顕家は西征の途につこうとしたが、足利方の攻撃を受けて多賀国府を失い霊山に逃れるという状態で出陣は思うにまかせなかった。夏を過ぎるころになってようやく西上の軍を発し、この西征軍のなかには根城南部の当主師行も参陣し、留守の糠部は弟の政長が中心となって固める体制をとったようだ。
出陣した北畠軍は鎌倉に迫り、これを迎え撃った斯波家長を一蹴すると鎌倉で越年、延元三年(暦応元年=1338)正月に鎌倉を発した。途中、北畠軍を阻止せんとする石塔・今川などの足利一族の有力者を撃破し、美濃において高・土岐軍と戦ってこれも破った。ところが、何故か道を伊勢から大和に向け、奈良般若坂の戦いでまさかの敗戦を喫した。ほどなく頽勢を立て直した顕家は、五月、和泉国石津において高師直の率いる足利軍と戦った。最初優勢にあった北畠軍も長旅の疲労によって大敗を喫し、顕家は討死、南部師行も率いてきた糠部衆とともに壮烈な戦死を遂げた。
建武新政下の奥州でめざましい活躍を示し、わずか数年で糠部を拠点に南部氏の地位を不動のものとした師行であったが、最期は異郷に屍をさらす結果となった。
南朝に節を通す
師行には男子がなかったため、根城南部氏の家督は政長が継いだ。政長も兄に劣らぬ人物で、新田義貞の鎌倉攻めに加わり、その後は、兄師行をたすけて津軽地方の戦いに加わった。その恩賞として、建武二年に七戸を賜っている。兄師行が顕家軍に加わって西上して戦死したのちは、糠部の南朝方の中心的存在として活躍した。そうして、本拠の根城と七戸を固め、嫡子の信政を兄師行の嗣子とし、二男の政持を新田、三男の信助を中館に配して分家を起させ、北奥における南部氏の基礎を築いた。
師行や顕家が戦死したのち、新田義貞も北陸の戦いで戦死し、翌年には後醍醐天皇も吉野に没して、南朝は衰勢の一途をたどっていった。他方、足利尊氏は征夷大将軍に任ぜられ、奥羽の南朝方にも足利方に転向するものが少なからず出てきた。政長にも北朝方への勧誘が行われたが、政長はこれに応じることはなく、津軽北朝方の中心である曾我一族と抗争を繰り返した。そして、顕家のあとを受けて鎮守府将軍・陸奥介として新しく赴任してきた北畠顕信(顕家の実弟)を政戦両略において支え、退勢期の奥州南朝勢力の維持につとめた。
顕信は滴石、石巻、宇津峰を拠点として奥羽を奔走しており、政長は北奥の重鎮として顕信をよく輔弼した。また政長は南部氏の宗家である三戸南部氏の政行に足利方について所領の安堵を受けるようにすすめたということが、『三翁昔話』にみえている。この話をただちに信じることはできないが、政長が衰退していた三戸南部氏になんらかの支援の手を差し伸べたことが、そのように伝えられたものと思われる。
南朝方に尽した政長は、正平五年(1350)、波乱の生涯を閉じた。師行のあとを継いだ嫡子の信政は北畠顕家の第一次西征軍に加わったが、その後の活動は養父師行や父政長の活躍にかくれて明確ではない。一説に正平三年、楠木正行が幕府軍の乱れに乗じて挙兵したとき、その軍に加わって戦死したともいわれる。
政長の死後、信政の嫡子で嫡孫にあたる信光が八戸を継承し、弟の政光が七戸を継承した。正平六年(1351)に幕府を二分する「観応の擾乱」が起こると、信光は顕信による府中奪還作戦に従軍し府中奪還に成功した。しかし、翌七年(1352)には、吉良定家の率いる北朝勢に再び奪取され南朝勢は宇津峯城に拠った。北朝勢の猛攻撃によって、宇津峯城は翌八年に落城、籠城していた南部伊予守、浅利尾張守らは北朝に降った。宇津峰城は徹底的に破却され、顕信は出羽藤島城に撤退した。
正平十六年(1361)、信光は北奥最後の北朝勢力であった曾我氏を安藤氏と共に攻め滅ぼしているが、その後は糠部を引き上げて甲斐国の本領に撤退したと伝えられている。甲斐に引き上げるに際して信光は、糠部の所領は三戸南部氏に管理を委ねたといい、弟の政光は七戸に残ってたようだ。
甲斐国における根城(八戸)南部氏
以後、甲斐の波木井にあった信光は、正平二十二年の正月、神郷の領主神大和守の襲撃を受けた。不意打ちであったが、信光ら南部一党はこれを撃退し、大和守の居城を攻め落とした。信光はこれを吉野に注進、後村上天皇から恩賞として甲冑一領を贈られた。さらに、年来の軍忠を賞した綸旨と甲斐国神郷大和守跡半分を賜っている。
文中元年(1372)、出家した信光は嫡子の長経は幼少であったため、弟の七戸政光に家督を譲った。甲斐に移った政光は、明徳の乱に際して幕府軍の攻撃を受け、籠城三ヶ月におよぶ戦いを演じ幕府軍を撃退した。幕府はふたたび政光攻めの軍を派遣したが、南北朝の合一がなり戦の沙汰もやんだと伝えられている。
明徳三年(1392)に南北朝の合一がなると、南朝方の武士たちはこぞって幕府に降服していった。そのようななかで、甲斐の政光はこれを潔しとせず、南朝方に節を通していた。『八戸家系』によれば、孤忠を貫かんとする政光に対して、将軍義満に仕える三戸南部守行が、義満の意向もあって帰服の礼をとることを勧めにきた。それに対して政光は、「二君に仕えることを恥とするのです」といい、重ねて「白刃に伏くしても武家方の粟を食いたくない」と守行のことばに耳をかさなかった。守行は政光の言葉に感動しながらも、「本領である甲州波木井を去って、南朝から拝領した八戸に退けば、南朝から受けた封土も失わず、将軍よりの命は足下一世だけは君事しないで、祖先の祭祀を奉じ、子孫を保ってはいかが」とことばを尽して説得した。この守行の誠心からのことばに政光もついに幕府への帰順を承諾した。
守行は京に帰ってありのままを将軍義満に復命し「私の身命に代えて、承認していただきたい」と願った。義満は政光の忠義と守行の篤実に感じて、両名をおいにほめたたえ、これを許したと伝えている。かくして、政光は甲州を去って奥州八戸に下り、根城に住むようになった。ときに、明徳四年(1393)のことであったという。そして、政光は八戸の家督を長経に譲り、みずからは七戸に退き実子政慶とともに住み別家を立てた。
ところで、信光が政光に残した譲状は八戸のものだけであり、甲斐の所領に関する譲状は残されていないのである。さらに、政光は南北朝合一のなる前の1380年代に近隣の諸将らと一揆契約を結んでおり、そこにみえる年号は北朝年号である。これらのことから、信光の糠部撤退も政光の甲州撤退も近世になって作られた話であろうとする説もある。
いずれにしろ、政光の幕府への帰順によって、八戸南部氏と三戸南部氏の勢力は逆転し、以後、八戸南部氏は三戸南部氏の指揮下に入ったのである。
勢力拡大の戦い
長経の代の応永十八年(1411)、秋田湊にあって勢力を拡大していた安藤鹿季の山北進出を抑えようとして三戸南部守行が兵を動かした。このとき、八戸からは長経に代わって弟の光経が従軍したというが、この戦いはおそらく八戸南部氏が主体で三戸南部氏が援軍を出したというのが真相のようだ。
山北は八戸南部氏の所領であり、鹿角は津軽への重要な通路で日本海側への交通の要地であった。それだけに、八戸南部氏にとっては、総力をあげて安藤氏を撃退せんとしたのである。光経は出陣にあたり櫛引八幡宮に戦勝ののちは着用の鎧を奉納すると誓い、後村上天皇から拝領した鎧を着用して出陣した。戦は苦戦だったが、ようやく勝利をおさめて無事に凱旋することができた。
この戦において戦況不利におちいったとき、月山に勝利の祈願をしたところ、満願の日に双鶴と九曜星が懐中に入る霊夢をみた。これが、戦陣の瑞兆としてあらわれ、南部氏は大勝を得ることができた。この吉兆を記念して、以後、南部氏は家紋に「対い鶴に九曜」を用いるようになったと伝えられている。そして、櫛引八幡宮には後村上天皇から拝領した鎧を神宝として奉納し、併せて乗馬と乗替馬を神馬として奉納した。
応永二十三年(1416)の「上杉禅秀の乱」に際して、南部光経は禅秀方に味方して、葦名・白河結城・葛西・田村氏らとともに鎌倉に出陣して、関東公方足利持氏を駿河に奔らせた。禅秀が敗死したあとは公方持氏に帰服し、禅秀党の岩松持国の挙兵を武蔵国入間川で迎え撃ち、岩松を捕らえて相模国竜口で斬った。
その後の永享四年(1432)津軽安東氏を攻撃し、ついに安東氏を津軽から追い出してしまった。この合戦は幕府に持ちこまれ、幕府顧問の満済准后の日記によれば「奥の下の国、南部と弓矢の事について、下の国弓矢に取り負け、えぞが島で没落、仍ち和睦の事、連々申すあいだ先度仰せ遣わし候ところ、南部不承方申すなり。」とある。
このころになると、幕府は奥州の武将たちに対する統制力を失い、強いものが勝手に近隣の勢力を併合し勢力拡大をはかる乱世になっていた。光経は幕府の調停にも耳をかさず、強引に安東氏を攻め支配地域を拡大し、葛西・伊達氏らとともに奥州の実力者にのしあがってきたのである。一方、宗家である三戸南部氏は根城(八戸)南部氏と協力しながら、勢力を拡大していったようでもある。そして、三戸南部守行の代になるとにわかに八戸氏を凌ぐ勢いを見せるようになる。ちなみに守行の室は信光の娘で、光経と守行とは義兄弟の関係にあった。
八戸を称する
光経のあとは、長安、ついで守清と続いた。守清には男子が無かったため、一族の新田清政の子行吉が娘婿として家督を継承した。行吉はのちに政経と改め、この政経の代にそれまでの南部から八戸を称するようになった。奥州探題の大崎教兼からの書状にも「八戸河内守」と記されており、八戸南部氏が八戸を名字する在地領主として自他ともに認識される存在になっていたことが知られる。
政経の代の康正三年(1457)、下北の蠣崎蔵人との間で合戦があった。戦いの原因は、一説に後醍醐天皇の後裔という北部王家の当主義純とその一族を蠣崎蔵人が謀殺したことにあるといわれる。また蠣崎蔵人は「多年在京の勤番を怠り、猶我意の挙動仕候段達叡聞」したため、政経は幕府に働きかけて蠣崎追討の命令を取り付け攻撃を開始したともいう。
政経は津軽海峡から陸奥湾に入り、田名部に到って夜明けを待ち蠣崎城を攻撃した。八戸方の不意打ちに蠣崎の軍は壊滅して、蔵人は一族・家臣とともに海上を蝦夷島に逃れ去った。この結果、下北は八戸氏の所領となり、そのときの戦功で八戸氏の家臣二十人が叙任の推挙を受けた。このことからも、この戦は政経の私戦ではなかったことがあきらかである。余談ながら、蝦夷島に逃れた蠣崎蔵人は、その後、蝦夷島に勢力を築きのちの松前氏の祖になったと伝えられている。
応仁元年(1467)京都で「応仁の乱」が起こると、日本全国は戦国時代となった。奥州でも戦いが繰り返されるようになり、津軽・秋田に勢力を拡大した八戸氏は南に向って勢力を拡大しようとしていた。このような時代において、八戸信長はしばしば京都に勤仕し、『八戸家伝記』によれば「八戸当主南部但馬守信長は上洛して将軍及び天皇の御前で横笛を吹いて賞された」という。そのことは、一族の七戸氏に送った信長の書状から知られ、ときの将軍は足利義政、天皇は後土御門天皇とされている。
ところが、信長が南部七戸殿に宛てた書状は永禄七年(1564)前後のものであるとする説が出ている。すなわち、信長が滞在した京都の宿が南部氏の本家筋に当たる甲斐前守護職で相伴衆の武田信虎の屋敷であり、天台座主梶井宮門跡応胤法親王の名も同書状に見えることから、信長の横笛を称讃した将軍は足利義輝であったと検証され、信長の活躍時期は百年近くも繰り下げられべきであるという。となれば、政経の実子とされる信長と政経との間には少なくとも三世代は入るものと考えられる。ここでは『八戸根城・南部家文書』 の記述に従い、信長は政経の子としておきたい。
三戸南部氏の台頭
信長は北奥の有力大名として将軍に近侍し、その在京は三カ年にもおよんだといわれる。そして、三戸南部氏の衰退を後目に奥州南部党の惣領として君臨し、その支配地域は津軽・鹿角・比内・糠部に及び、三戸南部氏などの分族は全て党的結合によるもので、惣領権の名の下に互いに覇を競うという状況にあった。とはいえ、糠部・岩手などは三戸氏や九戸氏などの勢力が主力であり、応仁の乱のころになると、三戸南部氏の台頭が目立つようになってきた。
信長のあとは治義が継いだが、すでに戦乱のために京都に勤番することもなくなった。さらに、幕府の権威も失墜し、八戸氏もたんなる地方大名ということになり、八戸・下北・津軽の所領を守ることに専念したようだ。治義のあとを継いだは義継は病弱で天文八年(1539)に早世、男子も無く弟勝義も病弱だったため、八戸一族は誰を当主にするかで意見が分かれ、一門の田中飛騨守が八戸城を占拠するという事件も起こった。結局、勝義が家督を継いだが、八戸氏はもっとも困難な時代に一族の内訌を引き起こしたうえに病弱な当主をいただくことになった。
このように八戸氏が勢力を後退しつつあるとき、三戸南部氏は安信の登場により、勢力を大きく拡大していた。安信のあとを継承した晴政は、天文八年に上洛して将軍義晴から名乗りの一字を賜り、晴政は名実ともに南部一族の代表者としての権威を手に入れた。永禄六年(1563)には、将軍足利義輝の御番衆中の関東衆二十五人のなかの奥州の武将として葛西・最上・岩城・相馬氏らと並んで晴政と九戸政実が名を連ねている。ここにおいて、八戸南部氏と三戸南部氏との地位は逆転し、さらに九戸氏にも先をこされる状態となったのである。病弱な勝義が死去したのちは、一族新田氏行政の子政栄が八戸氏を継いだ。しかし、わずか五歳であったため祖父の新田盛政が八戸城に入って名代を勤めた。盛政が死去してのちの永禄十二年ごろから政栄の八戸氏当主としての活動がみられるようになる。
三戸南部晴政は、乱世の武将として戦略戦術にすぐれていて、果敢な軍事行動をもって周辺の諸豪族を攻略して支配地を拡大していった。しかし、晴政は戦には強かったが、一族や家臣の統率力にかけるところがあったようだ。晴政の拡大政策が一段落すると、一族の間に不和が目立つようになり、八戸氏と七戸氏の対立、櫛引氏が八戸を攻めるといった一族間の紛争が続いた。なかでも最大のものは、晴政の後継者問題であった。
三戸南部氏の内紛
南部晴政には、はじめ男子がなかったため、叔父田子高信の嫡子で長女の婿である信直を嗣子と定めていた。ところが、その後に男子晴継が生まれると、実子にあとを継がせたいと考えるようになり、信直との関係が悪化した。さらに、信直が謀叛を企てていると讒言するものがあり、晴政は機会をとらえて信直を殺害せんとした。この情勢に対して八戸政栄は北信愛とともに信直を支援し、晴政と信直の和睦に尽力した。しかし、元亀三年(1572)、晴政は川守田村毘舎門堂に参拝した信直を襲撃したが、信直の反撃によって晴政は兵を引いた。危難を逃れた信直は政栄に救いを求め、政栄も信直を八戸城に迎え入れ、以後、これを匿いつづけた。その後まもなく晴政は病死し、家督は晴継が継いだが晴継もまた病死してしまった。
晴継の死後、南部氏の家督を誰にするかで家中は紛糾した。すなわち、田子信直を推す派と、南部一族で家中の大身九戸政実の弟実親を推す派とに分かれた。結局、八戸南部政栄・北信愛・東朝政らの南部一族の有力者が推した信直が家督を継ぎ、九戸実親の家督相続は実現しなかった。信直は相続後、ただちに晴継の葬儀を執行したが、これに参列しない家臣もあった。しかも、葬儀を終えて三戸城へ帰る途中の信直が襲われるという事件が起こった。信直は窮地を脱したものの、相続問題をめぐる南部氏家中の抗争は根深いものがあった。
こうした南部一族間の結束の乱れをついた大浦為信は、津軽における主導権を握って南部氏から離脱して独立を果たした。この為信の動きに対して信直は、九戸政実に津軽出陣を命じたが、政実は動かなかったばかりか為信に同調する姿勢を示した。このような情勢によって、信直は三戸城を留守にして津軽退治に出陣できなかったのである。そのような天文十七年(1589)、豊臣秀吉が諸大名に上洛して下知にしたがうように命じた。三戸の南部信直にも命令が届いたが、家中不穏のため三戸を留守にすることができず、翌年まで延期をこうた。しかし、翌十八年になると九戸政実の離反も明らかであり、信直はまったく身動きがとれない状態に陥った。とはいえ、このまま秀吉のもとへの参陣を延引することは処罰の対象ともなりまさに進退に窮してしまった。
このとき、八戸南部政栄が鎌倉期以来の勢力を背景として小田原に参陣すれば、秀吉から独立した領主として認められることは疑いなかった。しかし、信直、政栄がそろって小田原に参陣すれば、九戸政実が挙兵することは目に見えており、秀吉のもとに参じなければ元も子もなくなってしまう。ここに至って、八戸南部政栄はみずからの独立大名への道を断って糠部に残り、信直に協力して一族や領内の動揺、分裂を阻止することに努めることに決したのである。
ここに、八戸氏は鎌倉期以来の独立した領主権を失うことになり、南北朝期から室町期における輝かしい歴史に幕を閉じ、三戸南部信直の家臣に甘んじることになった。一方、南部信直は八戸政栄の譲歩によって近世大名南部氏への道を開くことができたのである。
信直の旗下に属す
信直の小田原参陣に際して政栄は、嫡子の直栄を随行させている。一説には、小田原参陣のとき嫡子直栄を信直に随伴させたのは、独立を目論む意図もあったが失敗したともいう。しかし、信直が直栄を同伴したのは人質の意味が大きかったと思われる。いずれにしろ、小田原の陣に際して信直が後顧の憂いなく行動ができたのは政栄の出処進退が大きかった。こうして、八戸南部氏は南部藩家老として一万二千石を安堵され、近世大名南部氏の重鎮となった。
政栄の後、直栄、直政と代を重ねるが、八戸直政は張先の越後高田で急病を発し、帰国途中に死去してしまった。このとき、南部家当主の利直は姪にあたる直政夫人を南部家重臣の後添えにして、当主不在を理由に八戸氏の併呑を目論んだ。しかし、直政夫人はそれをきっぱりと拒絶し、八戸氏の存続を叔父利直に願った。利直もそれを容れて、直政の娘に八戸一族の新田政広の子、直義を婿養子に迎え家名を立てさせた。しかし、利直は八戸氏が弱体化したことにつけこんで、八戸領田名部三千石の返上、さらに八戸から伊達領境の遠野への移封を持ちかけたのである。この利直の申し出を直義が断れるはずもなく、八戸氏は南北朝以来の領地八戸(糠部)を去って、遠野移封となったのである。
江戸時代の八戸氏代々は南部藩家老首座・盛岡城代家老を勤め、別格諸家との位置付けで宗家と同等の家格で遇された。かくして、諸侯にも匹敵する家として江戸期を通じて存続し文政元年(1818)、南部姓への復姓が認められた。・2005年09月04日
【参考資料:岩手県史/八戸市史/南部町誌/八戸根城・南部家文書/陸奥南部一族 ほか】

|
史伝書房さまの記事には、大変お世話になりました。
|
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
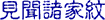

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
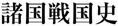
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
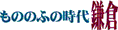

|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
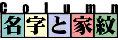

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

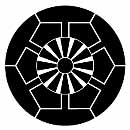
|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
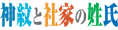

|
|

