
赤尾津氏
三階菱
(小笠原氏流) |

|
赤尾津氏は小笠原氏の一族、あるいは大井氏の一族といい、由利十二頭のうちで最大の領主であった。『湊・檜山両家合戦覚書』には、由利十二頭の中で「赤尾ツ一ノ頭也」と表現されている。由利地方の戦国時代における最大の勢力、それが赤尾津氏であった。
赤尾津氏の登場
由利地方の史料に国人領主があらわれるのは、宝徳二年(1450)のことである。すなわち、小助川立貞が年貢を横領したために赤宇曽領主である三宝院の訴えにより、幕府が未進年貢等催促の遵行を決定したということが知られ、小助川立貞はのちの赤尾津氏の祖にあたる人物と考えられる。しかし、のちに矢島氏の重臣として活躍する小介川(小助川)氏があり、こちらは矢島氏の同族であるといい、小助川立貞をそのまま赤尾津氏の祖と断定はできない。
由利地方の諸領主の興亡をつづった『由利十二頭記』には、応仁元年(1467)十二頭が打ち揃って信州から由利郡にやってきたとある。しかし、この由利十二頭記の記述は、さきの宝徳二年の小助川立貞のことをもちだすまでもなく、多分に物語的要素に満ちたものである。ちなみに由利十二頭記に記された赤尾津氏は、「赤宇津孫次郎道益」となっている。
さて、由利地方の国人として初めて記録にあらわれた小助川氏は、小助川地域を勢力下に置き、やがて赤宇曽地方まで勢力を伸ばしたことで、赤宇曽や赤宇津、赤尾津と称したようである。中世の武士は居館の地名をもって名字とすることが多く、赤尾津氏は居館のあるところの地名によってそれぞれ名乗りを変えたと思われ、こと赤尾津氏の名乗りに関していえば厳密な区別はないといえよう。やがて、亀田の南側に聳える高城山に赤尾津城を築いて本拠とした。
戦国時代の由利地方には統一勢力が存在しなかったため、赤尾津氏をはじめとした諸豪族が一揆契約を結んで、時代の荒波を乗り越えようとした。しかし、北方の秋田氏、東の小野寺氏、南の庄内武藤氏、さらに山形城の最上氏らの影響を受けることが多く、情勢によってその去従は定まらなかった。
天文元年(1532)小野寺氏の被官の仙北大曲城主前田氏が侵攻したとき、赤尾津左衛門尉(家保)はこれを迎え撃って前田氏を討ち取り、飛嶋を攻略し、嫡孫である長保をもって郡代に命じたという。一方、元亀三年(1570)赤尾津左衛門は前田氏らとの合戦で討死したとするものもあるが、こちらの左衛門は家保のあとを継いだ人物であろうか。
赤尾津氏の出自考察
赤尾津氏は赤宇津氏ともいい、さらに小笠原・池田・小介川・小助川・赤宇曾とも称した。『小助川氏系図』には、小笠原は甲斐国の在名、大井は信濃国の在名、小助川は、大井氏の流れで由利郡に移ってから称したとある。そして小助川とは中張村の川の名前であり、加えて赤尾津は由利郡の庄の名、小笠原は大井の本名とある。これらの記述は全面的に信用できるものではないが、先祖を同一にするある程度の結束力をもった集団が、小助川あるときは赤尾津・大井などを称する在地勢力として、由利地方に存在したことは疑いないことであろう。
赤尾津氏の系図は小助川氏系図も含めて諸本あるが、いずれも人名に異同があり、いずれが真かはにわかに判断できないものである。『源姓赤尾津池田系図』によれば、小笠原政長の子に俊光があり、その子に俊明・光貞を記して、俊明に仁賀保兵庫頭、光貞に赤尾津伯耆守と注している。
のちに、豊臣秀吉から領地安堵の朱印状を下付されたのは、諸本系図のなかで、赤宇津左衛門尉家保の子赤宇津光延のところに「先祖の領地二郷、安堵の御朱印を頂戴せり」とあるが、光延は天正十九年に死去したことが知られる。同年の九戸の乱には小介川治部少輔が出陣しており、秀吉の朱印を受けた赤宇津光延とは別人ということになる。また、小介川治部少輔は『源姓大井氏』に「小介川治部少輔」がみえるが経歴はまったく記されていない。先の小助川氏系図には、赤尾津左衛門−小介川治部少輔−赤尾津孫次郎光隆としているが、これも確認する手立てはないが、この系譜を源姓赤尾津池田系図にあてはめてみれば、赤宇津左衛門尉家保−赤宇津光延−赤宇津孫次郎長保となる。しかし、この系譜も赤尾津氏の歴代をあらわしたものとしては判然としないものである。
赤尾津氏の勢力
由利地方の所領高は、約五万石ほどであったという。そこに由利十二頭とよばれる諸領主が割拠していたのである。そして、赤尾津氏は由利衆のなかで「一ノ頭成」と呼ばれる大きな存在であった。
天正十五年(1587)二月、三戸城主南部信直が、重臣北左衛門佐信愛を名代として豊臣秀吉のもとに派遣した。北信愛は諸国が戦乱のために諸処を回り道をして、加賀国金沢の前田利家のもとに着いたのは四月のことであった。そして、利家を仲介として秀吉への謁見をはかったが、秀吉は九州に出陣中のため結局謁見はかなわず帰国の途についた。その道中で、酒田から南部までは物騒であったため、北信愛は赤尾津氏の掩護を受けたと「北信愛覚書」に書き残している。
北信愛を援けた赤尾津氏は、「軍記」などによれば「赤尾津左衛門尉大勢ヲ催シ同国仙北迄送」ったとある。赤尾津氏が庄内北部から由利地方にかけての実力者として認められていたことを物語ったものといえよう。また戦国期の日本図である「伊太利手稿日本図」によれば、出羽のなかに赤宇曾(安子津)、酒田、大宝寺(鶴岡)、最上、米沢の名が見えるという。これは由利地方の中では赤宇曾氏の居城のある赤宇曾のみが記されており、赤宇曾の名が全国的規模で知られていたことを示している。これは、赤宇曾氏の勢力の大きさをあらわした傍証の一つといえよう。
庄内武藤氏の侵攻
戦国時代、由利郡の南側にあたる庄内地方は武藤(大宝寺)氏が最大の勢力を築いていた。武藤氏は北進策を企て、義増の代から由利郡に割拠する由利十二頭との関係を結んで、安東(秋田)氏、小野寺氏と対抗しようとしていた。こうして、武藤氏と密接な関係を持つようになった由利衆は鮎川・矢島・禰々井氏らであった。一方、武藤氏と並ぶ庄内の有力者である土佐林氏も由利衆の仁賀保氏と関係を結び、武藤氏・土佐林氏と由利十二頭諸氏との間で複雑な相互関係が生まれてくるのである。
戦国時代の由利郡では、矢島氏と仁賀保氏が二大勢力として互いに抗争を繰り返したが、その背景には庄内の武藤氏、土佐林氏があり、庄内の動向に大きく左右されたものであったといえよう。
元亀元年(1570)、庄内では土佐林氏が叛乱を起こしたが、上杉謙信が調停に乗り出したこともあって鎮静化し、大宝寺義氏は庄内三郡の静謐をはかって、仙北の小野寺氏や由利郡内の赤宇曾氏、鮎川氏などと接触をはかっている。元亀二年、土佐林・竹井氏らはふたたび義氏に叛旗をひるがえした。義氏は竹井氏をやぶり、土佐林の投降を許して事態を収拾した。こうして、大宝寺義氏は庄内を平定し、北接する由利郡の国人らも大宝寺氏によって把握されるようになった。
以後、大宝寺義氏の北進策が実行に移され、由利地方で大宝寺氏に従わないのは赤宇曾の小介河氏を残すのみという状況になった。赤宇曾は由利地方の北端に位置し、秋田氏と深い関係を結んでいた。そして、秋田氏にしても大宝寺義氏によって由利地方が領国化されることは、看過できない事態であり、秋田愛季は小介河氏を支援して義氏と対立したのである。
そして、小介河=秋田氏と大宝寺義氏は攻防を繰り返した。天正十年に入ると、新沢館を中心に武藤方と小介河=秋田方は数度の合戦を繰り返している。三月には武藤方が筵掛権現堂に夜襲をかけたが、秋田方の手強い反撃で戦果は挙げられなかったようだ。新沢館は小介河氏の本拠であり、武藤方の攻撃に対して秋田氏とともに死守したということになる。
天正十年十二月、義氏は由利攻略の兵を起こして秋田方の砦を攻撃し、翌年には新沢城を攻め、その外構えをことごとく撃ち破り、焼き払い、城を残すばかりとした。このとき、由利衆のほとんどは大宝寺氏に加担して攻撃軍に加わっていた。しかし、小介河氏は秋田氏の応援をうけて大宝寺氏の撃退に成功し、義氏は兵を引き上げていった。この戦いは「新沢の合戦」とよばれ、この戦いに敗れた大宝寺義氏は間もなく家臣の叛乱にあってあえなく自害をして亡んだ。
由利五人衆
天正十八年(1590)小田原北条氏を降した豊臣秀吉は奥州仕置を行い、奥羽地方に太閤検地を行った。この間、奥羽では大崎・葛西・白河氏など多くの大名が没落した。そして、秀吉から領地安堵を受けた領主たちには「領地宛行朱印状」が交付された。
由利地方では、軍役賦課から推して赤宇曾氏四千五百石、仁賀保氏四千石、滝沢氏二千八百石、打越氏千六百石と割り出されていたが、「仁賀保文書」によって、仁賀保氏は三千七百十六石、打越氏は千二百五十石と推定高よりやや低かったことが判明した。それから推して赤宇曾氏の実際の安堵高は四千石程度であったと考えられる。とはいえ、由利衆のなかではもっとも多くの知行高を安堵されたのは赤宇曾氏であったことは変わらない。
このようにして由利衆は新時代に生き残ることができたが、それぞれの所領高はあまりに小さく、それぞれ個別では豊臣政権からの軍役を負担し、勤仕することは無理であった。そこで由利五人衆が設定され、他の由利衆は五人衆に配属させて把握するという由利衆の再編成が行われたのである。
五人衆とは、小介川(赤宇曾)治部少輔・仁賀保兵庫頭・滝沢又五郎・岩屋能登守・内越宮内少輔の五氏であった。そして、天正十九年の九戸の乱に際しては、赤宇津長保が出陣し浄法寺の合戦に敵将櫛引河内守を討ち取り、出羽国の軍勢の一員として活躍したことが系譜に記されている。
その後、文禄二年(1593)に秀吉が朝鮮侵攻を行ったとき五人衆は大谷刑部少輔の一手として軍役を担った。さらに、文禄五年(1596)には伏見作事用板の負担を命じられている。この由利五人衆の成立によって、由利地方の中世も終わりを告げたといえよう。
赤尾津氏の没落
関ヶ原の合戦に際しては、最上氏に属して出羽合戦に参加した。このとき、西軍の流したデマを信じた大半の由利衆は逃亡したが、赤尾津氏は岩谷・滝沢・仁賀保氏らとともにとどまり、戦後、出羽の大大名となった最上氏に仕えたといわれる。
『最上家譜』には、秋田・戸沢・赤尾津・六郷・仁賀保の各氏は、関ヶ原の戦に不参加のため転封を命じられ、最上氏が由利一円を領有したとある。また『秋田・最上両家関係覚書』に、最上義光の讒言をめぐって秋田実季と義光の家臣坂紀伊守とが対論した。その過程で由利衆の証言が求められた際、出座した由利衆は仁賀保兵庫頭・赤尾津孫二郎・内越の三名であった。この時点では、赤尾津氏は由利衆の一員として徳川政権から認められていたことが知られる。しかし、その後次第に由利衆は公的な史料に名を見せなくなる。これは関ヶ原の戦の戦後処理のなかで、「由利衆」とよばれた存在は徐々に解体されていった結果と考えられる。
そして、関ヶ原の戦後、仁賀保氏と内越氏は徳川氏の家臣として、すなわち徳川旗本(幕臣)として存続を許された。滝沢・岩屋氏は最上氏の家臣として続くことになった。ところが、赤尾津氏のみが「赤宇曾離散」という改易処分を受けたのである。
赤尾津氏がいかなる理由で改易に処せられたのかは、充分に明らかにされているわけではない。『秋田県史』では「赤尾津・滝沢・岩谷らは、最上氏の家臣となった。なお赤尾津氏は間もなく故あって罰せられて亡んだ」とある。また『奥羽永慶軍記』には「赤尾津孫次郎儀男子致早世」とあることから、赤尾津氏を継ぐべき男子に恵まれず、家が存続しなかったとも考えられる。いずれにせよ、赤尾津氏は「赤宇曾離散」し、中世のままの形態では近世に生き残ることができなかった。
かくして、由利十二頭の有力者として戦国時代を生き抜いた赤尾津氏は、他の由利衆のように幕臣または最上氏の家臣として存続することはなく、一族の一部が最上氏・佐竹氏などの家臣となって家名を伝えるのみとなったのである。
【参考資料:由利郡中世史考/大内町史/本荘市史 ほか】
→ダイジェストへ
→由利十二頭通史・家紋拾遺へ
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
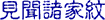

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
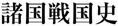
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
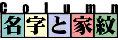
|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
|

