

|
留守氏
●桐/菊桐
●藤原北家道兼流
|
留守氏は頼朝の奥州征伐後、陸奥国留守職に任命された伊沢左近将監家景を祖としている。家景の出自については諸説があるが、『余目氏家譜』などによれば、家景は藤原道兼の五世の後裔と伝え、道兼は藤原氏摂関政治の全盛時代を現出した道長の兄にあたる。
家景は『吾妻鑑』の文治三年(1187)二月二十八日の条に、「右近将監家景、昨日京都より参着す。文筆に携わる者なり」とみえるように、鎌倉武士とは違った公家あるいは文官型の人物であった。そして、北条時政の推薦によって文官として頼朝に仕え、大河兼任の乱後、陸奥国留守職に任ぜられて多賀国府に来住したのであった。
勢力基盤を築き上げる
家景が就任した留守職は主として民政・財政を担当した役職で、陸奥の国内新地頭らへの国務上の命令権を有する重要な地位であった。建久元年(1190)の頼朝下文によれば、頼朝は従来の律令制を是認しながら、家景をして国務の任に当たらせた。そして、家景は多賀国府の在庁官人らを指揮命令したことは疑いの余地はなく、留守職が家景の子孫に世襲されるに及び、その指揮下にある在庁官人らとの間に主従関係結ばれるようになった。
一方、地頭らも留守職にある家景の下知に従って国事を勤め、もしこれに従わないときは、頼朝の命を受けて留守職が処分することができた。この意味においては、留守職にある家景は一般の地頭御家人より上位の存在であり、葛西清重とともに奥州総奉行と呼ばれたのである。ただし、国内地頭の上位にあるとはいえ、かれらに対する支配権は持ち得なかった。国内の地頭御家人はすべて頼朝の直接支配下にあり、留守氏も鎌倉御家人としては彼らと全く同格の立場であった。とはいえ、留守職に任ぜられたことが、その後の発展に大きく寄与したことはいうまでもないだろう。
ところで、家景の代は伊沢を号していたが、二代家元以降、職名を名字として留守を称した。また、家景の弟の小四郎家業は留守一族の筆頭で、のちに宮城氏の祖となった。そして、留守惣領は多賀城国府周辺の「高用名」と呼ばれた地域の地頭で、初期の居城は、利府の加瀬あたりにあったと考証されている。
留守氏は陸奥国留守職として、陸奥一宮である塩竈神社の奉幣祭祀を勤めたことが『別当法蓮寺記』に記されている。また、嘉禄三年(1227)の北条時房・泰時連署の下知状によれば「およそ神官は神主に相従い、神事を勤行すべし、神主は神官を憐愍し、先例に任せて沙汰致すべし」とある。ここにいう神主とは留守氏であり、神官は塩竈神社社人である。このように留守氏は塩竈神社の神主職となり、神社の神事勤行にまで強い支配力を有した。そして、社領の少なからぬ部分が留守氏の有するところとなり、社官たちは「宮侍」として留守氏の家臣として掌握されるようになり、留守氏の勢力拡大につながっていたのである。
留守氏の興亡
このようにして、留守氏は多賀城国府周辺の「高用名」と呼ばれた地域の地頭であるとともに塩竈神社の神主を兼帯して、北は別府、西は岩切、南は高砂、東は塩竈にまたがる地域を支配した。
『吾妻鑑』によれば三代家広まで留守職としての権限を持っていたようだが、次第にその機能を失い、一介の地頭に成り下がったようである。塩竈神社の実権は家広の弟良弁が実権を握っていた。家広の後を家政とする系図が多いが、恒家が正しいようだ。しかし、恒家の事蹟は不明である。家政は別に家を興し、のちの「余目氏」の祖となった。余目氏は後代、留守氏をしのぐ勢いをみせ、中世の諸大名の動向を知る史料として貴重な『余目記録』を残したことでも知られる。恒家のあとは、家信・家助とつづいたが、その動向は詳らかではない。わずかに、「塩竈神社文書」に記録が見え、塩竈神社の神主として活動していたことが知られるばかりである。
南北朝時代には、留守三郎左衛門尉が北畠顕家の南朝軍に属して転戦したことが知られる。この三郎左衛門尉は、留守氏七代の美作守家高に比定されている。留守氏は、顕家軍に属して津軽や白河方面に転戦し勲功を挙げたが、延元元年(1336)、出征先の三河国矢作宿において北朝方に転じて、以後、南朝方と戦っている。
八代家次の代には、「観応の擾乱」の余波で、正平六年(1351)畠山高国と吉良貞家の奥州二探題が争う「岩切城の合戦」が起こった。合戦は吉良氏の大勝で、「負け大将」の畠山氏に味方した留守家次は討たれ、余目・宮城などの一族ともどもほぼ全滅という悲運に見舞われ、留守氏は衰退してしまった。その頃の留守氏は新田城を本拠としていたようだが、文和元年(1352)、足利尊氏から宮城郡など所領を安堵されて勢いを盛り返し、九代淡路守以降は高森城に拠った。その後、家明の代に、ふたたび吉良・畠山氏の抗争に巻き込まれ、長世保に出陣したが敗れてのちは大崎氏の支配下に入った。
戦乱の時代
十二代詮家は応永年間中期(1400年代はじめ)に、一族の騒動に巻き込まれ、大崎氏から切腹を命じられた。そして、そのあとを継いだ持家のとき、弟の飛騨守三郎二郎との間で家督相続の争いが起こった。持家派は伊達氏を頼り、飛騨守派は大崎氏を頼み、三年間にわったて抗争が続いた。結局、持家が勝って相続をしたが、以後、伊達氏の干渉を受けることが多くなり、文明年間(1469〜86)に伊達持宗の子郡宗が十四代を相続し、留守氏は完全に伊達氏の影響下に入った。
明応九年(1500)、郡宗の子藤王丸が早世したため、余目氏ら留守一族は相謀って、藤王丸の妹に伊達尚宗の二男四郎景宗を迎えて留守氏十六代の家督を継がせた。このころの留守氏は伊達氏の意を迎えるのに汲々としており、伊達氏から後継ぎを迎えることが得策と考えたのである。景宗が留守氏の家督を継いだ時代は、戦国時代の初期にあたり、室町幕府の権威は衰え群雄が割拠して互いに領土拡大のための戦に明け暮れるようになっていた。奥州では管領職にあった大崎氏の力が衰え、南奥の伊達氏が勢力を拡大していた。そして、留守氏は郡宗ついで景宗の入嗣によって伊達氏の勢力下に入り、伊達氏の勢力を背景に近隣諸領主と争うようになった。
留守氏にとって、宿命的なライバルは国分氏であった。留守氏と国分氏とはともに宮城郡の地頭であり「岩切の合戦」で対立して以来、互いに仇敵視し、しばしば武力衝突があった。留守氏の内訌の際には、国分氏が一時留守氏領を押領したこともあった。しかし、郡宗が留守氏を継いだころから伊達氏の力を背景とする留守氏の攻勢が目立つようになった。景宗が留守氏の家督をついでのちの永正三年(1506)、国分氏と武力衝突するようになり、天文年代に入ると、両者の抗争はいよいよ激しくなり、天文五・六年(1536〜37)にはついに合戦となった。
大永三年(1523)、伊達稙宗が「陸奥守護職」に補せられた。そして、稙宗は陸奥守護職として国分氏と留守氏の抗争に干渉した。しかし、両者の抗争は、その後もしばしば繰り返され、それぞれ規模と実力が伯仲していたことから決定的な勝敗はなく、それぞれが同格の領主として伊達氏の傘下に属するまで抗争は続いた。
伊達氏天文の乱
天文五年(1536)、大崎氏に内訌が起った。大崎義直は伊達稙宗に支援を頼んだため、稙宗は三千余騎を率いて大崎平野に向かった。このとき、牧野・浜田ら伊達氏の有力家臣をはじめ、黒川景氏・武石宗隆・長江宗武、そして、留守景宗と国分宗綱も稙宗に従軍し、大崎の乱は平定された。このころには、留守氏らの奥州諸氏は今や伊達氏の麾下にあったことがうかがわれる。
天文十一年(1542)、伊達稙宗と晴宗の父子が抗争した「天文の大乱」に際して景宗は晴宗方に属し、稙宗方に加担した国分氏を攻撃している。景宗が晴宗方に属したのは国分氏が稙宗方に加担したことに対するためであったとも考えられるが、実のところは、この乱を好機として自家勢力の発展を目論んだものにほかならない。実際、この乱のきっかけとなったとされる稙宗の子時宗丸の越後入りに景宗は同行することになっていた。このことからも、景宗がとくに稙宗に反対していたわけではなかったことが知られる。
晴宗方に属した景宗は、晴宗党として大きな役割を果たしながら、国分氏との抗争も続けていた。そして、国分氏との戦いは、かなり苦戦の様相を態していたようだ。天文十七年、稙宗・晴宗父子の和睦によって乱は終熄し、伊達氏の家督は晴宗が正式に継承した。以後、乱に活躍した景宗は晴宗との間に緊密な関係を結び、これを背景として大名化の道を進むことになるのである。景宗の代に作られた「留守分限帳」は戦国時代における留守氏の家臣団、所領など、また、戦国大名の統治組織などを知るうえでの史料として価値が高いものである。
天文二十三年(1554)留守景宗の死によって、嫡子顕宗が留守氏をついだ。しかし、病弱の顕宗は父景宗が戦国武将として活躍をしたことに比べ、父の陰にかくれて目立たない存在であった。弘治二年(1556)顕宗と留守氏一族の村岡兵衛、同左衛門との間に内戦がおきた。これは、弟孫五郎を立てようとする一族との家督相続問題であった。
政景の入嗣
しかし、孫五郎も病弱で、家中の花渕紀伊、吉田右近、辺見遠江ら外様の家臣団は伊達晴宗の三男政景を養子に迎え、伊達勢力を背景にして留守家の安泰をはかるべきだと主張した。これに対して余目伊勢、同三郎太郎、村岡兵衛、佐藤太郎左衛門ら留守家譜代の一族は反対し、留守家中は二派に分れて争うことになった。結局、政景の家督入嗣が決定し、内紛は一応の幕をひいた。時に政景は、若冠十九歳の若武者であった。
永禄十一年(1568)、政景は黒川郡の領主黒川左馬頭晴氏の女を室に迎えた。政景の岳父となった晴氏は政景と留守一族村岡氏との融和を計ったが、永禄二年(1559)村岡氏は村岡城にたてこもり政景に対し反旗をあげた。政景勢は村岡城を攻め、村岡兄弟の叔父、郷家宮内が降参、村岡兄弟は深手を負うて退散し名取川辺で死去した。ここに、鎌倉時代以来留守一族の有力者だった村岡氏は滅亡した。その後も、余目氏、佐藤太郎左衛門父子らが政景に叛意を示し、政景はかれらとの対立を余儀なくされたが、それぞれ追放処分にしている。
このように政景は入嗣当時、留守家内部の反伊達勢力の抵抗にあいこれと戦った。そして叛乱を一掃した天正二年(1574)、米沢城下を訪れ兄輝元の麾下に属した。以後、伊達氏と留守氏は緊密な関係のもとに周囲の情勢に対処することになったのである。
天正三年三月、伊達氏に敵対していた二本松義継が輝宗に和を請い、二本松方面が一段落した。翌年の八月、輝宗は相馬氏を討つため、諸軍を率いて伊具郡に出撃した。このとき、政景も輝宗に従って伊具郡小斎に出陣した。その間、葛西氏領では本吉氏の反乱や大崎氏との戦いがあり、奥州各地で戦乱が続いていた。小斎に出陣した政景は葛西晴信に書を送り、葛西と大崎の戦いに応援軍を出したいが、出陣中のため不可能なことを述べている。翌年には、対相馬戦の陣代として伊具郡小斎に在陣するなど、兄輝宗を助けて活躍する政景の多忙ぶりがうかがわれる。
大崎合戦
政宗の代になると、政景は伊達家の重臣として若い政宗を補佐した。天正十三年(1585)十一月の仙道人取橋の合戦では、佐竹・葦名らを中心とする反伊達連合軍約三万に対して政宗軍は八千でしかなかった。この合戦に政景は一方の将として出陣し、奮戦力闘して連合軍の攻撃を阻止した。
ついで天正十六年、大崎氏家中の内訌に介入した伊達政宗により、大崎討伐軍の大将を命ぜられた。このとき、泉田重光も大将に命ぜられ、伊達軍は二人の大将を抱くという陣容になった。伊達軍は千石城に集結し、大崎方が籠城する中新田城攻略の軍議を開いたが、その席上で政景と重光が対立した。最新の装備を誇る重光らは強硬論をもって大崎勢を一蹴しようとした。その驕慢を危惧した政景は慎重論を述べたが、重光らは敵将である黒川月舟を岳父とする政景に暴言を吐いたのである。あわや一触即発の事態となったが、その場は収まり、伊達軍は先陣を泉田重光が率い、政景は後陣を率いて出陣した。
伊達軍の進攻に大崎勢からは抵抗らしい抵抗もなく、先陣は中新田城を猛攻撃し、本丸を残すばかりとした。ところが、そこへ春の大雪が来襲し伊達勢は攻撃を中止して兵を引き揚げようとした。ここにおいて、攻守は逆転し伊達勢は潰走する事態となった。
一方、後陣の政景軍に対しても大崎軍が襲いかかり、雪の大崎原野で政景軍は壊滅し多くの犠牲者が出た。政景は黒川月舟に使者を送り、娘婿の縁をもって苦境を救って欲しいと申し送った。これに接した月舟はにわかに憐憫を覚え、政景軍が引き揚げることを許し、政景は九死に一生を得た。こうして、伊達軍の大崎攻めは散々な敗北に終わったのである。
戦国時代の終焉
天正十六年六月、佐竹氏が仙道南口に出陣してきたことで、政宗は安達郡本宮に本陣を移した。政景は宮城郡の利府城から本宮表に参陣し、連日戦評定が行われた。このとき、政景は政宗から種々の馳走を受け、また内談の相手にされたりして、政宗から厚い信頼を受けていたことが知られる。七月、本宮付近で伊達・佐竹両軍の間で衝突があった。このとき、佐竹側には葦名氏が加わっていたため、伊達勢は苦戦を強いられたが決定的な勝敗には至らなかった。やがて、佐竹方より和睦の使者が来て、伊達と佐竹・葦名連合軍の三者和睦が成立し、政景は政宗の名代として三王山に出向し和睦を結んだ。
翌年、政宗は宿敵相馬氏を攻めるため、宇多郡駒ケ峯・新地城に出陣し、四方から総攻撃を行った。この戦いに際して政景は西を担当し、東は亘理宗元、北から田手宗実ら、南から原田宗時・泉田重光らが攻撃し、駒ケ峯・新地城は伊達軍の前に落城した。その後、政宗は軍を転じて会津の葦名氏を攻撃するため、軍を猪苗代方面に向かわせ、葦名氏と磐梯山麓の摺上原で決戦を行った。
戦いは政宗の大勝利に終わり、政宗は黒川に入城し葦名氏は滅亡した。この戦いに政景は参加しなかったが、黒川城に参上して祝詞を述べた。そして、しばらく黒川城にとどまり政宗と大崎問題を談合したようだ。そして、伊達・大崎・最上氏三者の和睦調停を成立させる働きを示し、大崎氏と和睦した政宗が月舟を処断しようとしたとき、政景は助命嘆願にこれつとめて舅月舟の一命を助けた。政景は百戦錬磨の武人であったが、人情に厚くまた外交的手腕にもすぐれた人物であった。
こうして、政宗は会津を支配下におさめ、大崎問題にも一応の結末がみえた。ところが、豊臣秀吉の小田原征伐が開始され、みずからの力をもって近隣を斬り従えるという戦国時代は終焉のときを迎えようとしていた。豊臣秀次・前田利家・浅野長政らは、政宗に小田原に参陣することを勧告してきた。このとき伊達家中は、秀吉と一戦を交えて堂々雌雄を決しようという伊達成実、小田原参陣をすべきとする片倉景綱の二つの意見に分かれたが、政宗はよく時勢を見誤らず小田原に参じたのである。小田原落城後の奥州仕置によって政宗は会津などを没収されたが、このとき、留守氏、国分氏らは政宗の家中とみなされ、独立した大名とは認められなかった。
文禄元年(1592)朝鮮の役の時、政景は肥前名護屋より渡海し釜山に上陸、各地を転戦、帰還の折り伊達姓御一門を許された。つづいて慶長元年(1596)、伊達政宗が国分盛重を攻撃した時にも政景は政宗の麾下として参戦した。この時、佐藤三郎が政景の陣所を訪ねてきて協力を申し出た。政景はこれを許し、佐藤父子の過去を許し、兵を添えて小鶴舘を守らせた。また、余目氏も許され、孫の余目土佐は村岡分流の稲沢信濃と共に寛永年代家老になっている。
北の関ヶ原の戦い
慶長五年(1600)関ヶ原の合戦のとき、上杉景勝の執政直江兼続の攻撃を受けた最上義光は苦戦に陥り、伊達政宗に応援を依頼した。政宗は政景を大将に命じて馬上五百余騎・鉄砲七百挺を第一陣として出発させた。政景は最上境の笹谷に至り、伊達勢が最上氏に加勢したことが敵陣に分かるように笹谷峠に旗指物を立て並べた。
長谷堂表に在陣していた上杉勢は、政宗の加勢に驚き退陣したため、政景らは山形城まで進んで軍評定を行った。そして、直江山城が陣を布く菅沢山と山形との間にある沼木村に出張して対陣した。やがて、関ヶ原の戦いに徳川家康が勝利したことが政宗のもとに伝えられ、政宗はこれをただちに政景らに報じた。一方、兼続も景勝から西軍敗戦の報を得て兵を引き上げようとした。これに対して政景勢は、一斉に直江軍を攻撃し、長岡山と戸上山の間で激戦の末、ついに直江軍を破り数百人を討ち取る勝利を得た。その後、伊達からの派遣軍は続々帰還していったが、政景は最上に在陣して上杉勢の残党に対処した。
関ヶ原の戦いは、秀吉死後の天下分け目の戦いで、結果は徳川家康の勝利に帰し家康の覇権が確立した。家康が上方に軍を返したとき、腹背に敵の攻撃を受ける危機にあったが、伊達政宗が家康に味方したことで上杉軍は追撃できなかった。政宗が上杉にあたったことは、家康の天下取りにおいて最大の功労となった。そして、最上氏を援けて上杉軍と戦った留守政景の演じた役割が最も大きかったことはいうまでもない。
このような政景に対して政宗の信頼も極めて厚く、政宗の治績を記した『貞山公治家記録』には、政宗と政景の親密さをうかがわせる記事が散見している。政景は居城を転々と移されたが、元和年間(1615〜23)に一ノ関城主となり二万石を治めて余生を送った。子孫は伊達一門・水沢伊達氏として続いた。・2006年2月14日
【参考資料:宮城県史/水沢市史/一関市史/仙台市史/多賀城市史 ほか】
■参考略系図
中世文書を手懸りに作成された『留守系譜』の世系によれば、家元には女子のみで男子が無かったため家業の子家広を養子に迎えて家を継がせたとある。『余目旧記』により、家業の子家広は家元の女子乙姫の夫となり家を継いだ。そして、余目氏とされていた世系も留守氏を称していたことが分かった。すなわち、家広のあと、家政と恒家の二系が並び立っていたのである。そして、恒家の系が留守氏の本流であったようだ。
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
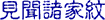

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
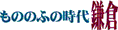

|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
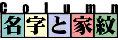

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
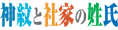
|
|

