

|
国分氏
●月星/九曜
●桓武平氏千葉氏流
|
国分氏は頼朝の奥州征伐に従った千葉介常胤の五男胤通を祖とし、胤通は下総国葛飾郡国分寺領を領して「国分」を称したことに始まる。胤通は『吾妻鏡』にはじめて登場した時から「国分」を称しており、早くより父常胤の代理として下総国衙に関わっていたと考えられる。常胤は頼朝の挙兵の初めから一貫してこれに従い、胤通をはじめ兄弟たちも頼朝からあつい信頼をうけた。
文治五年(1189)の奥州征伐に際して、常胤は海道方面の大将として出陣、戦後の論功行賞で「陸奥国五郡」を頼朝から賜った。「陸奥国五郡」とは、伊具・亘理・宇多・行方・磐城の五郡をさし、常胤はこの五郡を子息たちに分け与えた。すなわち、二男の相馬師常が行方郡、三男の武石胤盛が伊具郡・亘理郡・宇多郡、四男の大須賀胤信が磐城郡を分け与えられ、五男の胤通が宮城郡国分荘および名取郡において知行を得て同地の地頭となった。
国分荘とはいまの仙台市東部に位置する泉区の地方をいい、胤通は郷六に住したが、のちに千代城に移ったという。しかし、胤通が郷六あるいは千代城に居たという確証はいまのところ見つかっていない。胤通については『吾妻鏡』に散見し、そのあとは建長二年(1250)三月の条に「国分五郎跡」、正嘉二年(1258)三月の条に「国分五郎跡国分彦五郎」の名が見えるばかりで、宮城郡における鎌倉時代の国分氏の動向はまったく不明である。
奥州国分氏の出自考察
宮城郡における国分氏の動向が同時代の記録や史料上に現れてくるのは、南北朝時代に入ってからである。すなわち、「白河文書」のなかに残された国分淡路守に宛てた書状である。
文和二年(1353)、国分淡路守が奥州管領府から陸奥大掾沢田平次の旧領である宮城郡南目村を高部屋氏とともに石川兼光の代官に渡すべきを命ぜられたもので、当時、国分氏がこの地方で有力武士だったことを示したものである。そして、国分氏の所領は宮城郡国分郷であったことが「相馬文書」から知られる。相馬文書によれば、文和二年から十年後の貞治二年(1363)国分淡路守ならびに一族らは、その本領である国分寺郷の半分を何故か没収されて、八幡介景朝の旧領の替地として相馬胤頼に宛行われたのである。
ところで、国分淡路守が千葉常胤の子胤通を祖とする平姓国分氏であるかどうかについては、疑問が投げかけられている。ちなみに、中世の記録である「余目氏旧記」のなかに国分氏は「小山より長沼あい分かれ、なかぬまの親類」とあり、小山流藤原氏の同族と記されている。事実、国分氏が長沼氏を号したことは、宮城郡国分郷芋沢村宇那弥太大明神の棟札に「藤原朝臣長沼伊勢守政継(文正元年=1466)」「藤原朝臣長沼式部少輔宗治(天文五年=1536)」「藤原朝臣長沼郷六宗家(永禄五年=1562)」などの名が見えること。加えて、愛子村諏訪神社棟札にも「国分能登守藤原宗政」という名が見えることなどから、平姓国分氏に代わって藤姓国分氏が勢力を築いていたことは、疑いを入れないものである
とはいえ、奥州国分氏の発祥に関しては初代胤通が宮城郡に居住したというのが定説となっている。ところが、国分氏が宮城郡に下向したのは、胤通から七代を経た国分盛胤のときであったとする系図もある。そして、盛胤の子盛経は武石氏の子孫の亘理郡領主である亘理重胤と領地をめぐって争いとなり、応永十九年(1412)三月に重胤を討ち取った。重胤の子亘理胤茂は父の恨みを晴らすべく、応永二十三年九月に挙兵、国分盛経の館を急襲して盛経を討ち取り首級を父の墓前に供えたと伝えている。
亘理氏に討ち取られたという盛経の子盛忠は、宮城・名取・黒川三郡の主政に補せられ、その子盛行は東国擾乱に百戦百勝、その勢いは当たらざるものがあったと伝えられている。それを裏付ける史料があるわけではないが、盛経─盛忠のころから国分氏の威勢が拡大していったものと思われる。あるいは、盛経が戦死したことで平姓国分氏は滅亡し、藤姓国分氏がそれにとって代わったのであろうか。
国分氏の台頭
いずれにしろ、宮城郡国分荘を領した国分氏ははじめ平姓国分氏であったものが、おそらく南北朝時代に藤姓国分氏となり、さらに下って戦国時代に伊達氏から養子を迎えたことで伊達系国分氏となったものであろう。
「白河文書」に出てくる国分淡路守はすでに藤原姓と思われ、観応二年(1351)二月に、畠山氏と吉良氏とが戦った「岩切城合戦」で「かち大将の味方をいたし、其威勢いやまし」となった国分氏は、すでに藤姓国分氏であったとみて間違いないだろう。
ところで、国分氏は境を接する留守氏と宿敵の関係にあり、戦国時代の末期まで抗争を繰り返した。両者の抗争は、南北朝期に両奥州探題として奥州にあった吉良家貞と畠山高国が戦った岩切城合戦のときに始まった。すなわち、国分氏は勝大将の吉良氏に属し、留守氏は負大将の畠山氏に属して一族ほとんど全滅するという非運となった。その後、留守氏は再興されたが、両者はつねに対抗し、留守氏の内訌に乗じた国分氏が留守領を押領するということもあった。
しかし、留守氏に伊達氏から郡宗が入嗣したことで、伊達氏の力を背景とした留守氏の攻勢が目立つようになった。さらに郡宗の子藤王丸が早世したことで、ふたたび伊達氏から景宗が入って留守氏の家督を継ぐと、国分氏と留守氏とは武力衝突するようになった。天文年代(1532〜54)に入ると両者の抗争はいよいよ激しくなり、天文五・六年にはついに合戦となった。
十五世紀ころから、奥州では伊達氏が勢力を拡大し、稙宗の代になると「陸奥守護職」に任ぜられ、奥州の仕置は陸奥守護伊達稙宗が握るところとなった。その後、留守・国分両氏の抗争に稙宗が干渉したのは、陸奥守護職としての権限の発動であった。このころの国分氏の当主は宗綱(宗政ともいう)で、松森城に居たことが知られている。稙宗の調停があったとはいえ、国分氏と留守氏の抗争は繰り返され、規模・実力ともに拮抗した両者の勝敗はなかなか決まらず、同格の領主として両者が伊達氏の麾下に属するまで抗争の止むことはなかった。
天文五年(1536)、大崎氏に内訌が起り、大崎義隆は伊達稙宗に援助を申し入れ、これを承諾した稙宗は三千余騎を率いて大崎に向かった。この陣中には伊達氏の有力家臣とともに、国分宗綱と留守景宗が参陣し、大崎の乱平定に一役買っている。そして、このころには、国分氏ら奥州の諸氏は伊達氏の麾下に属していたのである。
奥州の戦乱
天文十一年(1542)、伊達稙宗と嫡男晴宗の不和から「伊達氏天文の乱」と呼ばれる一大争乱が起った。乱は伊達家中はもとより南奥州の諸大名を巻き込み、十年間にわたる大乱となった。この乱に際して国分宗綱は、田村隆顕・相馬顕胤・亘理宗隆・葛西晴胤・大崎義宣らとともに稙宗派に加担した。宿敵の留守景宗は晴宗派に加担したため、ここでも国分氏は留守氏と対立関係になった。
天文十三年十月、晴宗は留守景宗に来援を期待する旨の書状を送ったが、景宗は国分氏と戦闘中であったため、晴宗に援軍をなかなか送ることができなかった。翌年十月、晴宗は名取口に出撃して国分氏を背後から衝くことを景宗に申し送っている。天文の乱に際して、国分氏と留守氏とは一進一退の戦いを繰り返したが、おおむね国分氏が攻勢にあったようだ。やがて、乱は稙宗と晴宗が和睦し、晴宗が伊達氏の家督を継いだことで終熄した。天文二十三年(1554)、留守景宗が死去すると顕宗が留守氏を継いだが、病弱であったことから伊達氏より政景を迎えて家督を譲った。
国分氏は奥州の戦乱に際して、伊達氏と協調しながら領内の一円支配を押し進めた。そして宗綱・盛氏の時代にほぼ支配体制が形成されたようで、国分氏領内三十三郷の豪族である朴沢氏、福岡氏、萱場氏、白石氏、横沢氏、古内氏らが国分氏と縁を結んで、やがて家臣として従うようになっている。
国分氏と対立・抗争を続けてきた留守氏には伊達氏から三代にわたって養子が入り、すでに留守氏は伊達一族というべき存在となっていた。この伊達氏の入嗣政策は、国分氏にも向けられてきた。『性山公治家記録』によれば、天正五年(1577)国分盛氏が嗣子なく死んだため、晴宗五男の政重が入嗣して国分盛重と称して千代城主となったとある。しかし、国分系図を見ると盛氏には盛顕・盛廉らの男子がある。
盛氏は盛顕に家督を譲って隠居したが、盛顕は多病で子もなかったため、永禄十年(1567)に家督を弟の盛廉に譲って隠居した。ところが、元亀三年(1572)、中野氏の乱に際して討伐のため出陣した盛廉は、刈田郡において戦死してしまった。そのため、盛顕がふたたび国分氏の家政にあたったが天正六年(1578)に死去したとある。かくして、政重(盛重)が盛顕の後継ぎととなり国分氏を継承したのである。
戦国時代の終焉
国分氏の当主となった盛重は政景の弟にあたったため、これより国分氏と留守氏とは兄弟分となり、永年にわたる両者の対立関係は伊達氏を紐帯として融和したのである。しかし、この養子の一件には国分氏家中にかなり強い反対があり、また盛重の政治もよろしきを得なかったため内紛が絶えなかった。
天正十五年になると、政宗は国分氏の仕置のため盛重にしばしば使いを出しているが、家中は容易におさまらなかったようで、ついに十月、政宗は小山田筑前に国分征伐を命じている。この事態に国分盛重はみずから米沢に参上して謝罪したことで征伐には至らなかったが、盛重は家中の混乱に悩まされ続けたようだ。
天正十六年(1588)、大崎合戦のときも国分氏は政宗から大崎氏に呼応することを警戒され、盛重は米沢に蟄居状態に置かれ、家臣らもまた参戦しなかった。これは、盛重の兄で留守氏を継いだ政景が大将として出陣したのとは対照的であり、盛重の処遇はみじめなものであった。天正十八年、豊臣秀吉による小田原征伐に際しても国分氏には何の沙汰もなく、その後の「奥州仕置」でも大名として認められなかった。
一方、小田原参陣を怠った大崎・葛西氏らは、奥州仕置で所領没収となり、その処置に不満をもった大崎・葛西の旧臣らが一揆を起こした。伊達政宗は蒲生氏郷とともに一揆征伐にあたったが、政宗と氏郷との間に確執があり、それが原因となって政宗は秀吉から一揆煽動の嫌疑を受け上洛を命じられた。
このとき、名生城に籠城していた氏郷は、政宗からの人質として留守政景と伊達成実を要求した。政宗は二人が出陣中のため国分盛重を提出したが、氏郷は承知しなかったため、やむなく盛重と伊達成実とが人質となった。そして、これが盛重の政宗に対する最期の奉公となった。
国分氏の没落について、伊達氏の記録には「慶長元年(1596)三月、故ありて国分氏没落す」とあるばかりで、その理由も分からない。理由のひとつとして、留守氏の家督となった政景は政宗に忠勤を励み、政宗の意によく従った。一方、盛重は人取橋の合戦にも代官として白石・北目氏らを出しただけで、伊達の存亡を欠けた戦いにみずから出陣しなかった。当時の国分氏は留守氏とともに二万石を領する伊達家中最大の地方領主であっただけに、その兵力は伊達氏にとって少なくなかった。
とはいえ、盛重は伊達政宗の信頼を得てそれなりの処遇を受けていたようだ。しかし、朝鮮の役にも出陣せず、政宗が詰めていた京都の伏見にも赴かなかったため悪評がたった。その背景には、国分家中の盛重に対する反発があり、ついには国分氏の重臣堀江掃部が政宗に讒言したことで窮した盛重は伊達氏を出奔するに至ったのである。また、このころの伊達家中は伊達成実が出奔するなど不協和音が生じており、盛重は国分氏、伊達氏に嫌気がさし、姉の嫁ぎ先である佐竹氏を頼って出奔したのではないだろうか。
その後の国分氏
盛重には三男一女があったといい、実永と宥実は出家し、末子の重広は父没落ののち家臣に護られて成長した。成長後、古内実綱に認められて養子となり、古内平蔵と名乗った。重広は馬術に長じて名声が高くなり政宗に召出され、のちに世子忠宗の傅となった。以後、累進を重ね、寛永十三年(1636)には一万五百石を賜り国老に列し、要害の地岩沼に封ぜられた。万治元年(1658)忠宗が没すると、重広はそのあとを追って殉死したと伝えられている。
その他、国分盛氏の庶子郷六盛政は伊達家に仕え四百四十石、ついで、盛氏の五男駿河も伊達家に仕え三百石の虎間番士の家柄として続いた。盛政の系統は森田家を興し、駿河は横沢を称しそれぞれ子孫相継いだという。
ところで国分氏の家紋は、千葉一門らしく「九曜」を用いたが、ほかに「左三つ巴」も用いたと伝えている。三つ巴紋は藤原秀郷流共通の紋であり長沼氏も三つ巴を用いていたことが知られ、三つ巴紋は国分氏が平姓から藤姓へと代わったことの傍証となるのではないだろうか。・2006年2月15日
【参考資料:宮城県史/水沢市史/仙台市史/泉市誌 ほか】
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
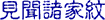

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
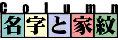

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
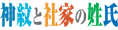

|
|

