
本庄氏
竹輪に二羽飛び雀*/桐
(桓武平氏秩父氏流)
*上杉景勝から使用を許されたという。
繁長の旗指物には「上」の字が大書されていた。 |


|
本庄氏は桓武平氏秩父氏の流れをくむ。建永元年(1206)ごろ越後小泉庄の本庄・加納の両所が地頭請所となり、平(秩父)季長の長子行長と次子為長がそれぞれ本庄と加納の地頭となった。行長の子孫がのち本庄氏を名乗り(鎌倉時代には小泉氏も称した)、為長の系統が色部氏を称した。
正応元年(1288)ごろ、本庄氏は年貢対捍の罪科で没落したといわれるが、鎌倉末から小泉(本庄)持長(系図の持長とは年代が合わない)が健在で、勢力は維持していたようだ。
戦乱への序曲
鎌倉幕府が滅び建武新政が開始された直後の建武元年(1334)、本庄持長は一族の色部長倫に攻められた。このことは、鎌倉初期に越後に入部して以来、秩父一族の宗家であった本庄氏に対して庶流の色部氏が敵対するまでに力を築いていたことをうかがわせる。一方、色部氏に攻められた本庄氏は、その後数年間は史料がなく、鳴かず飛ばずの状態にあったようだ。しかし、再起不能なまでに打ちのめされたものでもなかったようである。
越後は南北朝期に上杉氏が守護に任ぜられてから、戦国時代に至るまで上杉氏が守護職を世襲し、それを守護代の長尾氏が補佐した。そして、越後は地理的に関東と近いことから、鎌倉府の関東公方足利氏、それを補佐する関東管領上杉氏の影響を受けることが多かった。とくに十五世紀に入ると関東では「永享の乱」「結城合戦」「享徳の乱」などの戦乱が打ち続き、越後の武士たちは関東に出陣して奮戦した。
長禄三年(1459)の古河公方足利成氏と関東管領上杉房顕が戦ったとき、越後守護上杉房定は房顕を支援するために本庄氏・色部氏などの国人領主たちを率いて関東に出陣、合戦に功を上げた本庄三河守・色部弥三郎らは将軍足利義政より感状を受けている。しかし、本庄氏・色部氏らの国人領主は鎌倉武士の系譜を引くものが多く、南北朝期以後に越後に入部してきた守護上杉氏・守護代長尾氏らに対して、決して心服はしていなかった。本庄房長は延徳元年(1489)、つづいて明応二年(1493)と守護上杉房定に反抗し、守護軍の攻撃を受けている。
房定の代は本庄氏らの抵抗があったとはいえ、守護全盛の時代であった。そして、房定が死去すると房能が新守護となったが、房能の時代になると下剋上が横行する戦国乱世となった。その風潮は越後も例外にはおかず、守護代長尾能景が戦死したのちに守護代職をついだ為景は房能の養子定実を擁して房能に謀叛を起したのである。
永正四年(1507)為景は挙兵して府内の守護館を急襲、房能はあえなく敗れて関東に逃れようとするところを捕捉されて討死してしまった。「永正の乱」とよばれる長尾為景の下剋上で越後の戦国時代は幕開けとなり、その後の歴史の流れを決定した大事件であった。以後、越後は為景を支持する者と反対派とに分かれて内乱が続くことになる。
為景の台頭と挫折
為景の台頭に対して、本庄時長・色部昌長・竹復清綱ら揚北の国人領主たちはそれぞれの居城において為景・定実に反抗の兵を上げた。かれらの反抗は、府内の守護政権の動揺につけこんで行われてものであった。為景・定実はただちに中条藤資・安田長秀らに命じて各個撃破のためにまず本庄城へ押し寄せ、猛攻を加え本庄城を陥落させた。このときの戦いで時長の嫡男弥次郎が戦死している。乱はたちまちのうちに平定されたが、色部氏のみは徹底抗戦を続け、房能の兄で関東管領の上杉顕定に救援を求めた。
顕定は殺された房能の実兄で、弟の讐をうつため越後に入国したが、関東が不穏な状況にあることも手伝って目立った軍事活動はとらなかった。その後、為景に対立していた色部昌長の平林要害が落され、色部氏はもとより本庄氏も反抗を続けることができなくなり、為景方に降伏してしまった。顕定が、本腰をいれて越後に兵を入れたのは永正六年のことであった。顕定軍はさすがに精強でたちまちのうちに為景・定実は蹴散らされ、越後から越中へと落ちていった。府中に駐屯した顕定の戦後処理は苛酷なもので、越後の国人たちは顕定軍の占領地政策に不安と不満を募らせていった。永正八年(1511)、為景・定実は体勢を立て直して蒲原津に上陸すると、多くの国人らはそれに応じた。顕定は関東へ逃れようとしたが上田長尾氏が為景方に転じたため、上田庄で追撃してきた為景勢と一戦を交えたが敗れて討ち取られた。
以後、本庄氏も色部氏も為景に誓書を出すなどして、つとめて為景と事は構えていない。このころ、本庄氏の庶家にあたる鮎川氏、小川氏らが台頭してきて、宗家の本庄氏と肩を並べる存在に成長していた。まさに、時代は激動していたのである。
天文二年(1533)、上杉一族の上条定憲を中心とする旧守護勢力は為景打倒の兵を挙げた。本庄・色部氏らの揚北衆は為景の下から離れて上条方に加わった。戦乱は、長尾氏一族も上条方に加担するなどして、次第に為景方の不利へと傾いていった。さらに、為景が後楯としていた幕府の有力者細川高国が政変でたおれたことで、上条方が活気づき、いよいよ為景は四面楚歌という状況に陥った。その後、宇佐美氏率いる上条勢と為景勢とが三分一原で合戦し為景勢が勝利したが、それは攻勢の上条勢を一時的に退けたものに過ぎなかった。ついに為景は隠退を決意し、嫡子晴景に長尾家督と守護代職を譲った。そして、その年の暮れに波乱の生涯を閉じたのである(天文十一年死去とする説もある)。
ここにおいて、越後の国人たちは急速に戦争に対する熱を冷まし、本庄・色部・鮎川氏らも晴景と妥協して兵をおさめた。
打ち続く戦乱
晴景は越後の戦乱を治める力量に乏しく、国人たちとの妥協をはかり、為景に幽閉されていた定実を守護に復帰させたのである。しかし、定実には子がなかったため老齢の自分が死ねば守護の座も当然消滅することを憂いて、後継者を望むようになった。そこで白羽の矢が立てられたのが、定実の外孫にあたる伊達稙宗の子時宗丸であった。
時宗丸は揚北の有力者中条藤資の妹が稙宗の側室となって生んだ男子で、伊達家との折衝は藤資があたったため中条氏と同じ揚北衆を刺激した。すなわち、養子の件が成ると中条氏の勢力が強大化することは必然であり、他の揚北衆は一斉に猛反対の立場を示したのである。
その急先鋒となったのが本庄房長で、藤資は伊達氏の支援を得て本庄城を攻撃した。房長は鮎川・小川氏らの一族を糾合して攻撃を防ごうとした。しかし、伊達・中条連合軍の攻撃に堪えきれなくなった房長は、隣国出羽国庄内地方の大名大宝寺氏の下に逃れて陣容を立て直して伊達・中条連合軍に当たろうとした。房長は城を留守兵に守らせ、みずからは主力兵を率いて庄内に向った。このとき、一門の鮎川清長も同陣する約束になっていたが、清長は約束を破って出陣しなかった。さらに、同じ一門で実弟でもある小川長資が兄房長の留守に乗じて本庄城に攻め入り、これを乗っ取ってしまったのである。
小川氏の叛逆を大宝寺への途中で知らされた房長は、激怒して軍を返そうとしたがあまりに激しい興奮のため、急病を発して頓死してしまった。おそらく、心臓発作と思われるがまことに悲惨な最期となった。このころ、房長の室は妊娠中であったが、城内にあって小川氏の兵を防いだものの、全身に傷をおって道路に倒れていたのを鮎川氏の家臣に発見されて、付近の寺に担ぎ込まれ介抱を受けどうにか蘇生したという。そして、それから七日後に無事男子を産み落としたが、激動のために早産であったようだ。このときに生まれた男子こそが、のちに成長して謙信麾下の勇将として名を馳せる本庄繁長である。
勇将繁長の登場
その後、伊達氏内部で稙宗と嫡子晴宗との間で対立が起こり、時宗丸養子の件は立ち消えとなった。伊達父子の対立は「天文の乱」となり、南奥州諸将を巻き込む大乱となった。一方、この事態に勢いをえた黒川・色部・鮎川らの養子反対派は中条藤資を攻撃した。加えて、黒川・色部・鮎川氏らは天文の乱に際して晴宗に加担し、晴宗からその応援を感謝されている。
ところで、本庄房長が憤死してのち小川氏が本庄家中で勢力を振るい、それに鮎川氏も加担していたようだ。当然、本庄氏内部では小川氏らの横行を快しとせず繁長の成長を待つ勢力もあり、本庄氏家中は混沌としていた。その事態を収拾するため色部勝長が調停に乗り出し、鮎川清長は勝長に起請文を出し本庄氏にも誓書を出している。かくして、本庄氏内部は一応の平穏をみたものの、それは一時的なものに過ぎなかった。本庄氏の勢力を代表する者は小川長資であり、本庄氏の家臣は決して長資に心服していなかった。さらに、長資は暴虐な行動が多く、房長の忘れ形見繁長を養育する本庄盛長は、繁長に対して長資の悪事を語って聞かせたであろう。
天文二十年(1551)、十三歳になった繁長は小川長資が菩提寺である耕雲寺に詣でたとき、手勢を率いてこれを襲い、ついに憎き長資を切腹させた。このとき、鮎川清長も繁長の攻撃の対象になったようであるが、色部氏の調停によって繁長と清長は和解した。ここに、長かった本庄氏の内紛も終わりを告げ、繁長が青年武将として歴史の表舞台に登場してくることになる。
こうして、永年にわたる一族の確執を清算した繁長は、青年武将として揚北の武士団の間において重きをなすようになり、越後国内はもちろんのこと近隣諸国にまで勇名を馳せる活躍を始めるのである。このころ、長尾氏では凡庸な晴景に代わって景虎(のちの上杉謙信)が跡継ぎに立てられ、長尾氏の家督となり実権を確立した時期であった。
謙信の麾下に属す
永禄元年(1558)、景虎から繁長に動員令が下った。これに対して繁長は景虎の兵に加わったのではなく、すべて自己の領内の士卒をもって組織した一軍の大将として出陣している。この時期の本庄氏の勢力のほどがうかがえる。翌二年、景虎は二度目の上洛を果たした。この壮挙を祝って諸将が太刀を贈呈した目録『侍衆御太刀之次第』によれば、まず直太刀の衆として一門の古志長尾・桃井・三本寺の名があり、次に披露太刀の衆として諸大名の名が列記され、本庄繁長は中条藤資につぐ第二位に名が記されている。その順序は城中における各将の座席の関係によるものと考えられるので、当時の上杉家中における繁長の地位がいかに高いものであったかを端的に示したものといえよう。
永禄・元亀年間(1558〜72)は、景虎の活動が最高潮に達する時期で、関東・信濃・越中へと軍を発していた。この間、繁長も景虎に供奉して各地に転戦したことは間違いないだろう。しかし、その事実を証する史料は必ずしも十分に伝わっていない。
繁長の活躍を軍記物などから拾ってみると、永禄三年三月、景虎は越中に攻め入り富山城を陥落させ、八月には、関東に軍を進め北条氏康軍と合戦、繁長は上杉軍の先鋒として奮戦した。翌四年、景虎は小田原城を攻囲し、直後、上杉憲政から上杉名字と関東管領職を譲られ鶴岡八幡宮で関東管領就任の式を行った。ここにおいて、景虎は長尾景虎を改めて上杉政虎(以下謙信で統一)を名乗った。この間、始終繁長は謙信に供奉した。その後、謙信は越後に帰国するとただちに信濃川中島に兵を進めた。もっとも激戦となった第四回目の川中島の合戦であり、武田信玄の軍師といわれる山本勘助の「啄木鳥戦法」でも知られている戦いである。
九月十日の未明、武田軍の作戦の裏をかいた上杉軍は陣容を整えて夜の明けるのを待っていた。一方、本庄繁長・新発田長敦・色部長実・鮎川清長らの一隊二千余人は、千曲川のほとりに陣を布き海津城より来るであろう武田軍の別働隊に備えた。戦いは明け方に始まった。機先を制したのは越後軍で、甲州軍の本陣を急襲してこれを破り倉科まで武田軍を追い詰めた。越後軍は初戦の勝利によって、川中島に一休みして兵糧を使った。そこへ武田信玄の長男義信が八百ばかりの兵を率いて攻め込んできたことで、越後軍は周章狼狽し志田義時・大川高重らの諸将が討死するなど越後軍は窮地に陥った。まさに、謙信にとって痛恨の油断であった。そこへ、海津城の抑えに任じていた本庄繁長・新発田長敦・色部長実らが駆け付け、義信軍のなかに斬りこんだ。本庄氏らは義信軍に大打撃を与え、千曲川の広瀬まで追い落とした。謙信は危うく窮地を脱することができたのである。
俗説によれば、このとき謙信が義信に付け込まれたのは武功が少ないため油断したからだと繁長がそしり、謙信の不興をかったというが、これはその後繁長が謙信に対して謀反したことを理由付ける作り話に過ぎないものであろう。
繁長の謀叛
永禄十一年(1568)、本庄繁長は上杉謙信が越中に遠征しているさなかに、武田信玄からの誘いに応じて叛乱の兵をあげた。
繁長は謙信に仕えて諸処の戦陣に明け暮れたが、感状を賜るのみで領地が増えるということもなかった。さらに、長尾藤景の討伐を命じられ、藤景を討ったがそのことに対する褒賞もなかった。繁長は次第に謙信への疑心暗鬼が募り、そこを信玄がうまく突いて謀叛に誘ったものである。このころ、信玄は駿河方面への作戦を企図しており、それには越後に内乱を起こさせて謙信を釘付けにし南方進出を容易ならしめる意図があった。いいかえれば、繁長は信玄にうまく利用されたといえよう。とはいえ、繁長にしても庄内地方にも睨みをきかし、鎌倉以来の血筋を誇って謙信「何する者ぞ」といった気概ももっていたことと思われる。繁長は謀叛に先立って、同じ揚北衆で同族でもある色部氏、中条氏らに協力を求めたが、色部氏らは頭を縦に振らなかった。さらに、一族の鮎川盛長も謙信側についたため、繁長は孤立して本庄城に籠城した。
繁長は武田氏からの援助を頼りにして孤軍奮戦したが、信玄からの援助は兵糧が届いたにすぎなかった。そして、謙信が自ら兵を率いて出陣してきた。しかし、繁長は屈することなく、謙信軍に頑強に抵抗したため、謙信は本庄城を包囲したまま年を越した。
繁長は謙信軍に対してよく戦い、十二年になると乾坤一擲の夜襲をかけるなど謙信軍に抵抗を示した。さらに春になると、攻城軍諸将の間に合戦を倦む者も出始め、謙信も戦の収拾を急ぎ、ついに伊達・葦名両氏の仲介を入れた繁長は謙信に降り反乱は落着した。降った繁長は嫡子顕長を人質として府中に指し出し所領も削られたが、命だけは助けられた。謙信も繁長の剛勇と、本庄氏の軍事力を惜しんだのであろう。
この乱を通じて、自立性を維持していた揚北衆に対する謙信の統制がさらに強化された。乱後の元亀二年(1571)八月、謙信は色部氏の忠節を賞して、府内における色部氏の席次を本庄繁長の上に据えた。これによって、鎌倉以来、秩父平氏の宗家たる本庄氏と庶家色部氏の地位は逆転してしまった。
繁長の不遇と再起
乱後、繁長はほとんど表向きの席に出たり、功名手柄を現すような機会は与えられなかった。天正三年に作成された「上杉氏軍役帳」にも繁長の名は見いだせない。さらに天正五年の軍役動員名簿である「上杉家家中名字尽 手本」にも繁長の名はない。天正五年当時の謙信は四十七歳の働き盛りで、関東の混乱をおさめ、上洛して専横を極めている織田信長を討とうと悲壮な決意をしていた。そして、神に祈り、恃みとする将士の名をみずから筆をとって書き連ねたのが家中名字尽であり、そこに繁長の名がないことは謙信から股肱の将として認められていなかったことを示している。謙信治世下に繁長の活躍の舞台はなかったのである。
しかし、謙信に真正面かた反抗した繁長の名は広く世間に知れ渡っていて、降服後の不遇もまたよく知られていた。織田信長は伊達輝宗に対し繁長をふたたび謀叛せしめるよう働きかけることを画策したが、さすがに繁長は応じなかった。信玄に踊らされて、その生涯を棒にふるほどの失敗をしたことを胆に命じていたのであろう。
繁長がふたたび表舞台に登場してくるのは、天正六年三月、謙信の死後に起こった「御館の乱」においてであった。御館の乱とは、謙信の二人の養子である景勝と景虎の家督争いであり、繁長に対して景勝からただちに参陣するよう催促があり、景虎の方からも誘いがあった。このとき、繁長の嫡子顕長は春日山に謙信の人質としてあったが、景虎一党が春日山から御館に脱出したとき連れ去られ、景虎の陣営にあった。しかし、繁長はいち早く景勝派の領袖吉江信景に使者を送り、景勝派の旗幟を鮮明にした。
繁長にとって景勝・景虎のいずれにも味方をしなければならない義理はなかった。しかし、繁長も越後武士のひとりとして小田原北条氏出身の景虎よりも謙信に近い景勝に肩入れをしたものと思われる。加えて、一族の鮎川氏が景虎支持に傾いたこと、色部長真が態度をはっきりしていないことなどから、いち早く景勝に加担して立場を強化しようとしたのであろう。とはいえ、繁長は乱に際して積極的に介入することはせず、本庄城にあって鮎川氏との闘争を続けていた。翌七年、景虎方の重鎮である北条景広が戦死したことで、景勝派が優勢となり、三月、景勝軍の攻撃によって御館は陥落した。景虎は関東へ脱出をこころみたが追撃を受けて、鮫ケ尾城に逃げ込んだが城主堀江宗親の裏切りによって自刃してはてた。
その後も、景虎派の抵抗が続いたが大勢は決し、乱は景勝の勝利に終わった。景勝は御館に在城していた顕長を繁長の功に免じて許されたが、本庄氏からは廃嫡することが条件となっていた。いずれにしろ、この乱の進退によって、謙信時代に失った信頼を回復し、ふたたび揚北衆の重鎮として活躍することになった。
新発田氏の乱
その後、織田信長の越中侵攻が急になり、天正九年になると御館の乱後の恩賞に不満をもっていた新発田重家が信長に通じて反乱を起した。本庄繁長は色部長真とともに新発田に出陣し、城外の家屋を焼き払ったりしたが、重家に大きな打撃を与えるほどのものではなかった。同年六月、織田軍の進攻を阻止するため越中魚津城を守備していた上杉軍は一人残らず壮烈な戦死を遂げた。一方、信濃からは信長の武将森長可が越後に進撃を開始し、うちには新発田重家の反乱と、景勝はまさに存亡の淵に立たされていた。ところが京都本能寺で異変が起こり、織田信長は死去し、景勝は一大危機を脱出することができた。
信長後の中央政界では羽柴秀吉が台頭し、信長の事業を継承して天下統一への途をひた走り始めた。天正十一年、景勝は繁長を重用して新発田氏の抑えとした。さらに恩賞としてそれまで用いていた桐紋に代えて守護上杉氏から譲渡された「竹に飛雀」の紋を許し、古志長尾家の座敷を繁長に与えたのである。ここに繁長は謙信時代に失った席を回復したというだけではなく、上杉氏として最上の座席を与えられたことであり、それはそのまま繁長に対する景勝の篤い信頼を示すものであった。
十四年、景勝は初めての上洛を果たし秀吉に謁見したが、留守は本庄繁長にまかせ、色部氏に留守中問題が起きた場合は本庄と相談し、なかよくするように念を押している。景勝は首尾よく秀吉との親交を深め帰国したが、繁長は春日山城に参府して祝意を表している。秀吉に謁見し豊臣体制の重鎮に位置付けられた景勝は本格的に新発田氏討滅を期し、翌年九月赤谷城を落し、十月五十公野城、ついで同月末に新発田城を落して重家を斬った。ここにまったく越後国内は景勝のもとに統一されたのである。
新発田氏の乱で、もっとも景勝方の中核となって働いたのは繁長で、その功はもっとも大なるものがあった。かくして繁長は景勝政権下の重鎮として、揚北の北方に続く庄内との関係を深めていくようになる
本庄氏と庄内
戦国時代、越後に接する出羽・会津方面は、越後上杉氏と深い関係をもっていた。そして、出羽では米沢の伊達氏、山形の最上氏、大宝寺に大宝寺武藤氏がそれぞれ割拠して、互いに領国拡大をはかり、対立抗争を続けていた。このうち大宝寺氏は室町期以来、越後上杉氏の庄内進出によって、上杉氏と密接な関係にあった。天正期、大宝寺義氏は上杉謙信の力を背景として庄内地方を服属せしめていた。しかし、謙信が没すると最上氏の勢力が強大になり、庄内をめぐって鋭く対立するようになった。
天正十一年、最上義光の策謀にそそのかされた家臣の叛乱によって義氏は自害して果てた。そのあとは弟の義興が立ったが、上杉氏の援助なくしては自立できず、景勝は義興の後見として本庄繁長を起用し、繁長の子千勝丸(のちの義勝)を養子とさせた。以後、庄内は上杉氏を背景に最上氏の北進を食い止めようとする大宝寺氏と最上氏とのせめぎ合いが続き、俗に「最上・上杉の草刈場」と呼ばれた。
天正十五年、またしても最上義光は策謀をめぐらし、そのそそのかしに乗った東禅寺氏が義興に叛乱し、その鎮圧のさなかに義光の軍が庄内に侵攻、尾浦城を攻囲し義興は自殺してしまい、庄内はついに最上氏の手に落ちた。翌十六年、本庄繁長は庄内奪還をはかって兵を挙げ、最上勢と十五里ケ原で戦い壊滅的打撃を与えて庄内を取り戻した。最上義光は繁長の庄内攻撃は秀吉の私闘禁止令に違反するとして訴えたが、義勝に対して豊臣姓が与えられ、官位も受けるという形で庄内支配権は義勝に認められた。かくして、庄内は上杉氏のもとにもどった。
そして、天正十八年八月、秀吉の命を受けて景勝は庄内に入り、由利郡・仙北郡に進み、大森城に本拠をおいて検地を押し進めた。景勝の検地は九月初旬に概ねその作業を終え、中旬には秀吉から帰国の許しを得て帰国の途についた。ところが、十月、奥羽各地に土豪が中心となって一揆が蜂起した。陸奥では大崎・葛西の旧臣らが、出羽では由利・仙北・庄内三郡に一揆が広がった。いずれも在地に君臨していた地侍たちが一揆を率いて、上杉・大谷など上方勢の根拠地を襲った。
地理に通じた一揆勢はゲリラ戦をもって討伐軍を悩ましたが、結局は体制の前に敗れていった。一揆の平定後、本庄繁長と大宝寺義勝父子が大和に流罪になった。これは、繁長父子が一揆を煽動したことによるといわれ、本庄氏がそのような行動に走ったのは、検地に活躍した色部長真との対立が背景にあったといわれている。
関ヶ原の合戦
その後、上杉氏に復帰した繁長は、系図によれば、文禄元年(1592)の秀吉による朝鮮出兵に際して肥前名護屋城に在陣し、同年景勝から一万石の知行を宛行われた。慶長三年、景勝は秀吉から奥州会津に転封の命を受け、会津に入部した。繁長も本庄城を出て、奥州田村郡仙道守山城に移住し景勝から改めて一万石を賜った。その後、慶長五年に至り、奥州の諸大名への抑えとして信夫郡福島城の城番を命じられ福島城に移った。
秀吉死後、豊臣政権は徳川家康と石田三成との対立が表面化していった。そのころ国元に帰っていた景勝は家康から再三の上洛命令を受けたが無視し続けたため、慶長五年、景勝は家康によって征伐を受けることになった。この家康による会津征伐こそが、関ヶ原の合戦の引き金となったのである。同年七月、家康に呼応した伊達政宗は上杉領に兵を出し、甘粕備前守の守る白石城に攻め寄せた。不意を襲われた白石城は防戦も空しく落城し、政宗の手におちた。十月、政宗は繁長が守る福島城へ兵を進めてきた。
福島城の本庄繁長は、政宗の大軍が迫ってくるという報に接して、城に籠っていたずらに時日を移すよりは進んで出撃し、政宗軍を迎え撃とうと決心した。本庄軍の陣容は本庄勢に加えて、小田切安芸守・車丹後守らの遊軍を加えても二千人足らずの軍勢でしかなかった。これに梁川城を守備する須田長義の勢およそ六百がいた。一方の政宗軍は、政宗の本隊だけで二万人、その他遊軍や一揆勢なども加わり、総勢は本庄方の二十倍近い大軍であったと推定されている。
戦いは、摺上川の下流を渡河した伊達の屋代隊と、小田切勢との間で始まった。小田切隊は手強く戦い、緒戦は上杉軍の優勢であった。このとき、繁長の二男充長は伊達の茂庭隊の渡河を阻むため、鉄砲を乱射せしめた。しかし、少人数でもあり、何千という茂庭隊を阻止することができるはずもなく、やがて渡河した茂庭隊を正面にして奮戦した。しかし、たちまち斬り立てられて、ついには斬り死にを覚悟したとき、小島左近に諌められてようやく死地を脱した。
屋代隊を相手に戦果を挙げた小田切隊も充長隊を退けた茂庭隊が合流したことで、ついに支えきれず退却をした。そして、伊達氏の大軍は川一面に広がって渡河を開始しはじめた。このとき、上杉軍のめぼしい将士はほとんど戦死していた。もはや城下町に乱入した伊達勢を遮るものはなく、伊達勢は一丸となって福島城に殺到した。このとき、福島城の各城門は一斉に開かれて、城兵は繁長の命令一下、いずれも決死の覚悟で伊達勢の密集部隊のなかに突入した。この思い掛けない勇敢な出撃に出鼻をくじかれた伊達勢はたちまち多くの戦死者を出した。しかも、混戦のなかで命令も徹底せず、応援に駆け付ける者も進退が自由にならない状況を呈した。
政宗軍を撃破する
このころ、須田長義を将とする梁川城兵は政宗が梁川城をまっ先に襲うであろうと信じ、油断なく備えを整えていた。、ところが、伊達の大部隊は桑折方面から福島に向かったという情報を得た。長義はただちに出動を命じ、阿武隈川を渡って伊達勢の跡を追った。そして、前田・桑折で伊達軍の小荷駄隊に追い付き、これをたちまち蹴散らし、摺上川を渡って急追し、松川北岸に至って渡河を終えていない伊達軍を捕捉し伊達軍に襲い掛かった。渡河の途中で背後から追撃を受けた伊達勢はたちまち大損害を受けて川中に追い込まれ、ほとんど壊滅した。長義はこれより先、早打ちで来援を福島城に告げていた。
この報に勢いをえた福島勢は、一層、奮い立って伊達勢を突きまくった。一方、すでに浮き足立っていた伊達勢は前後から挟撃を受けて、大混乱に陥った。これをみてとった繁長が中央本陣に向かって集中攻撃をかけたことで、ついに伊達軍は総崩れとなり、無数の屍体を遺して退去した。一方、福島勢は追い討ちをかけ、一齋道二は政宗の本陣深く斬り込み、政宗に二太刀まで斬り付けたが、馬上の政宗は辛うじて難を逃れたといわれる。こうして、繁長は二十倍もの戦力の開きを克服して、伊達軍に完勝したのであった。この戦いにおける両軍の戦死者の数は詳らかではないが、それは莫大なもので、とくに伊達勢の死傷者は甚大であったことは間違いないだろう。
繁長の指揮した上杉勢は伊達勢に勝利したとはいえ、関ヶ原の合戦に西軍が敗れたことで、景勝は会津百二十万石を没収され、改めて米沢三十万石に封じられた。このとき、本庄繁長も米沢に移住し、三千三百石を給されたという。そして、慶長十年、七十五歳を一期として死去した。戦乱の時代を駆け抜けた剛将繁長の死をもって本庄氏の戦国も終わったといえよう。
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
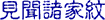
 そのすべての家紋画像をご覧ください!
そのすべての家紋画像をご覧ください!
|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
日本各地に割拠した群雄たちが覇を競いあった戦国時代、
小さな抗争はやがて全国統一への戦いへと連鎖していった。
その足跡を各地の戦国史から探る…
|
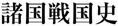
|

丹波
・播磨
・備前/備中/美作
・鎮西
・常陸
|
安逸を貪った公家に代わって武家政権を樹立した源頼朝、
鎌倉時代は東国武士の名字・家紋が
全国に広まった時代でもあった。
|
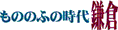

|
2010年の大河ドラマは「龍馬伝」である。龍馬をはじめとした幕末の志士たちの家紋と逸話を探る…。
|
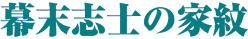
 これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
これでドラマをもっと楽しめる…ゼヨ!
|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
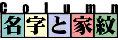

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

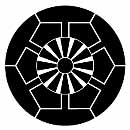
|
日本には八百万の神々がましまし、数多の神社がある。
それぞれの神社には神紋があり、神を祭祀してきた神職家がある。
|
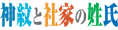

|
|

