
新発田氏
三つ星*
(宇多源氏佐々木氏加地氏流)
佐々木氏一族として目結を使用したか。
米沢上杉まつりの際、掲げられている
家臣団の幟のうち新発田守敦の幟には
隅立四つ目結が描かれている。 |
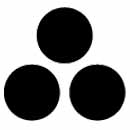
|
新発田氏は、宇多源氏佐々木氏の流れである。佐々木氏は、頼朝の挙兵に初めから加わり、鎌倉幕府が成立すると諸国の守護・地頭に任じられた。越後国加治荘は佐々木盛綱が与えられ、この盛綱の子孫が越後に分立、嫡流は加治氏を称し佐々木一族は越後に繁衍とした。
越後に土着する
南北朝初期、越後佐々木一族は足利方に属し、越後守護として上杉氏が入部してくるまで、加地近江守景綱は大将として色部氏や水原氏を指揮して南朝方と戦った。その後に続く、南北朝の内乱期は全国的傾向として、一族が分裂して戦う事象が多く見られたが、佐々木氏も例外ではなかった。しかし、この間の佐々木一族の動向は伝来文書などが失われたこともあって詳らかにはできない。
やがて、南北朝の内乱が終熄すると、越後は守護上杉氏と守護代長尾氏による国内統治が進められた。とはいえ、守護は京都にあることが多く、実際の越後統治は守護代長尾氏に負うところが大きかった。
在地で政治を取り仕切る長尾氏は次第に守護をしのぐ勢いを見せるようになり、これに幕府・鎌倉府の対立が重なって、長尾氏と守護上杉氏とは対立関係になった。応永末年(1421〜27)になると、守護上杉氏=幕府と守護代長尾氏の対立は武力抗争に発展し、越後を二分する「応永の乱」と呼ばれ内乱となった。乱の結果は、守護方の勝利に終わり、国人のなかから守護の被官となった者がでたように、守護の国人掌握がいっそう進み上杉氏の守護領国制支配が強化されたのであった。
この応永の内乱に参加した中条房資が残した記録に「加地・新発田・白川之面々」「加地・新発田面々」というふうに、佐々木加地氏のなかから、加地氏とならんで新発田氏が歴史の表面に現われてきたことを伝える記述が散見している。佐々木氏一族が雌伏のときを脱して、国人領主として台頭してきたのである。とはいえ、国人領主制を展開しはじめたころの加地氏・新発田氏の系譜関係は十分に解明できない。後代になってつくられた新発田系図、竹俣系図などによってみても、よく分からないのである。ただ、新発田氏は時秀の系統をひき、竹俣氏は義綱を始祖とすると伝えているのみである。
謙信に仕える
戦国時代になると、新発田氏は惣領家加地氏をしのぐ勢いを示し、阿賀野川以北の国人領主のなかで、長尾為景と対抗する最も独立性の強い存在にまで成長していた。享禄三年(1530)上杉氏の一族上条定憲が長尾為景に対して兵を挙げた「上条の乱」で、新発田伯耆守綱貞は、五十公野景家、加地春綱、竹俣昌綱らとともに上条方に与して長尾為景と戦った。しかも、綱貞は反為景派の指導的役割も担ったようだ。
この乱は、天文五年(1536)まで、足掛け七年にわたって続き、上条方は次第に為景方を追い詰めていった。 その後、為景は家督を晴景に譲って隠居した。とはいえ、越後国内の争乱は断続的に続き、病弱でもあった晴景は、天文十七年(1548)弟の景虎(のちの謙信)に家督を譲った。天文二十年、景虎は上田の長尾政景を降し、上・中越地域は景虎の平定するところとなった。
ここに至って、下越の諸国人領主たちも謙信に従うようになり所領を安堵されて、上杉氏の家臣として把握されることになる。こうして、謙信に仕えるようになった新発田長敦は、軍政両面において頭角をあらわした。永禄二年(1559)謙信が上洛して将軍足利義輝に拝謁し帰国したとき、越後・信濃・関東の諸将は謙信の壮挙を祝賀して太刀を献じたが、新発田長敦も竹俣慶綱・加治彦次郎らの佐々木一族も太刀を献じている。
永禄七年、新発田長敦は春日山城門番をつとめ、永禄十一年(1568)武田氏の軍が信州長沼に進出したとき、謙信の命を受けて、長敦は一族の五十公野氏らとともに信州飯山に出陣している、その後、内政・外交も担当するようになり、謙信政権内で重要な地位を占める家臣となっていった。
当時の新発田氏の軍事力を知るものとして、天正三年(1575)の『上杉軍役帳』によれば新発田長敦軍役数は百九十四とある。これは同帳で九位に当たり、宗家の加治彦次郎や一族の五十公野右衛門尉を上回り、揚北衆では色部氏に継ぐ第二位であった。阿賀野川以北において、佐々木一族は本庄一族につぐ勢力を有していた。
謙信の死と御館の乱
天正六年三月十三日、謙信は関東出陣を目前に急逝した。独身だった謙信には子が無く、生前、景勝と景虎の養子を迎えていたが、そのいずれをも正式に後継者として指名していなかったため、家督争いが起こった。これを「御館の乱」という。
この乱に、上杉景信・山本寺定長らの旧守護上杉一門・長尾一門らは景虎に味方した。旗本は景勝方と景虎方に分裂した。すなわち、景勝方には樋口兼続・山吉・小国らの譜代衆が属し、景虎方には本庄秀綱・北条高広ら謙信時代に権力の座にあった者たちであった。このことは、御館の乱が景勝の旗本と謙信の旗本の抗争も内包していたことを示している。
この乱に際して、上・中・下越の国人領主のほとんどが景勝に味方した。新発田長敦も景勝方に加担して揚北の国衆の重鎮としてこれを結集し、景勝政権の樹立のため内政・外交に手腕を発揮した。とくに、武田勝頼との和平交渉は長敦の尽力に負うところが大きかった。さらに一族の竹俣慶綱や、弟で五十公野氏を継いでいた重家らが軍事的に活躍し、とくに重家の活躍は目覚ましかった。
御館の乱は、景虎を支援する実家の北条氏や、会津の葦名・甲斐の武田ら国外の応援もあり、さらに、本庄秀綱の先制攻撃や、すぐれた外交手腕などもあって大局的には景虎が有利と思われた。その局面を打開して景勝有利に導いたのは、新発田長敦らが担当した武田勝頼との和議の成功が大きかった。天正七年正月、積雪のために北条軍が越後に侵入できないうちに景虎を攻め滅ぼす計画をたてた景勝方は、御館に攻勢を続け、ついに三月になると御縦は陥落、景虎は城を脱出して関東に逃れようとした。しかし、景勝軍の追撃を受けて鮫尾城に逃れたが、城主堀江宗親が景勝方に転じたため万事窮した景虎は自害して果てた。こうして、乱は景勝の勝利に終わり、景勝が上杉氏の家督を継承した。
ところが、乱に活躍した重家らは論功行賞から外された。軍奉行の安田顕元はこれを諌めて切腹したが、結果として重家らに恩賞は与えられなかった。このことは、景勝が、戦国大名として成長するために自らの譜代の部将・旗本たちを遇し、国人衆とよばれる外様の武将たちを遇さなかった結果であった。そのようななか、新発田長敦は天正七年(1579)に病死した。長敦の跡は弟の重家が五十公野家から実家新発田に戻って継いだ。『越後治乱記』によれば、これは景勝が重家の軍功に報いたものと解釈している。しかし、重家の恩賞に対する不満は、新発田の名跡の継承を許されたくらいでは満たされず、いつしか謀反の道へと進んでゆくことになる。そして、天正九年に入ると重家は新潟津の沖の口を押領し、織田信長と連絡をとりあうに至った。
景家の反乱
重家の謀反に対して、景勝は思いきった手を打てなかった。それというのも、天正十年に入ると織田信長軍の越中進撃はさらに急となり、景勝としては全力を投じてもなお力が足りない状況だったからである。さらに三月になると、信長は武田勝頼を天目山に滅ぼし、信濃路、三国峠からも越後に進撃を開始した。これに呼応して重家は、西蒲原郡の木場城攻撃を開始するなど、行動を活発にした。
上杉方は信州方面からの信長軍の侵攻に対して防戦につとめたが、敵するべくもなく戦線を引き上げるほかなかった。このような景勝の窮境は、重家にとっては好機到来であった。重家は景勝の軍が春日山防衛に回されている留守をねらって、篠岡・水原・下条の諸城に攻撃をしかけた。
このころの景勝の心境を示した書状が残されている、それは常陸の佐竹義重に宛てたもので、景勝が死を決しての遺書とも言われている。情勢が逼迫していることを景勝は自覚していたのである。景勝の窮状はその後さらに切迫した。越中の魚津城は落城寸前となり、関東口からは滝川一益が乱入する勢を示し、信州口では森長可が越後に乱入し、関山、二本木などに進出して放火した。これをみた会津の芦名盛隆は、いままでの中立の姿勢を捨て信長に忠誠を尽くすことを約束した。もはや、景勝に残された途は、春日山城での自害しか残されていなかった。
ところが、ここに奇跡が生じた。織田信長が本能寺で、その部将明智光秀によって殺害されたのである。これを聞いた信長の部将たちは、皆とるものとりあえず、先を争って京都あるいは自領へと引き上げて行った。
景勝にとっては、ひたひたと取り巻いていた信長の大軍が突然姿を消し、一気に生気を取り戻すことができた。おそらく、当初は狐につつまれた思いであっただろう。一方、重家にとっても事態は晴天の霹靂であった。景勝打倒の日も目前と思われていたのが、逆に、自らが滅亡に追い込まれる事態となったのである。
景勝との死闘
本能寺の変後、景勝は重家討伐は後にして、信州や越中の回復に力を注ぎ、自らも出馬するなどして北信濃四郡の確保に成功した。そして、信州から戻ると、重家を一もみに平定しようと、直ちに軍を下越に発した。そして、重家軍に対して優勢に戦を進めた。しかし、この頃景勝の兵は戦に倦み、かつ戦が有利に進んでいることから、軍規に乱れがみえ、あと一押しができず景勝は兵をまとめて撤収をはじめた。これをみた重家は、勝手知った土地の地形を利用して、景勝軍の背後から攻撃をしかけた。これに対して景勝軍は一筋道という地形に阻まれて、殿の軍が重家軍に散々に討たれるのをただ見ているだけという状況に陥った。
この戦で重家は景勝の部将菅名但馬守・水原満家・上野九兵衛など名のある大将をつぎつぎに討ちとり、刈羽城将の安田能元に重傷を負わせ、景勝を今一歩というところまで追い詰めた。さすがに景勝は馬を返して重家軍と戦い重家軍を追い返したが、この「放生橋の戦」と呼ばれる合戦は新発田重家方の会心の勝利であった。
信長亡きあとの中央政界は、その跡目を巡って羽柴秀吉と柴田勝家とが反目していた。そして、ついに両者は決裂し賤ケ岳の合戦へと事態は動いていった。秀吉は景勝に書を送り、勝家の背後を襲ったら能登・越中は景勝に与えようと言ってきた。しかし、この好機を景勝は捕えることができなかった。すなわち、関東との国境方面からは北条氏政が策動しているとの使者が来る。信州方面は、徳川家康が北上を目指したことで信州衆に動揺が生じていた。そこで、景勝は秀吉から求められていた越中・能登方面への出馬をとりやめ、信州に自ら出馬して家康に備えるに至ったのである。しかし、景勝のこの行動は秀吉の怒りをかった。
秀吉は勝家を北の庄城に滅ぼすと、早速書を送り、景勝の違約を攻め、越中・能登を与える約束を取り消し、景勝の覚悟を迫った。さらに、佐々成政に「成政が景勝の秀吉への服属をすすめ、それが成功したならば景勝は成政の家臣にしてやろう。もし景勝が従わなかったら、兵を出して征服し、越後国は成政にまかせる」と述べた書状を送っている。
これを受けた成政は、景勝に対しての支配を速やかにするために新発田重家に使者を送り、「すみやかに使者を秀吉に送ってほしい」と申し送っている。成政は重家を越後の有力な独立大名として秀吉に承認してもらい、あわせて成政とともに景勝を討伐すべき命令をもらおうとしたのであろう。しかし、景勝も秀吉に使者を送り、誓詞を呈上し、秀吉もこれを了解している。
かくして、天正十一年七月、景勝は新発田重家攻めの軍を発した。そして、八月景勝と重家の軍は八幡において大会戦となった。戦は数時間を経ても勝敗が決せず、景勝は自ら馬に乗って決戦場にかけつけ、旗本の侍どもはその馬前で槍をふるって奮戦し、この勢をもって景勝方は勝利をおさめることができた。しかし景勝は、佐々成政に攻められた越中の諸将から救援の声がしきりとなり、最終的な勝利をおさめることなく、このときも春日山城に帰っていった。
時代の変転
天正十三年(1585)五月、景勝は今度こそ重家を滅ぼそうと春日山城を出発した。しかし、中央情勢は、景勝に重家討伐に専念する余裕を与えなかった。すなわち、秀吉は長久手の戦いに家康に味方した佐々成政および小田原にあって服従しない北条氏攻撃を計画し、景勝に協力を求めたのである。そこで、景勝は重家攻めを中止し、秀吉の佐々成政攻めを応援した。同年八月、秀吉は大軍を率いて越中に侵攻しついに成政は降伏した。このことは、新発田重家にとって、佐々成政との共同作戦をもって景勝を打倒する作戦が潰え去ったことになる。ここに至って、重家は景勝によって滅ぼされる運命しか残っていないと思われた。
ところが、秀吉政権内に重家助命を主張する者がいた。そこで、秀吉は使者を越後に下した。また、このころ秀吉は関白に任じられ、天下統一者としての名実を備え、もはや、その承認なくしては軍事行動を起こすことは許されなくなっていた。言い換えれば、重家の生死は秀吉の手中に握られ、秀吉政権は重家を許そうと考えたのである。さて、秀吉の使者による斡旋は景勝と重家の両者の間に行われたようで、それぞれから返答があった。重家の返答の内容は不明だが、景勝からの返答は「重家がいる限り、その猛毒のために、平和な生活を送ることはむつかしい。自主的に講和をする意志はない」というものであった。重家の返答もおそらく、降伏や妥協の余地はないというものであったろう。こうして、秀吉斡旋の期間中も両軍の小競り合いが続いた。
天正十四年(1586)五月、景勝は下越の諸将に留守を命じて上洛し、六月、大坂城で秀吉に謁見をたまわった。そして、七月に府内に帰着し、同月、本庄と色部に新発田攻めに参加することを命じた。 こうして、八月、景勝は府内を出発し、阿賀野川のほとり笹部に布陣した。この戦陣には、秀吉から木村吉清が軍監として付けられていた。このことは、重家は秀吉の天下統一の障害物と規定され、その平定が命じられたということになる。言い換えれば、これまでの景勝による重家討伐は、かつての戦国大名の領土拡張戦と呼べるものであったが、いまや、秀吉の天下統一戦の一環を形成するものとなったのである。
ただし、このときの重家攻めは降伏させ、景勝と融和させることにあり、殺害までは考えていなかったようだ。おそらく、秀吉は重家の一命を助け、北条攻めに使おうと考えていたようだ。したがって景家が、この戦に巧みな処世をし、北条攻めに手柄を立てれば、恩賞として少なくとも本領安堵、場合によっては小大名に取り立てられることもあったであろう。しかし、十月家康が上洛して秀吉に臣礼を尽くし、秀吉が家康に関東のことをゆだねたとき、新発田重家の運命は決した。
すなわち、秀吉は景勝に対して「北条攻めについては徳川家康に万事一任することにしたので、自らは関東へ軍を出すことを中止した。だからもはや専心、新発田重家を討ち果たすように努力せよ」という事態になったのである。
かくして景勝は重家討伐の大義名分を得ただけでなく、一刻もはやく重家を討ち滅ぼすべき責任を負わされたのであった。天正十五年四月、兵を進発すると水原城を陥れた。このときは、会津の芦名義広がひそかに援兵と弾薬を重家に送っていることが分かり、それに備えるために兵を返した。そして、八月、あらためて軍を発し、五十公野城下に火を放ち、九月、新発田城を攻撃、さらに加治城を陥れた。ついで、赤谷城を攻め落とし多数の会津兵を殺害して芦名方の重家支援ルートを断った。そして十月、ふたたび五十公野城を攻めて落し、二十五日新発田城を攻め落として憎い重家の首をはねた。
新発田重家の死
重家は、武勇の誉れが高く、江戸時代になって編纂された軍記物は、筆を尽くしてその最後をたたえた。その筆致は文飾に過ぎるとはいえ、当時の重家観を示すものであろう。
元禄二年(1693)ごろに成立した『管窺武鑑』によれば、その最後は、五十公野城が落ち、新発田城の搦手も破られ、本丸に退いた重家主従はおびえた気配もなく、軍令は行き届き、寄手に油断があると城内から突いて出るなど意気盛んであった。さらに城は縄張り堅固であり、堀は広く深く寄手もせめあぐんだ。景勝は部隊を視察のうえ、「本丸は自分が旗本をもって踏みつぶすから諸将は見物しておれ」と宣言した。
これを聞いた藤田能登守は御大将にそのようなことをさせるのは滅相もないと、真っ先に堀に飛び込み重家方の囲みにぶつかっていった。そして、ついに塀を踏み破り、武者走りの土手の線を突き破り、奥へ奥へと突き進んだ。このとき、重家は太刀を抜いて横たえ、床几に腰掛け、左右に屈強の武者十騎ばかりを従えて広庭に備えていた。そこに藤田能登守が突っかかり、重家は太刀を捨てて直槍を取ってこれに応じた。双方死力を尽くして渡り合ったがついに重家は深傷を負い、奥へ引入り火を懸けた。ここにいたって重家に最後まで従った家来たちは、腹を切る者、あるいは斬死する者、炎中に入る者など、一人も残らず討死した。
重家方の働きはまことに剛強無類で、上杉方も賞賛を惜しまぬ見事なものであったと記されている。いずれにしろ、上杉景勝に対して前後六年間も抵抗を続けた新発田重家は、ここに滅亡した。重家には、幾多のチャンスがあった。しかし、そのいずれも手中にすることはできず、ついに景勝の前に滅ぼされる運命となった。このことは、重家が古い部類に属した武将であったためともいえよう。かれが新しい発想の武将であったならば、幾多のチャンスを決して取り逃すことはなかったように思えるのである。
また、重家の抵抗に対して、その撃滅に景勝が六年の歳月を要したことは、戦国末期から豊臣時代へと時代が転換してゆく時間の流れと軌を一にしたものであった。こうして戦国の豪傑が一人、歴史の彼方に消えていった。
■参考略系図
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
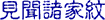

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
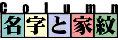
|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
約12万あるといわれる日本の名字、
その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。
|

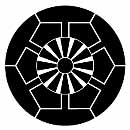
|
|

