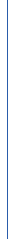
|

■
戦国山城を歩く
土佐藩祖山内一豊ゆかりの三宮城
 摂津池田から丹波阿篠山を経て綾部に通じる国道173号線の福知山を綾部方面に走っていくと、
左手先鋒に「山内一豊ゆかりの城-三之宮城跡」というカンバンがあらわれる。
土佐二十万石の藩祖となった山内一豊ゆかりの城が丹波の山奥にある…?、その意外さに
驚かれる人も多いのではなかろうか。
摂津池田から丹波阿篠山を経て綾部に通じる国道173号線の福知山を綾部方面に走っていくと、
左手先鋒に「山内一豊ゆかりの城-三之宮城跡」というカンバンがあらわれる。
土佐二十万石の藩祖となった山内一豊ゆかりの城が丹波の山奥にある…?、その意外さに
驚かれる人も多いのではなかろうか。
城址は山上の主郭を中心に、京都方面に伸びる尾根に腰曲輪を築き、登り道の要所に竪堀が落とされ、
驚くほど大きな井戸跡が残っている。主郭の北西尾根には堀切が切られ、そのまま山腹に竪堀として落ちている。
北西にある不断寺との間は尾根続きであったものが、現在、国道173号線が通じ旧態は損なわれている。
三ノ宮城への登り口は、城址南にある三宮小学校側裏手の公園の片隅に登り口のカンバンがあり、
そこから山上の主郭までは十分くらいで登るころができる。北方の不断寺側ヵら尾根越しに、
小学校東方山腹の忠魂碑からも山道が通じているが、小学校裏からのコースが無難だろう。
・国道173号線より三宮城址を見る
|





|
小学校裏手の登り口 ・ 竹薮の中の堀状地形 ・ 山腹の曲輪 ・ 竪堀を見上げる ・ 井戸址、大きい!
|
|
三ノ宮城s下には綾部に通じる街道が南北に走り、船井郡と天田郡とを繋ぐ道が東西に走る交通の要衝であった。山内氏は
三ノ宮を本城として城址南方の三ノ宮交差点を隔てた山上にも三ノ宮東城を築き、
両城が連携して城下を通じる街道を扼していた。城史の詳細は不明というしかないが、主郭には
城郭の概要と山内氏の簡単な由来が記されたカンバンが立てられている。しかし、歴史に関しては、
付記された系図とともに、そのままには受け取れないものである。
|





|
曲輪手前の竪堀 ・ 南曲輪 ・ 国道173号線方面を見る ・ 主郭下の腰曲輪 ・ 主郭の城址標の山内氏家紋
|






|
西尾根より堀切越しに主郭を見る ・ 堀切から伸びた竪堀 ・ 主郭から越し曲輪を見下ろす ・ 山麓の山内家 ・ 不断寺墓地の山内氏墓石に刻まれた家紋
|
……………
 さて、三ノ宮城が先祖の地ともいわれる山内一豊は尾張に生まれ、父盛豊が戦史死したのち流浪、
織田信長、ついで豊臣秀吉に仕えて順調に出世街道を歩んだ。そして、関が原合戦のとき
徳川家康に属し、戦後、土佐一国の国主となった戦国時代でも稀な幸運の持ち主である。
一豊の山内氏は藤原秀郷の後裔を称しているがその出自や系図などは諸説があり不明なところが多い。
さて、三ノ宮城が先祖の地ともいわれる山内一豊は尾張に生まれ、父盛豊が戦史死したのち流浪、
織田信長、ついで豊臣秀吉に仕えて順調に出世街道を歩んだ。そして、関が原合戦のとき
徳川家康に属し、戦後、土佐一国の国主となった戦国時代でも稀な幸運の持ち主である。
一豊の山内氏は藤原秀郷の後裔を称しているがその出自や系図などは諸説があり不明なところが多い。
諸説あるなかで有力視されているのが丹波出自説で、『丹波志』などによれば一豊の先祖は足利将軍家に仕え、
一豊の祖父久豊は政争に敗れた将軍義晴とともに流浪、
ついには尾張に流れて岩倉織田氏に仕え家老になったという。
久豊の去った丹波三ノ宮には一族の山内和泉守が残り、和泉守が病没したのち子孫は三ノ宮において帰農、
いまも子孫を称する旧家があり丹波一帯には山内姓が存在している。
一豊の山内氏が果たして丹波三ノ宮城から出たか否かはわからないが、三ノ宮城があり、山内名字が残り、
山内姓の家では土佐山内家と同じ「細三つ柏」の紋を使用していることは紛れもない現実のことである。
・主郭案内板に描かれた縄張図
|
|
[ 山内氏 ]

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
| ……
|
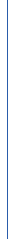
|

