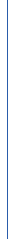
|

■
戦国山城を歩く
山上に見事な石垣、須知城
 須知城が記録にあらわれるのは、南北朝時代の観応三年(1352)のことで南朝方に属していたらしい。室町時代の丹波守護は、幕府管領職を務める細川京兆家が世襲し、細川氏は守護代を送って丹波の支配にあたった。守護代の支配は苛酷なものであったようで、延徳二十一年(1489)、船井郡を中心に大規模な国人一揆が蜂起した。一揆の中心的存在となったのが須知氏で、
知城に立て籠もって討伐軍に抵抗した。
須知城が記録にあらわれるのは、南北朝時代の観応三年(1352)のことで南朝方に属していたらしい。室町時代の丹波守護は、幕府管領職を務める細川京兆家が世襲し、細川氏は守護代を送って丹波の支配にあたった。守護代の支配は苛酷なものであったようで、延徳二十一年(1489)、船井郡を中心に大規模な国人一揆が蜂起した。一揆の中心的存在となったのが須知氏で、
知城に立て籠もって討伐軍に抵抗した。
一揆は一旦制圧されたが、翌二年、ふたたび須知城に籠城して蜂起。抵抗は四年まで続き、細川政元みずからが出馬して一揆は制圧された。このとき、須知氏をはじめ荻野・久下氏らは壊滅的損害を受け、家伝の文書や記録なども失われてしまった。その後、須知氏は再起を図り、戦国末期の信長の丹波攻めには明智光秀に協力している。しかし、須知元秀が八木城攻めに負った傷がもとで死去すると、何故か光秀に攻められ残った須知一族も四散してしまった。須知城は光秀によって改修され、いまに残るように石垣を多用した城に再生されたという。須知には須知氏の菩提寺であった玉雲寺、
須知大宮と称された能満神社、名勝として勇名な琴滝などの見どころも多い。
・明石方面より城址を見る
|






|
殿屋敷の居館遺構? 城址への分岐点 尾根のしっかりした山道 城址西端の切岸 寺院跡ともいう西の曲輪
|





|
西曲輪の腰曲輪 三の曲輪の切岸 三の曲輪へ 三の曲輪と二の曲輪を隔つ石垣 二の曲輪虎口の石垣
|





|
二の曲輪の武者走り 主郭の石垣 主郭の虎口 主郭の土塁 野面積の石垣
|





|
見事な大石垣 堀切を越えて東曲輪へ 切岸と上り土塁 囲み土塁 切岸と曲輪
|





|
東曲輪土塁 集落を見下ろす 大石垣下の堀切 段曲輪を見る 登山道に置かれたチラシ
|
須知界隈を歩く






|
須知氏が建立した玉雲寺山門・庫裏 名勝-琴滝 琴滝近くに祀られる中世五輪塔群 須地氏ゆかりの能満神社
|
|


|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
| ……
|
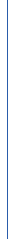
|



