


・信濃小笠原氏・信濃高梨氏・信濃諏訪氏・信濃村上氏・上州長野氏
|

信濃小笠原氏

鎌倉時代以来の信濃守護。天文十七年、信玄が上田原で村上義清に敗れると、勢いに乗じて村上義清、小笠原長時らの反武田勢力は、武田方の支配下にある諏訪に侵入した。結果は、諏訪の地下人の反撃にあって、長時は負傷し退却している。
天文十九年、信玄は小笠原氏の本拠林城に攻めかかった。抗戦むなしく長時は村上義清を頼って落ちていった。
そして幾度か失地回復を企てたがいずれも敗れて、ついに天正二十二年信濃桔梗原の合戦に敗れて没落。


信濃高梨氏

国境を接した越後の長尾氏と密接な関係をもっていた。関東管領上杉顕定が長尾為景を攻めると、高梨政盛は
外孫にあたる為景に味方して
顕定を討つなど、高梨氏の全盛時代を築いた。
政盛の孫政頼の代になると、武田信玄の勢力が北信濃にも及んでくるようになり、ついに信濃の所領を維持できなくなって、小笠原氏・村上氏らと越後の上杉謙信を頼って退却している。永禄四年の川中島の戦いには、上杉軍の先陣として、秀政・頼親ら高梨一族は活躍している。


信濃諏訪氏

諏訪政満の子頼満のころから戦国大名化していった。頼満は下社の金刺氏を滅ぼし、諏訪地方に領国制を展開、対には甲斐の武田信虎と争うまでに成長した。諏訪と武田は講和を結び、信虎の娘が頼満の孫頼重に嫁したのである。しかし、頼満の死後、信虎の子信玄と頼重は対立、ついには武田氏によって滅ぼされてしまった。
諏訪氏はその後、頼重の叔父満隣の子頼忠によって再興された。頼忠は家康に仕え、関ヶ原の合戦後、その子頼水が諏訪氏の本貫地高島二万七千石を領した。


信濃村上氏

村上顕国(頼衝)の子が義清で、父祖以来の信濃国埴科郡坂城の葛尾城を根拠地とし、北信濃四郡を制圧し、天文十年には武田信虎としめしあわせて小県郡の海野氏を追い、北信に勢力を振るった。
その後、信濃に進出してきた武田信玄を上田原に破ったが、ついに天文十二年居城の葛尾城を失い、越後の上杉謙信のもとに走り復領を依頼した。これがひとつの原因となり、信玄と謙信による川中島の戦いが繰り広げられることになったが、義清の願いは達せられなかった。


上州長野氏

長野憲業の子業政は、関東管領上杉憲政に仕え、憲政が北条氏康と戦い平井城から退去すると、管領再興を名分とし、北条・武田氏の侵攻に対抗するため西上野の武士たちを結集し、居城箕輪城にちなみ箕輪衆と称した。
業政は永禄四年に没し、その子業盛が十四歳で家督を継いだ。しかし、信玄の西上野侵攻は激しくなり、同年十一月小幡氏は武田氏に降り、箕輪城を中心とした一揆の一角が破られた。永禄九年九月、武田勢の攻撃によって業盛の奮戦むなしくついには自害し箕輪城は落城、長野氏は滅亡した。

|
|


|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
どこの家にも必ずある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
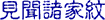
 そのすべての家紋画像をご覧ください!
そのすべての家紋画像をご覧ください!
|
|



