

|
浅利氏
●十本骨扇/雁金
●清和源氏武田氏流
|
浅利氏は、甲斐源氏の一族浅利義成が甲斐国青島荘浅利郷に居住し、浅利氏を称したのに始まる。浅利氏は浅利郷を本貫の地とするが、文治五年(1189)奥羽合戦ののち、浅利遠義は源頼朝から陸奥国比内地方の地頭職を宛行われた。このとき、秋田郡に橘氏、鹿角郡に成田氏、雄勝郡に小野寺氏、平鹿郡に平賀氏が地頭職を与えられている。
また、『承久軍記』によれば、承久三年(1221)浅利太郎知義が東山道より京都を目指したことが知れる。さらに、太郎は嘉禄二年(1227)若宮祥師公暁を謀殺したと『吾妻鏡』にみえる。その後『奥南落穂集』に「知義下向、鹿角ニ住シ三代浅利太郎義邦トイフ」と記されている。浅利氏が比内地方に定着した時期は明かではないが、おそらく、はじめのうちは代官支配であり、鎌倉後期に庶流浅利氏が比内に移住したものと思われる。
南北朝から室町期の動向
建武元年(1334)、北畠顕家は南部師行に鹿角・比内を給付した。同年の『津軽降人交名注進状』に浅利六郎四郎清連の名がみえ、建武五年『浅利清連注進状』が残っている。
清連は当初南朝方であったが、翌二年の足利尊氏の反乱に際して北朝方に与し、鹿角の成田、及びその背後にいる南部氏など南朝方と激しく戦った。延元元年(建武三年=1336)、清連は曽我貞光の一族曽我光俊・同光時らとともに鹿角大里城の成田小次郎を攻めたが、南部師行の支援をえた成田勢によって曽我・浅利勢は敗退したという。翌延元二年にも、曽我・浅利勢は鹿角に攻め込み、宮方の楯三ケ所を攻め落としている。以後、曽我氏が勢力を拡大し、北朝方有利に展開するようになり、比内地方は浅利氏が支配するところとなったようだ。
その後、1350年代になると比内郡領主として沙弥浄光が登場する。浄光は浅利氏が伝統的に支配してきた甲斐浅利郷を譲渡しているから、浅利氏惣領であったとみて間違いないだろう。文和三年(1354)の沙弥浄光譲状によれば、南北朝期の浅利氏は甲斐国浅利郡と比内郡を所領としていたことが知られる。
さらに、紀州熊野に伝わる『米良文書』によると、比内徳子(独鈷)郷の浅利氏が嘉吉元年(1441)七月、由利に住む先達の先導で那智に願文を奉じている。このことから、この時点では浅利氏が比内の独鈷に拠点をおいていたことがわかる。そのほか、「米良文書」には浅利の記録が多く含まれており、浅利氏は米代川舟運と日本海海運を媒介として熊野に帰依していたのであろう。
室町時代における浅利氏の動向としては、松峯神社を比内庄司浅利家代々が行ったこと、応永二十五年(1417)『時宗過去帳』に浅利氏阿弥陀仏七名、一房一名がみえる。さらに、永享十二年(1440)の結城合戦において甲斐浅利氏が参加したこと、嘉吉から長禄年間(1441〜57)の間の『円福寺書状』には、八戸政経宛に「浅利殿云々」とみえている。しかし、これら文書に残された浅利氏の関係や系譜などの詳細は明確ではない。
浅利氏の勢力恢復
南北朝時代の動乱期の浅利氏に関しては、『沙弥浄光譲状』や『南部文書』などのわずかな史料から比内地方に対する支配の様子がうかがわれる。やがて、南北朝の内乱のなかで比内地方における浅利氏の勢力は後退し、桧山地方に勢力を拡大してきた安東氏と、仙北・比内地方に勢力を拡大しようとする南部氏との対立の間で揺れ動いていたものであろう。
室町時代における浅利氏については、史料上からその動向を探ることはできない。しかし、その間も浅利氏は比内地方に小さいながらも勢力を維持し、大勢力である安東・南部氏の対立を利用して生きのびたようだ。そして、十六世紀初頭に甲斐国から浅利氏本流の浅利則頼が移住するにおよんで比内地方における勢力の恢復を図ったものと考えられる。
浅利則頼の比内移住に関して、『独鈷村旧記』によれば、天文年中(1532〜53)に甲斐から赤利又(明利又)に移住、ついで十狐(独鈷)に城を築いて比内を領有したといい、一方、『長崎氏旧記』には、永正十五年(1518)に津軽から比内に移り、当初赤利又にいたが、やがて十狐に一城を築いて、比内中心部に進出し、比内地方を領有したと記されている。
戦国時代の初期、南部氏と安東氏の対立を利用しながら生き延びざるをえなかった浅利氏は、比内地方の辺境に位置する赤利又に拠っていたものと想像される。そして、『浅利氏正論』は、阿仁地方の鉱山資源をもとに力を蓄積したいったのだとしている。このように比内の辺境に細々と勢力を保っていた比内浅利氏のもとに、甲斐の浅利則頼が合流して、ふたたび比内地方に勢力を盛り返すために十狐に拠点を築いたものと考えられる。十狐城主には、もともと南部氏の被官である十狐次郎五郎がいたものに、則頼を大将とした浅利勢が夜襲をかけて攻め落としたとする説もある。
いずれにしろ、十狐城主となった則頼は、永正十七年(1518)、笹館城を築き弟の頼重を城代とし、さらに花岡城を築いてもうひとりの弟定頼を城代としておき、比内地方に勢力を拡大していったのである。かくして、比内地方における勢力の恢復を実現した浅利則頼は、天文十九年(1550)十狐において死去したと伝えられている。
浅利則頼の事蹟、諸説
浅利則頼は衰退のなかにあった比内浅利氏を中興した人物といえるが、則頼の具体的事跡はほとんど残っていない。
『坊沢・長崎文書』所収の「主人則頼系図」には、「俗称浅利与市、あるいは兵部大輔と称した」とあるが、『奥羽永慶軍記』には浅利兵部少輔と記述されている。また没年は、「下川沿・佐藤文書」所収の『浅利与市則頼分限帳』では天文十九年六月十八日となっている。永慶軍記では則頼は天正十七年(1589)の湊合戦に参加したことになっており、記述がそれぞれ錯綜しているが、没年は則頼分限帳が正しいと判断される。そして、『浅利則頼侍分限帳』には、則頼は本拠を独鈷に置き、笹館城に浅利勘兵衞、花岡城に同治郎吉、八木橋城に同及蘭をそれぞれ置くなど、一族を三支城に配置し、家老を中野・茂内・麻当・新田の各村に一名ずつ、独鈷には十一名をそれぞれ置いていたと記されている。
分限帳の記述から、浅利氏の家臣団編成が、村落に居住する村落領主をそのまま村に置いて家老に充てるとともに、一方では村落領主を本拠独鈷に集めていることが知られる。当時、中央では城下町が形成され、兵農分離が進行していたが、浅利氏の領国支配はいまだ旧態であった。とはいえ、それは北羽地方の国人衆に共通するものであったと判断される。
比内浅利氏は、則頼が登場したことで小さいながら戦国大名へと飛躍することができた。そして、佐竹文書中の浅利氏系図などは、系を則頼とその兄弟から起して「其の先は不知」となっている。則頼が甲斐から移住してきたという説も、それを裏づける基本史料に乏しく、とくに戦国時代に入ってから移住してきたというのは時代相からも信をおきにくい。また、『浅利軍記』には「則頼は生国甲斐で、奥州に下り津軽に住す」とあるが、『浅利軍記』は荒唐無稽な記述が多く、注意を要すべきものとされており、その記述をそのままに信じることはできない。
いずれにしろ、浅利氏は則頼の一代で勢力を拡大したことだけは疑いのないことといえよう。
家中の争乱
則頼のあとは、嫡男の則祐が継いだ。このころになると、戦国争乱は一層激しさを加え、南部氏は比内に圧力を加えるようになり、安東氏も阿仁地方を掌握し、比内と境を接するまでに領国を拡大した。さらに、北方には南部氏から独立を目指す大浦氏が割拠し、比内浅利氏の脅威となりつつあった。
このような情勢下で、浅利氏が比内を維持していくには、これらのいずれかの勢力と手を結ぶしかなかった。そのような永禄五年(1562)、安東愛季が突如として扇田長岡城を攻撃し、浅利則祐は敗れて自害した。『長崎氏旧記』によれば、「秋田領主安東太郎愛季との不和が原因、戦いに利あらず」として、秋田氏との間に抗争があり、その戦いが不利となって自害したということしか分からない。のちに、佐竹氏の家臣となった浅利氏が提出した系図には則祐は抹殺されていることから、則祐の自害に関しては何らかの謀略があったようにも想像される。
則祐の死後は、その弟の勝頼が安東氏の臣下の比内領主として登場してくる。『比内町史』によれば、「則頼の苦労に、嫡子則祐と二男勝頼の仲の悪さがあった。二人は腹違いの兄弟で、浅利の竜虎とよばれる俊秀であったという。家臣は二派に分かれて、それに一族までが加担する情勢となったが、則頼は嫡子の則祐に家督を譲った。これを不満として勝頼と一党は安東愛季と結び、長岡城を攻撃、則祐を生害に追い込んだ」とある。
則祐の死は安東氏の急襲によるものであったとはいえ、実際のところは家督争いがもたらした結果と思われる。家督を奪った勝頼は、則祐を浅利氏の過去帳から抹殺する暴挙を行い、みずからの立場を正統化しようとしている。
秋田氏の麾下に属す
永禄九年(1566)、秋田愛季が臣浅利某に鹿角谷内城を襲撃させた。浅利某とは浅利勝頼のことで、谷内城主は長牛(一戸)友義であった。このときの戦いで勝頼は、谷内城を攻略できなかった。翌年、愛季は大高主馬を大将に比内(浅利氏)・阿仁・松前・由利や鹿角の武士六千を率いさせ、ふたたび谷内城を攻撃させた。この戦いには三戸南部晴政も援兵を送って長牛友義を援助したが、戦いは南部方の敗北となり、鹿角は秋田氏の支配するところとなった。しかし、南部晴政は永禄十二年に大軍を派遣して鹿角をふたたび支配下に収めている。
このように、則祐のあと浅利氏の家督となった勝頼は秋田(安東)氏の被官として活躍したが、秋田氏被官のなかでは最大の勢力を持ち独立性も強く、やがて小さいながらも戦国大名として自立を目指すようになった。しかし、比内地方は秋田・南部・津軽の接点にあることから、南部・大浦(津軽)氏と対立する秋田氏にとって、比内地方の支配権を確立しておくことは不可欠なことで、浅利氏に対しても強い統制が行われた。やがて、天正年間(1573〜)になると、秋田氏の注意は南方の由利地方に向けられるようになった。これを好機とした勝頼は、独立のための行動を起こすようになり秋田氏との間で抗争となった。
勝頼は乱暴ではあったが、それだけに勇猛で戦闘に強かった。両者の抗争は年々激化し、天正九年ごろからはさらに激戦となり、秋田氏と浅利氏の間で戦いが繰り返された。戦いはほぼ浅利勢が勝利を収め、ついに秋田氏も戦いを続ける愚を思って和睦の提案をした。そして、天正十一年三月、愛季は和睦の話し合いと称して浅利左衛門尉義正(勝頼)を桧山城に招き、酒宴の最中に愛季の家臣深持・松前らが義正を殺害した。
『長崎氏旧記』には、天正十年、秋田城之介(愛季)が和睦のためと称して長岡城を訪れ、以前から愛季に通じていた勝頼の家臣生内権助が、酒宴の席で勝頼を刺殺したという。秋田氏との局地戦ではおおむね勝頼が勝利をおさめたが、政略的には秋田氏には及ばなかったといえよう。
いずれにしろ、勝頼は秋田氏によって謀殺され、秋田・浅利の対立は一段落し、勝頼の子頼平は津軽為信のもとに逃れて身を寄せた。こうして、比内地方はふたたび秋田氏が掌握するところとなった。
浅利氏の復活
天正十七年、南部氏の計略によって比内が南部領となる事件が起った。その結果、比内をめぐって秋田氏と南部氏との間で合戦となった。翌十八年、南部信直が九戸政実の叛乱に手を焼いている隙をねらった秋田実季は津軽為信と結んで、比内を南部氏から奪還した。このとき秋田実季は津軽為信の斡旋もあって、津軽に身を寄せていた浅利頼平を比内に還住させたのである。こうして、浅利氏は秋田氏の臣下として比内に返り咲くことができた。
それまで、頼平は津軽氏の支援を得て、天正十二年に比内へ、同十四年には大館城へ、同十五年には比内の所々の城を奪回していたというが、定かではない。浅利頼平の比内還住によって、実季は弟の実時を大館城代とし、領外の敵に備えさせるとともに、浅利氏に対する目付けとした。
このころになると、中央の情勢は大きな変化をとげていた。天正十年六月、天下統一に邁進していた織田信長が本能寺の変で横死した。その事業を継承した羽柴(豊臣)秀吉は、対抗勢力をつぎつぎと斥け、四国、九州を平定し、着実に天下統一を進めていた。そして、天正十八年(1590)、秀吉は小田原征伐を開始し、秋田・小野寺・南部・最上の奥羽諸将や、南部からの独立を目論む津軽氏らが小田原に参陣して秀吉に臣従した。
その後の秀吉朱印状によって比内は秋田郡に編入され、浅利頼平は秋田実季の家臣となり、七千三百石の知行地を与えられた。ただし、うちの二千石は実季の蔵入地に指定され、頼平はその代官を兼ねることになった。この処遇に頼平が満足すれば問題はなかった。しかし、頼平は秋田氏の下風に立つことを潔よしとせず、旧臣の結束を固めつつ、後援者である津軽為信を通じて、独立した領主になるための中央政界工作を開始した。そして、豊臣政権の官僚である浅野・木村・片桐氏のほか、徳川家康にも接近をはかった。
浅利氏の没落
文禄二年(1593)、ついに両者の紛争が再燃した。この年、秋田実季は年貢算用を行ったところ、前年の文禄の役のさいの軍役金の一部が未納であることが明るみに出た。これをめぐって秋田・浅利は争論となり、頼平は上洛して直接秀吉に奉公したい旨を訴えるまでに事態は悪化した。幸い、木村常陸介の仲裁で、軍役金の未納分は用捨(容赦)することで一応の解決をみせた。
ところが、翌年にも浅利氏は納入を渋ったため、実季は比内に軍勢を入れ、物成を押収するとともに浅利氏支配下の村を焼き払った。そして、翌文禄四年八月、秋田・浅利両氏は米代川をはさんで対峙し、戦闘を繰り返すようになり、それは慶長元年(1596)まで続いた。
文禄三年(1594)、秋田実季は浅利氏との紛争解決のために上洛した。慶長元年、浅野長吉は佐々正孝に対して両者の調停に乗り出すように指示を与えた。そして、四月、前田利家から浅利氏に対して直接の指示が出された。頼平は隠居して比内に住み、妻子は秋田に置くべきである。また軍役は秋田並みに負担し、紛争後に築いた城は破却することを命じる、というものであった。これは、ほとんど実季の要求に添う内容であった。
ここに至っても頼平はあきらめず、片桐且元に訴え、なんとか形勢を挽回しようと図った。慶長二年、頼平は片桐且元の要請で上洛した。浅利氏のこのように執拗な独立工作が展開できた背景には、豊臣政権内部の指揮系統が一本化されていないことがあった。すなわち、石田・増田らのグループと浅野・木村らのグループがそれぞれ独自の判断で事を処理することがしばしばだったのである。そして頼平は浅野らのグループに働きかけ、浅野らもこれを支援する動きをみせたのである。
 さらに浅利氏の重臣である片山・八木橋らが実季支援にまわり、津軽為信が浅利氏の背後についていたことも事態を複雑にしていた。しかし、事態は秋田実季の有利に展開し、次第に浅利氏は孤立化していった。そして、慶長三年一月、頼平は大坂で急死してしまった。『浅利軍記』は頼平の死を「毒殺された」としているが、おそらくそうであったと思われる。こうして、鎌倉期から比内郡地頭として活動を続けてきた浅利氏は、悲劇的な最期を迎えたのであった。
さらに浅利氏の重臣である片山・八木橋らが実季支援にまわり、津軽為信が浅利氏の背後についていたことも事態を複雑にしていた。しかし、事態は秋田実季の有利に展開し、次第に浅利氏は孤立化していった。そして、慶長三年一月、頼平は大坂で急死してしまった。『浅利軍記』は頼平の死を「毒殺された」としているが、おそらくそうであったと思われる。こうして、鎌倉期から比内郡地頭として活動を続けてきた浅利氏は、悲劇的な最期を迎えたのであった。
浅利氏における戦国後期の当主は則祐が生害、勝頼は謀殺、そして頼平は毒殺と、その背後には秋田氏の策謀があった。まことに、非運の一族であったといえよう。頼平が死去してのちの浅利氏一族は、佐竹氏に鷹匠として仕えて、近世に生き残ったと伝えられている。・2006年3月25日
・家紋:近世浅利氏が用いた雁金
【参考資料:東北大名の研究/比内町史/秋田の中世・浅利氏 ほか】
→ダイジェストページ
■参考略系図
浅利氏の系図は鎌倉時代から室町時代にかけて不明な点が多い。また、朝頼以降も諸本が伝えられており、そのいずれが正確なものかは、いまとなっては判明が困難としかいいようがない。比内浅利氏と戦国時代に甲斐武田氏に仕えた浅利氏との系譜的関係も詳らかではない。下記系図は諸本ある浅利氏系図を校合したものを参考として掲載した。
|
|
応仁の乱当時の守護大名から国人層に至るまでの諸家の家紋
二百六十ほどが記録された武家家紋の研究には欠かせない史料…
|
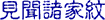

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
日本各地に残る戦国山城を近畿地方を中心に訪ね登り、
乱世に身を処した戦国武士たちの生きた時代を城址で実感する。
|

|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
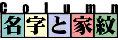
|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|

|
|

