
小川氏
二つ鷹の羽
(武蔵七党のうち日奉姓西党)
|

|
中世、薩摩国甑島の領主として知られる小川氏は、武蔵七党の一である日奉姓西党から出たという。
日奉姓西党は武蔵守として赴任した藤原宗頼が武蔵国に土着したことに始まり、系図によれば宗頼の孫宗忠が西内大夫を称している。宗頼の子孫は国衙の役人として続いたようで、その居住地が国衙の西方にあったことから西を名乗ったようだ。宗頼の長男は西太郎宗守、次男宗貞は西二郎を名乗り、宗貞の長男宗綱は西貫主を号している。貫主は蔵人頭の異称で、頭となる者、主だった者という意味も有した。村山貫主、丹貫主など武蔵七党の始祖となる人物が多く称しており、蔵人頭に任じられていなくても一族(党)を統率する者が私称したようだ。
さて、宗綱の系が西党の嫡流となり、その二男上田二郎の子宗弘は西多摩郡東秋留村の小川牧(小河郷)に住して小川(小河)太郎入道を名乗り小川氏の祖となった。その他、西党からは長沼、稲毛、平山、由木、立河、二宮、由井、小宮氏らが分出して、多摩郡を中心として都築・橘樹郡に一族が広まった。
小川氏の発祥
小川(小河)宗弘は国衙の役人であるかたわら、小川郷の開発につとめ、小川牧を別当として管領、郷の氏神である二宮神社の神主職を掌握して勢力を広げていったようだ。当時、律令制による兵制は廃止されており、国内の治安を維持するため国衙には国司の指揮する兵士がいたが、それは国司の私的従者たちであった。宗弘ら在地開発領主らは郷・牧の官人や庶子を私兵として、自領内の治安維持に努めていた。ちなみに、律令制下で国軍を司った兵部省を引き継いでいたのは左右馬寮で、そこに勤める役人は中央国家の軍事警察力を支える人々であった。宗弘は小川牧の別当として左右馬寮との関わりを持ち、ときには左右馬寮の長官から京都警固の命を受けて上洛することもあったのではなかろうか。かくして、小川氏は官人系開発領主として武士化していったのである。
平安時代の末期、 武士の棟梁と目される源氏や平家が平安貴族の走狗として保元・平治の乱に活躍、やがて貴族に代わって平家が全盛を迎えると小川氏ら在地開発領主も安穏とはしていられなくなった。
治承四年(1180)、平治の乱に敗れて伊豆に流されていた源頼朝が、三浦氏、北条氏らの支援を得て平家打倒の兵を挙げ伊豆目代の山本兼隆を討った。しかし、石橋山の合戦で敗れると、三浦氏が衣笠城に籠って頼朝は辛うじて安房へと逃れた。対する平家方は畠山重忠が衣笠城を攻撃、その軍には武蔵七党の武士らが加わっていた。おそらく、小川氏も同族の二宮氏・小宮氏らとともに参加していたものと思われる。
その後、安房の頼朝のもとには上総・下総の武士たちが馳せ参じ、さらに武蔵武士たちも来集してきて、相模に入国したときには雲霞のような軍兵がいたと『吾妻鏡』に記されている。相模国鎌倉に本拠をおいた頼朝は、東国における武士の棟梁となり、武士たちは頼朝の家人となり主従関係を結んだ。小川氏も二宮氏・小宮氏とともに頼朝の御家人となり、本領を安堵されたのであった。以後、頼朝は東国武士を率いて、平家との戦いを制して鎌倉幕府を開くことになるのである。
歴史への登場
平家との戦いにおける一の谷の合戦では小河小次郎、平山武者所季重ら西党の武士が義経の配下に見えている。また、平家が滅亡したのち、頼朝の推挙をうけないまま任官して叱責を受けた武士の一人に小河馬允がいた。馬允は左右馬寮の三等官で、小川牧を管領した小川氏に相応しいものであった。しかし、頼朝の叱責を受けた武士たちが、ただちに官を返上したことはいうまでもないだろう。
鎌倉幕府を樹立した頼朝が、建久元年(1190)に上洛したときの随兵の中に小川二郎、二宮小太郎、小宮七郎がいた。ついで同四年の的始の射手に二宮弥次郎が選ばれている。その他『吾妻鏡』には、小川氏の名が散見しており鎌倉御家人として一所懸命に勤めていたことが知られる。
頼朝の死後、北条氏が権勢を振るうようになり、幕府樹立に活躍した有力御家人たちは北条氏の謀略で淘汰されていった。やがて、三浦一族で侍所別当の和田義盛が北条氏と対立するようになり、建暦三年(1213)、和田の乱が勃発した。乱は北条義時率いる幕府方の勝利となり、義盛に味方した武蔵七党の横山党は壊滅的打撃を受けた。一方、小川氏ら西党は幕府方に味方したようで、戦死者の一人に小川馬太郎がいた。馬太郎の死によって小川氏は所領をまっとうすることができたのであった。
承久元年(1219)、源実朝が暗殺され源氏の嫡流の血筋が断絶してしまった。北条義時は頼朝の甥にあたる九条道家の子頼経を新将軍に迎えたが、この幕府の混乱をみた後鳥羽上皇は幕府打倒の謀略をめぐらし、承久三年に倒幕の軍を起こした。承久の乱であり、合戦は幕府軍の大勝利に終わった。この乱に際して小川季能は合戦最大の激戦地となった宇治川の合戦に活躍、戦後、恩賞として肥後国益城郡のうちと薩摩国甑島を賜った。季能とともに出陣した小宮氏も伊予国弓削島の地頭職を得ており、小川・小宮氏らの西党諸氏は武蔵のみならず全国へと広まっていたのであった。
甑島小川氏
当時の武士は惣領は本国にあって、遠方の所領には庶子を代官として送る例が多かった。新恩として得た甑島へ赴いたのは、季能の庶子小川小次郎季直であったという。季直の入島の時期は明確ではないが、前の支配者との間で合戦沙汰となり、いまも甑島にはそのときの合戦で討死した「七人合頭」「八人合頭」と呼ばれる戦没者の墓が残されている。なんとか甑島に入った季直と一党は、鶴亀城を築き手打村を本拠にして甑島に土着したのであった。
南北朝時代を迎えると、甑島小川氏は武家方として活躍、戦国時代には島津氏に属していたようだ。その間における小川氏の事績は明確ではないが、甑島の領主として存続したことは間違いない。『甑島惣廟諏訪社御神事由緒』には、明応二年(1493)より文禄四年(1595)までの百年間における神事に関わった小川氏の人々の名が記されている。その名乗りをみると小川氏が通字とした「季」の字を持っており、西党小川氏の人物であったことは疑いない。このように小川氏が甑島領主として諏訪社の神事を行い、中世を通じて甑島を支配していたが、小川有季のとき太閤検地による所行替えで甑島を去ることになった。
文禄四年のことで、有季は郎党二百余騎を率いて新知行地として与えられた田布施へと移住していったのである。その後の甑島は島津氏の直轄地となり代官が治めるところとなった。田布施へ移り住んだ有季は吹上浜で憤死したとも、有馬氏の謀略にあって谷山で討たれたともいわれる。小川氏系図によれば有季のあとは娘婿伊勢内記の子が継いでいるが、小次郎季直以来四百年にわたる甑島小川氏の歴史は有季の代で幕を閉じたのであった。
小川氏余談
ところで、本貫地に残った嫡流小川氏はどのようになったのであろうか。同族として鎌倉御家人に連なった小宮氏、二宮氏らは戦国時代末期まで勢力を保っているが小川氏の名はまったく見られない。小川氏系図を見ると嫡流小川氏は様丸のところで終わっており、甑島に渡った季直以降の記載はない。一方、甑島小川氏系図では季直以降の代々の記述はあるが、嫡流は様丸の代で終わっている。このことは、様丸の代に嫡流小川氏が滅亡、あるいは没落したことを示している。
小川氏は鎌倉幕府の有力御家人であった三浦氏と関係が深く、季直の父季能は三浦泰村と乳兄弟であったという。『秋川市史』によれば、三浦氏と北条氏が戦った宝治の合戦(1247)に際して小川氏嫡流は三浦氏に味方した。その結果、乱後に所領没収となり、一族は没落したのであろうと推察されている。おそらくその通りであろうと思われ、武蔵武士小川氏の血脈は遠く薩摩国甑島に紡がれたのであった。
甑島小川氏の家紋は「二つ鷹羽」だが、西党の同族である小宮氏、平山氏も鷹羽紋を用いている。本貫の地を遠く離れ、一族としては遠い関係になりながらも、それぞれの家が繋がっている。家の歴史とはまことに数奇なものである。
【参考資料:武蔵武士・秋川市史・甑島移住史 ほか】
■参考略系図
・武蔵武士・秋川市史・甑島移住史から作成。小川氏は日奉姓であり、祖宗頼を藤原道隆の孫としているのは明らかな付会であろう。
|
|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。
なんとも気になる名字と家紋の関係を
モット詳しく
探ってみませんか。
|
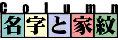

|
どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|

|
|

