


.  真田昌幸
真田昌幸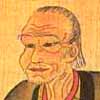 ●天文十六年(1547)〜慶長十六年(1611)
●天文十六年(1547)〜慶長十六年(1611)●信濃上田城主。武田氏に仕えてはじめ武藤氏を継ぎ、のち旧姓真田氏に復し上田城を築いた。武田氏滅亡後、昌幸は 信長に属し、信長死後は家康に属した。しかし、家康より沼田城の明け渡しを命じられてこれを拒絶。家康と昌幸とは 合戦におよんだが、絶妙の戦い振りを見せて徳川軍を撃退した。関ヶ原合戦では西軍に従い、秀忠軍を上田城に 釘付けして関ヶ原の決戦に遅参させた。西軍の敗戦後、二男幸村とともに高野山に蟄居。以後、世に出ることなく 大坂の陣を前にして生涯を閉じた。  武田信玄
武田信玄●大永元年(1521)〜天正元年(1573) ●甲斐国守護。大膳大夫.信濃守。幼名太郎、諱は晴信。武田信虎の長男。三条公頼の女を娶る。永禄二年入道して信玄となる。元亀三年西上の途につき。翌年四月駒場にて病死。  上杉謙信
上杉謙信●享禄三年(1530)〜天正六年(1578) ●越後守護代長尾為景の末子、諱は景虎。兄晴景に代わって越後の戦国大名となる。上杉憲政より関東管領職と上杉家を相続。二度上落。第四回川中島の合戦は有名。織田信長軍と手取川で戦い激破。  上杉景勝
上杉景勝●弘治元年(1555)〜元和九年(1623) ●上杉謙信の一族長尾政景の次男として生まれ、母は謙信の姉であった。父政景の死後、謙信に育てられのちに その養子となった。謙信の死後、もう一人の養子である景虎との家督争い「御館の乱」に勝利して上杉氏の当主となった。 豊臣秀吉に仕え五大老の一人となり、会津百万石の大大名となった。秀吉の死後、石田三成に呼応して、 徳川家康に反旗を翻した。 しかし、三成が関ヶ原で敗れたため家康に降伏し、米沢三十万石に減移され、米沢藩祖となった。
 直江兼続
直江兼続●永禄三年(1560)〜元和五年(1619) ●越後与板城主樋口兼豊の子で、直江氏を継いだ。上杉景勝の家老として知られる。兼続は文武に秀でた人物として 知られるが、武に関しては、関ヶ原の戦いの時に、最上方の長谷堂城攻めが知られるばかりである。兼続の真骨頂は、 上杉家の執政としての実績と学問を奨励した政治家としての面にあった。関ヶ原の戦いに際して家康に送った 「直江状」が有名だが、いまは疑問視されている。 とはいえ、上杉景勝に反家康の行動をとらせたのは、やはり兼続であっただろう。  明智光秀
明智光秀●享禄元年?〜天正十年(1582) ●近江・丹波で五十万石を領知。安芸守光綱の子という。織田信長に従い、足利義昭の上洛に尽力。本能寺を急襲して、信長を自殺させた。山崎合戦では羽柴秀吉に惨敗。小栗栖で刺殺された。  斎藤道三
斎藤道三 ●生年不詳〜弘治二年(1556)
●生年不詳〜弘治二年(1556)●美濃の戦国大名。『軍記物』によれば、京妙覚寺で修行していたが、還俗して山城国の灯油商奈良屋の女婿となり、 灯油を売るため美濃に往来していたという。その後、守護の弟土岐頼芸に仕えて、頭角をあらわし、ついには頼芸を追放、 美濃の実権を握った。しかし最近の研究で、妙覚寺で修行し俗した僧とは父・新左衛門尉のことであるといわれ、 父子二代で「国盗り」したという説が有力である。美濃国主となった道三であったが、晩年は嫡男義龍と対立し 長良川合戦で敗死した。  今川義元
今川義元●永正十六年(1519)〜永禄三年(1560) ●駿河の大名。兄氏輝の没後、家督を継ぐ。甲斐の武田信玄、相模の北条氏康と同盟して、西方への勢力拡大を図ったが、織田信長との桶狭間の戦いに敗れて討ち死にする。  徳川家康
徳川家康●天文十一年(1542)〜元和二年(1616) ●江戸幕府の創始者。松平広忠の長男。三河を平定し徳川氏に改姓。三・遠・駿・甲・信五ケ国を領有す。豊臣政権下で関東移封、五大老の筆頭。大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし天下統一を完成。  織田信長
織田信長●天文三年(1534)〜天正十年(1582) ●織田信秀の嫡男。桶狭間の戦いで今川義元を倒し、尾張・美濃の軍事力を背景に足利義昭を奉じて上洛。天下布武の理念に燃えて全国統一を目指すが、本能寺の変に遭い未完の天下となった。  豊臣秀吉
豊臣秀吉●天文六年(1537)〜慶長三年(1598) ●武家としてはじめて関白に任官した。本能寺の変後に対立武将や戦国大名を屈服させて天下統一した。六歳の秀頼を遺して他界したため、豊臣家は衰亡の一途を辿り、大坂夏の陣で滅亡した。  前田利家
前田利家●天文七年(1538)〜慶長四年(1599) ●加賀藩主前田家の祖。尾張荒子出生。織田信長に仕え、各地を転戦。功により越前府中、さらに能登一国、後に河北・石川二郡を加え、金沢に移る。五大老の一人。豊臣政権下で家康に次ぐ実力をもっった。 |





|

|
