
 |

【補遺_3】 簗田氏/矢島氏/遊佐氏 |

|
簗田氏 下総国関宿城【水葵三本立ち】 名字の地は足利庄に隣接する下野国梁田郡の梁田御厨で、平安期に足利氏に属したと伝える。鎌倉期の事蹟は明らかでなく、室町期にいたり鎌倉公方足利氏の家臣として急速に台頭する。名字の地から鎌倉公方の料所下河辺荘に移るのが室町初期でやがて関宿を拠点に勢力を拡大していくのである。 簗田家中興の祖は満助で公方満兼の一字を拝領し、その娘は公方持氏に嫁して成氏を生んだ。以後、簗田氏は晴助に至るまでいずれも公方の一字を与えられて名乗りとしている。 永禄三年(1560)越後上杉氏の関東出兵に際し、晴助は一族を率いて参陣、これと結び付いて藤氏を公方に擁立し、後北条氏に対抗しようと企てた。しかし結局、失敗に終わり、天正二年(1574)には北条氏の攻撃を受けて関宿城が落城、持助は水海城に退いた。 |
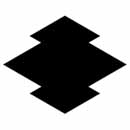
|
矢島氏 出羽国根城館【松皮菱】 矢島氏は仁賀保氏と同族と伝えられ、大井氏とも称しているので、甲斐源氏小笠原氏流の大井朝光の後裔と思われる。 戦国期の矢島氏は、仁賀保氏と並ぶ由利郡の二大勢力であり、両者は抗争を繰り返した。矢島満安と仁賀保氏の抗争は、永禄三年から文禄元年までの間に十数回に及んでいる。矢島氏は由利諸党の中では孤立化した状態にあり、満安は仁賀保氏との抗争が激化したため、本拠を根城館から新荘館に移したという。 天正十六年、矢島の地は仁賀保氏の領地となったという。天正十八年の小田原参陣、それに続く太閣検地、翌十九年の九戸の乱などに矢島氏の名は見い出せない。一方仁賀保挙誠は豊臣秀吉から所領を安堵されているが、そのなかには矢島地域も含まれており、この段階で満安は矢島の支配権を失っていたようだ。満安は秀吉から所領を安堵されなかったものと思われる。 文禄元年、満安は由利郡の諸氏の攻撃を受け、西馬音内に逃れた。翌二年西馬音内城主の小野寺茂道は、小野寺義道の疑いを受け軍勢を向けられ、満安は自害し、矢島氏は滅亡した。 |

|
遊佐氏 河内国若江城【木瓜】 藤原秀郷の末と伝えられ、出羽国飽海郡遊佐郷を本貫とする畠山氏の被官。南北朝期に畠山氏が奥州探題となったとき臣従したらしい。永徳二年畠山基国が河内守護に補任されたときは遊佐長護が守護代に任じられている。以後、本宗は代々河内守の官途を称した。 長禄四年、守護が義就から政長に更迭されて畠山氏の家督争いが激化すると、遊佐氏も両派に分かれ、国助・就家は義就に、河内守長直は政長に属して争った。応仁の乱前後を通して、軍事的には義就派の就家側が終始優勢で、河内を支配していたのはこの系統である。 戦国期の当主は長教で、かれは軍略にすぐれ畠山氏の実権をにぎり、三好長慶も彼のために苦杯をなめたが、長慶は和睦して長教の娘を娶り、姻戚関係を結んだ。しかし、それから三年後、長教は反長慶派の刺客によって、暗殺されてしまった。その子信教は高政に仕えて守護代となり、永禄十二年高政を遂い、その弟昭高を暗殺したりしたが、信長に殺された。 |
