
 |

【補遺_2】 長束氏/仁賀保氏/松永氏/溝口氏 |

|
長束氏 近江国水口城【唐花菱】 長束正家は、はじめ近江佐和山・大溝城主丹羽長秀、同長重に仕えた。出自は明らかではない。天正13年(1585)まで長重に仕えて越前府中城にいたが、財務に長じているのを秀吉に見込まれて、同年七月、秀吉の奉行衆に抜擢された。 天正19年には、やはり秀吉奉行の増田長盛とともに近江の検地を実施し、翌年には肥前名護屋城の造営を奉行、文禄三年(1594)には伏見城の造営に大きな役割を果たしている。翌年、大和郡山へ移封された増田長盛の跡を襲って近江水口五万石に封ぜられ大名に列し、以後累増して関ヶ原の戦い直前には十一万石を領し、従四位下侍従に昇っている。 関ヶ原の戦いでは、弟直吉とともに西軍に属し、正家は美濃南宮山に陣し、直吉は水口城を固めた。しかし、南宮布陣の大将吉川広家は平素より石田三成を憎み、戦前に家康への内応の契約をなしていたので正家は動けず、やむなく水口へ戻って同城を固守した。 |

|
仁賀保氏 出羽国山根館【一文字三つ星】 仁賀保氏は、甲斐源氏小笠原氏流の大井朝光の後裔と伝えられる。ただし、家紋の一文字三つ星は大江氏流の家紋であり、また、仁賀保氏の通字「挙」は大江氏の通字でもあることから、大江氏との関連も考えられる。いずれにしても、大井朝光の子友挙が信濃国大井荘から出羽国仁賀保に移ったのを始めとするらしい。戦国期には由利十二頭の中心的存在であった。 しかし、由利郡内の領主はいずれも小勢力であり、近隣勢力の影響を受けざるをえなかった。仁賀保氏は庄内の大宝寺氏の影響を受けていたため、小野寺氏との関係が密接であった矢島氏と抗争を繰り返した。 天正十八年、仁賀保挙誠は豊臣秀吉から所領を安堵された。その後常陸国武田に移封されたが、ふたたび仁賀保で一万石を与えられた。 挙誠の跡を継いだ良俊は七千石を知行し、弟誠政に二千石、誠次に千石を分知したが良俊に嗣子なく断絶。弟ふたりの系統が徳川旗本として存続した。 大井朝光−友挙…………重挙−挙晴−挙誠┬良俊 ├誠政 └誠次 |

|
松永氏 大和国信貴山城【蔦】 出自には諸説あって確証はないが、その姻戚関係から考えて畿内の出身であることは間違いない。久秀は若年から三好長慶の右筆となって活動していたと推測され、天文十一年には長慶の部将として南山城に進駐している。弟長頼も軍事的才幹をもって長慶に仕え、久秀よりもはやく独立の部将として活動している。天文二十二年、長慶が将軍足利義輝を京都から追放すると、久秀は伊勢貞孝らと京都の庶政を採決している。弟長頼は丹波八木城主として守護代内藤氏の名跡を継承する地位にあった。 永禄二年長慶から大和方面の軍事を委任されて、信貴山城主となり、翌年には大和をほぼ制圧、信貴山城に天守閣を造営している。長慶の没後、三好三人衆と共謀して将軍義輝を暗殺、のちに三人衆と対立、その内訌で東大寺大仏殿を炎上させている。永禄十一年織田信長と和睦して大和一国を安堵されたが、のちに信長に離反したが降伏、大和を安堵された。しかし天正四年またもや信長に反旗をかかげ、信貴山に籠城。織田信忠の包囲の前にあえなく陥落。名物の平蜘蛛の釜を砕いて自殺した。連歌師貞徳は孫にあたる。 ……… 某┬久秀−永種−貞徳 └長頼 |
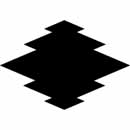
|
溝口氏 加賀国大聖寺城【掻摺菱】 清和源氏武田氏流逸見義重の後裔と伝える。義重は承久の変の功で美濃国大桑郷を拝領したという。この義重の子孫が尾張国溝口に溝口を称したという。 しかし、『溝口家譜』には逸見義政が常陸溝口村を賜り、戦国末期の勝政のとき、近江・美濃に移ったとするなど混乱がみられる。史料的には、尾張溝口氏は応永元年(1394)からみえ、溝口富之助が常安寺を再建したと伝える。同氏の拠城は豊場にあり、子孫は尾だ信長に仕えている。しかし、名字の地といわれる溝口と豊場では十数Ɠも離れており、溝口氏の出自は不明というほかはない。 ひとつの可能性として、遅くとも南北朝期から豊場に拠っていた溝口氏が織田氏に臣従したあと、その一族が、信長の重臣となった丹羽長秀の麾下に入ったとも考えられる。溝口氏が飛躍的に発展するのは秀勝の代からである。 |
