

|
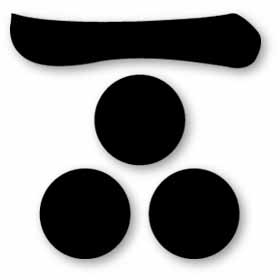
一文字に三つ星
 毛利氏の祖大江氏は、菅原氏と同じく土師氏の後裔であることは、日本書記、六国史、新撰姓氏禄などによって知られる。ところが、大江氏の場合、平城天皇の皇子阿保親王の子が本主であるとするものもある。しかし、これは、後世の仮冒といえものであろう。
毛利氏の祖大江氏は、菅原氏と同じく土師氏の後裔であることは、日本書記、六国史、新撰姓氏禄などによって知られる。ところが、大江氏の場合、平城天皇の皇子阿保親王の子が本主であるとするものもある。しかし、これは、後世の仮冒といえものであろう。
大江氏の本紋(定紋)「一文字に三つ星」は、阿保親王が一品の位であったことに因み、一品の字を紋章化したといわれている。紋の上では、その出自を皇室の裔としているのである。また、「一文字に三つ星」紋は、各地の大江氏系氏族の代表紋ともなっている。
「見聞諸家紋」を見ると、毛利氏の紋は「三つ星に吉文字」と出ている。これは三つ星に、嘉字である「吉」を「一文字」に替えて、配したものであろう。
しかし、正親町天皇から賜わったという「十六葉菊」、足利将軍から賜った「五七桐」や、元就が戦場で沢潟にとまったトンボを見て大勝を得たことにちなんだ「沢潟」も用いている。その他にも「丸に矢筈」「鶴丸」「八本矢車」など、全部数えると10種近くにもなる。
これらの紋は天皇の御前に伺候するときには「五七桐」を、元就の墓参には「沢潟」をというように。それぞれの場によって使い分けていたようだ。また、本・支によって「一」の字を筆書体や角字にする。あるいは尻上がりの一、尻下がりの一などにして本・支を区別している。







●左上から「十六葉菊」「五七桐」「抱き沢潟」「鶴丸」「八本矢車」「丸に矢筈」「立ち沢潟」
|
|

|
戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。
その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。
|


|
どこの家にも必ずある家紋。家紋にはいったい、
どのような意味が隠されているのでしょうか。
|


|
|



