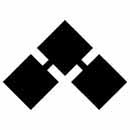甲斐の名族にして、一蓮寺過去帳に「応安七年十二月六日、持阿(原氏)。長禄二年十二月二十八日、道阿(原右衛門四郎)」等の名が見える。また、羽尾記を見れば「原監物、原隼人」らの名が見え、一説によればこの原氏は、清和源氏土岐光行の後裔とも伝える。 ・右:参考略系図 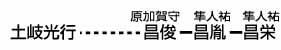 原加賀守昌俊は、信虎・信玄二代に仕えた「陣場奉行」で、その子が隼人佑昌胤(昌勝)で父の没後、同じく陣場奉行を務めた。また行政も担当したが、合戦には百二十騎を従えて戦陣に臨んだ。内五十騎は外様近習衆であった。外様近習衆とは「信玄公外様近習」といわれて百騎あった。諸国から集まった牢人部隊であったが、合戦の場数を踏んだ猛者揃いで、千騎以上の働きをした信玄秘蔵の武士団であった。
原加賀守昌俊は、信虎・信玄二代に仕えた「陣場奉行」で、その子が隼人佑昌胤(昌勝)で父の没後、同じく陣場奉行を務めた。また行政も担当したが、合戦には百二十騎を従えて戦陣に臨んだ。内五十騎は外様近習衆であった。外様近習衆とは「信玄公外様近習」といわれて百騎あった。諸国から集まった牢人部隊であったが、合戦の場数を踏んだ猛者揃いで、千騎以上の働きをした信玄秘蔵の武士団であった。天文十七年二月、信州上田原の合戦で板垣・甘利らが討死すると、あとを引き継ぎ、行政面ですぐれた手腕をみせた。だが、戦場での武功にこれといって取り立てるほどの働きはなかったようで、永禄四年、川中島の合戦を前にした割ケ嶽城攻めでは、十三ケ所も負傷して後退、川中島の合戦にはついに出陣できなかったほどである。 長篠の合戦では反対の急先鋒であったが、勝頼が出陣を決めると、決定に従い、昌胤ら陣場奉行も武器をとり、配下百二十騎を率いて敵陣に突入、壮烈な戦死をとげた。 原氏の家紋にどんな深山でも踏み迷わせず、目的地へ結び付ける、まじないのようにも思われていた「千切」紋があった。戦国時代南木曽の山間には、木曽義仲の後裔をとなえた木曽氏が、福島城に拠って勢力を保持していたが、木曽義昌の代、信玄に攻められて降った。そのとき武田氏の先鋒をつとめたのが、原隼人昌勝であった。原氏に「千切」紋があればこそ、迷路のごとき木曽攻めの先鋒を願いでたものらしい。 |





|